軍馬たちを門前に残し、臼砲によって破壊された鉄扉をくぐって砦の中へ走り込んだトゥパク・アマルたちは、咄嗟に、うっ、と呻いて、口と鼻を手の平で覆った。
(トゥパク・アマル様…これは……!)
早くも、じわっと込み上げる涙をたたえた目で、ロレンソがトゥパク・アマルを見た。
(ああ、アンドレスのやつ、どうやら、『あれ』を使ったらしい…)
トゥパク・アマルも、クシャミをこらえながら、視線で応える。
彼は、己の黒ビロードのマントを手早く引き千切って、口と鼻を覆うように顔に結びつけた。
他のインカ兵たちも、慌てて、各々、戦闘衣やマントの裾を千切って、即席のマスクを身に着けた。
目を覆うゴーグルもほしいところではあったが、この頃には、スパイス類の飛散は、そこそこ沈静化してきてはいたので、裸眼でも何とか持ち堪えられそうではある。
それでも、十分に、目の奥深くまでヒリヒリと沁みてはくるが…。
そうこうしている間に、まだスパイス弾の効果で弱っている敵の剣戟をかわして、転がるように4階部から1階まで駆け下りてきたアンドレスが、トゥパク・アマルたちの視界の中に飛び込んできた。
「トゥパク・アマル様――!!」
破壊された鉄扉から続々と雪崩込んでくるインカ兵たちの陣頭に立つ、漆黒の戦闘衣を纏った長身を瞬時に見出し、アンドレスは感極まって歓呼の叫びを上げた。
そんなアンドレスをトゥパク・アマルも真っ直ぐに見つめて、暫し言葉を呑んでいる。
戦闘衣も、頭髪も、何もかも、灰かぶり姫さながらに小麦粉や唐辛子に覆われ、全身は返り血まみれな上、顔も手足も火傷や切り傷だらけ――。
その酷い姿は、アンドレス本人が見ようものなら、愕然とせずにはいられぬことであろう。
火傷や大小の傷は、昼間の艦砲射撃の余熱の残る砦の石壁を、長距離に渡って、我武者羅に登り続けたためもあろう。
その後も、劣勢の中、ここまで戦い続けてくるのは並大抵のことではなかったはず。
トゥパク・アマルは、切れ長の目を細めて、深く頷いた。

いや、アンドレスだけではない。
彼と行動を共にしたインカ兵も黒人兵も、皆、目も当てられぬ風体であった。
だが、その姿にこそ、このような無謀な作戦に挑み、敢行し続けた、ひとかたならぬ忍耐と勇気の証しが刻まれているのだ。
ささくれ立った急峻な外壁を這いずり回って傷だらけの全身に、唐辛子や胡椒が沁みて激痛があろうに、恐らく、本人たちは、苛烈な戦いに追われ、そのような自身の痛みに気付く僅かな暇(いとま)さえ無かったことであろう。
「まだ戦いは終わっていない。
なれど、皆、ここまで良くやってくれた。
よくぞ、ここまで戦い抜き、持ち堪えてくれたな」
篤い思いのこもったトゥパク・アマルの声音に、アンドレス隊の兵たちは恍惚となりながら、頭(かぶり)を振った。
「勿体無きお言葉でございます。
我らは当然のことを……!」
そう答えつつも、込み上げる熱いものが胸中に溢れて、それ以上の言葉が続かない。
アンドレスもまた、まるで今頃になって胡椒や唐辛子の成分が効いてきたかのように、どうにも熱くなってたまらない鼻をすすり上げた。
そんな彼の耳元に、トゥパク・アマルの艶やかな低音が響きくる。
「アンドレス、よくぞ、皆を導いた。
砦に進軍する我らに対する援護にも、助けられたぞ」
(――!)
いよいよスパイスが染みてきたのか、それとも別の理由なのか、目元が潤んでくるのを、アンドレスは大きな瞳を見開いて懸命に堪えている。
一方、トゥパク・アマルの表情は、今再び、鷲のように鋭く峻厳さを増し、見るからに戦闘モードに切り替わっていく。
彼は、周囲の敵兵へと鋭利な視線を一閃させると、味方の軍団に向き直って、鞘から長剣をズバッと抜き放った。
彼ら新手のインカ兵を取り囲むようにして、今や正気を取り戻しつつあるスペイン兵たちが群れ成して、憎悪と復讐に燃えた眼をギラつかせ、次の瞬間にも斬りかかってこぬばかりである。
先の抜剣突撃の余韻が生々しく残る赤銅色の刀身を胸の高さに構え、トゥパク・アマルが猛々しく言い放つ。
「皆の者よ、まだ戦いはこれからと心得よ。
この砦の外では、インカ軍本隊7800の兵がビルカパサに率いられ、敵の大軍10000と熾烈な戦火を交えている。
敵大軍の武装は、これまで類を見ぬほどの重装備。
この砦の要塞砲をもって制する以外に手段は無い。
我らは、一刻も早く全ての要塞砲を占拠し、ビルカパサ軍を援護する」
トゥパク・アマルの号に鼓舞されたインカ兵たちが、オオオ!!と、轟くばかりの咆哮を上げて大気を熱く振わせながら、猛然と敵群れの中に斬り込んでいく。
先刻までの圧倒的優勢とは打って変わって、急転直下、一挙に劣勢な立場へ突き落とされたスペイン兵たちの形相は、さすがに必死の様相を呈している。
砦内部のスペイン兵は約1000。
対するインカ側は、もともとのアンドレス隊500の兵に、トゥパク・アマル軍やロレンソ軍による1700の援軍が加わって、今や、ざっと2200にも及ぶ数である。
門前で蹴散らされたスペイン守備隊は既にかなりの打撃を被っており、彼らの残党が砦内部の戦闘に加わってこようとも、インカ側の兵力優勢に変わりはなかった。
自軍に倍するインカ兵を相手にせねばならなくなったスペイン兵たちに圧しかかるプレッシャーは、ただならぬものであった。
しかし、それでも、プライドも意地もひときわ高く強固な彼らは、この重要な砦を断固として渡してなるものかと、決死の反撃を挑んでくる。
砦全体は、たちまち白熱した肉迫戦の坩堝(るつぼ)と化していった。

トゥパク・アマルたち援軍の到来によって、砦内部の空間は、その広大さにもかかわらず、先にも増して人口密度が高まり、大混雑となっている。
その雑多で濃密な空間で、無数の剣の林が打ち合い、それらの放つ金属音が殷々と鳴り渡る中、間隙を突くようにして、断続的に銃の発砲音が弾け飛ぶ。
昂ぶる人熱を全身に纏わりつかせながら、トゥパク・アマル自身もまた、我こそはと次々に打ち掛かり来る敵勢を相手に、鋼のごとき強靭な腕をしならせ、重厚な長剣を縦横無尽に振るっていた。
「トゥパク・アマル様!!」
加勢に走り込んできたアンドレスに、「わたしのことは案ずるな」と、トゥパク・アマルの鋭利な双瞼が相手の瞳の奥まで貫き通して言う。
「それより、そなたは、そなたの為すべきことをせよ」
「ですが、トゥパク・アマル様!
敵兵は、皆、トゥパク・アマル様を狙って、蟻のように群がってきているではありませんか!」
「それで良いのだ。
多数の敵に囲まれていた方が、狙撃兵は、わたしを狙いにくい」

言葉を呑んで息を詰めたアンドレスに、トゥパク・アマルが素早く肩を寄せて言う。
「それよりもアンドレス、我らが優勢な今のうちに、砦の武器庫と火薬庫を押さえよ」
断固たる口調に、アンドレスは、「御意!」と、即座に応じていた。
「それから、アンドレス、大事なことを聞き忘れていた。
アレッチェ殿は、どうなっている?」
アンドレスは、急に冷や水を浴びせられたような思いで唇を噛み締め、苦々しく首を振った。
「すいません…。
屋上階の火災に乗じて逃げられてしまってからは、全く姿を見ておらず、どこにいるのか――。
その後のアレッチェの所在も、動向も、掴めてはおりません」
アンドレスの返答に、トゥパク・アマルは研ぎ澄まされた面差しを思慮深くさせて、「そうか」と、短く答える。
「だが、恐らく、アレッチェ殿は、この砦から脱してはおるまい。
この砦を見捨てて、一人、逃走するような男ではない」
そうしている間にも、二人の腕は、絶え間なく敵勢と戦い続けている。
眼前で、また一人、己の手に掛かって床に崩れゆく敵兵の姿を目の端に捉えながら、アンドレスは、不意に、如何ともしがたい強い不安が突き上げてくるのを感じていた。
彼は、剣を手にしたまま、トゥパク・アマルの顔を見上げた。
長身のアンドレスよりも、トゥパク・アマルは、さらに頭一つ分は軽く身の丈がある。
「トゥパク・アマル様、くれぐれもお気を付けください。
こうして、アレッチェが、俺たちをここまで砦内でやりたい放題に野放しにしておいたのは、トゥパク・アマル様を砦内に誘(おび)き寄せるための罠だったのかもしれません…!」
突如、己の身内に沸き起こった不安を止めることができず、そのままを言葉にしながら、アンドレスは、不吉な予感に背筋が寒くなるのを覚えていた。

他方、トゥパク・アマルは、激しく剣を振いながらも、まだ平静な息遣いを保ったまま、物思わし気に答える。
「いや、そなたが申すように、アレッチェ殿がわたしを砦に呼び寄せるための罠にしては、あまりにスペイン兵の犠牲を出しすぎている。
これほど多勢のインカ側の援軍が砦に雪崩れ込めば、砦が危機に瀕することは、あの者とて承知していたはず。
彼に打つ手があったのならば、我らを砦に到達させぬための防衛策を、もっと早々に実行していたはずだ」
「では、アレッチェも、此度は為す術も無く、どこかに身を潜めて静観するしかなかったと?」
絞り出すようなアンドレスの言葉に、トゥパク・アマルも、「あの者が考えることは、わたしにも計り知れぬ。予断できぬことだけは確かだが」と、眉根を寄せた。
大きな琥珀色の瞳を揺らしながら、アンドレスがトゥパク・アマルを喰い入るように見据えている。
「俺には、あの執念深いアレッチェが、このまま引き下がるとは思えません。
特に、あの者の一番の狙いは、トゥパク・アマル様のお命です。
どうかくれぐれもお気を付けて――!」
アンドレスの言葉に、トゥパク・アマルは静かに微笑み、「そなたの言葉、心に留めおこう」と、頷いた。
そうしている間にも、インカ軍の大将を討ち取る絶好の機会とばかりに、敵は雲霞の如くトゥパク・アマルに群がってくる。
だが、その一方で、今や数的には優勢に転じているインカ兵たちが、それらの敵勢を圧倒する勢いで、トゥパク・アマルの加勢に飛び込んできていた。
それらの激しい鬩ぎ合いの中心で剛腕を振るいながら、トゥパク・アマルの鋭い目がアンドレスに決然と命じた。
(アンドレス、行け!
武器庫と火薬庫を、しかと頼んだぞ)
その視線に力強く頷き返し、アンドレスは、後ろ髪を引かれる思いながらも、味方の兵たちにトゥパク・アマルを託し、踵を返した。
(トゥパク・アマル様、アレッチェには、どうかお気を付けて――!)
そう心で叫びながら、武器庫に向かって突き進むアンドレスの周りにも、敵兵は四方八方から押し寄せてくる。
それらの軍勢を討ち払って我武者羅に道を斬り拓いていくアンドレスの傍に、疾風のごとく、鋭利な目をした褐色の若武者が華麗な剣捌きで飛び込んできた。
「アンドレス、加勢するぞ!」
その若者の凛々しい笑顔に、アンドレスも、パッと大きく顔を輝かせる。
「ロレンソ!!」
ひとしきり二人は敵と激しく剣を交えた後、さらに湧き出してくる敵兵たちと睨み合いながら、背中合わせの体勢で口早に言葉を交わし合った。
「ロレンソ、すまなかった。
あの時、屋上階で、マルセラがアレッチェにひどい目に合わされているのに、俺は、何もできなくて……」
アンドレスは、ずっと胸につかえていたことを苦し気に口にした。
「いや、そなたのせいではない。
わたしも、あの時、砦の麓に布陣していたものの、怒りに我を忘れ、すんでのところで、兵を率いて砦の射程内に飛び込むところであった。
トゥパク・アマル様が止めに来てくれていなければ、今頃は、わたしも、大勢の兵たちも、どうなっていたか分からない。
今思えば、全ては、アレッチェの計算ずくの挑発だったのだ」
そう語るロレンソの肩が、あの時の光景を思い出しているのであろう、激しい憤りに震えるのを己の背中で感じ取りながら、アンドレスも居た堪れぬ思いで唇を噛み締めた。
アンドレスは、胸詰まる思いを振り払うようにして、つとめて明るい声音で背後のロレンソに語りかける。
「だけど、マルセラは、すごいぞ!
俺たちの力なんかに頼らずとも、自分で、敵の手中から脱出をはかったんだ。
今は、この砦の別の場所で、仲間たちと果敢に戦っている」

ハッと、こちらを振り向いたロレンソの強い視線を背後に感じて、剣を握り締めたまま、アンドレスも半顔ほど背後を振り向いた。
「マルセラ殿はご無事であったか!
今、どこにいるのだ?!」
瞳を輝かせて己を喰い入るように見入るロレンソに、アンドレスは聞かれるまでもない、とばかりに意気揚々と即答する。
「マルセラと一緒に囚われていた仲間たちを解放するために、地下牢に行っているはずだ。
ロレンソ、行ってやれ!
今すぐ、マルセラのところに!
捕虜となった仲間たちを解放するために、彼女に手を貸してやってくれ」
「しかし、アンドレス、そなたとて加勢が必要な時ではないか」
そう応じながらも、マルセラが無事と分かって矢も盾もたまらぬ朋友の気持ちが、アンドレスには手に取るように分かっている。
「俺のことは気にするな」
そう言って、アンドレスは、スパイスまみれの顔に力強い笑みを浮かべ、周囲にグルッと視線を走らせた。
その動きにつられてロレンソも辺りに目をやれば、いつの間にか、アンドレスの周りには、ジェロニモをはじめとするアンドレス隊の精鋭たちが多数結集してきており、敵勢と勇ましく剣を交えている。
その様子に、ロレンソは素直に頷き、「では、行かせてもらうぞ、アンドレス」と、微笑んだ。
二人は、どちらからともなく剣から自由な左手を差し出して、「また後で会おう!」と、力強く握り合った。
「気を付けて行けよ!」
そう呼びかけた己の言葉など、もはや耳に入らぬ勢いで、ロレンソは、飛ぶような速さで敵群れの真っ只中を突き進んでいく。
その後ろ姿を目の端で見送りながら、アンドレスの心にも、急に、せつない思いが突き上げた。
右手は休み無く剣を繰りながらも、彼の左指は、いつしか首からさげたグランデーロの小瓶に、胸甲の上から触れていた。
この手製のお守りを渡してくれた時のコイユールの微笑みが、胸の中いっぱいに、甘く、優しく、甦る。
『アカシアの実やヒマワリの種、それから、インカローズ――特別な守護の力を持つ9種類のお守りが、瓶の中で1つにまとめてあるの。
だから、これを持っていれば、槍で刺されても死なないって言い伝えられているほどなのよ。
きっと、戦場でもアンドレスのことを守ってくれると思って』

群がる敵兵たちの向こうに見え隠れする覗き窓の、さらに彼方の夜闇へ視線を馳せて、アンドレスは、甘酸っぱい思いで満たされた胸の内で囁いた。
(コイユール、今頃、どうしているだろうか?
砦の内外で、こんな惨い戦闘になって、本陣は、運び込まれた負傷兵でごった返していることだろう。
きっと、息つく暇も無いほど、治療や看護に追われているな――)
思いが、どうにも、そちらに飛び立ってしまいそうになるのを懸命に堪えて、アンドレスは、己の心を厳しく引き締め直した。
(戦いに集中しろ、アンドレス!
これ以上の犠牲を増やさぬためにも、一刻も早く、この砦戦に決着を付けてしまわねばならないんだ!)
その頃には、風のように馳せていたロレンソは、早くも地下牢へ通じる地下通路まで進んできていた。
ここまで進んでくる間にも、ロレンソの部隊の兵たちが、多数、彼と行動を共にせんとロレンソの元に馳せ参じていた。
だが、地下牢に潜入するのに大勢だとかえって目立つため、特に腕の立つ数名の者のみを同行させていた。
砦の最端部に設けられた古びた石段を駆け下りて踏み込んだ地下階は、おぼろな松明の間隔もまばらで妙に薄暗く、外気の入る覗き窓なども無いために、空気も冷たく淀んで湿っている。
ロレンソたちは、その黴(かび)臭い薄闇に身を紛らわせ、物陰から物陰へと、足音を忍ばせて苔むした石床を馳せながら、地下道をさらに奥深くへ進んでいく。
敵兵たちの多くは上階の戦闘に参戦するために出払ってしまっているようで、今も地下通路に残っている者は殆ど無かったが、それでも、地下牢の番兵たちと思しき、厳つい巨兵たちの姿がちらほら見られた。
それらの牢番たちが慌ただしい足取りでドカドカと通路をよぎっていくのを、石柱の陰に身を隠してやりすごすロレンソたちの耳元を、番兵たちのくぐもった会話が掠めていく。
「あの脱走したインディオの女が、地下牢の捕虜どもを、どこかに逃がしやがったんだ!」
「だから、あの時、俺は、あの女に気を付けるよう、おまえに警告したじゃないか」
『あのインディオの女』というのがマルセラのことであると、ロレンソには瞬時に分かった。
ロレンソの耳は、ますます番兵たちの会話に釘づけられていく。
「俺が警告したにもかかわらず、おまえは下心を出して女の策にはめられた。
おまえが無様(ぶざま)に気を失っている間に女に脱走された挙句、地下牢の鍵まで奪われていたなんて、なんたる情けない」
「今さらゴチャゴチャ言っても始まらんだろう!
それより、逃げ出した捕虜たちを見つけるのが先だ。
あの女の手練手管にはめられて、蹴り上げられたところが今も痛むの何のって…!
今度見つけたら、絶対に、ただではおかん」
極度に苛立った敵兵たちの荒々しい会話に息詰めて聞き耳を立てるロレンソの胸は、今にも心臓が飛び出しそうなほどだった。
ロレンソは、闇に身を紛らせながら、それらの番兵たちの、張りしきった分厚い肩や筋骨隆々たる丸太のような腕をまじまじと見据えた。
(下心を出して女の策にはめられた――?
マルセラ殿が手練手管を使っただって?
まさか…一体、どんなことをして、あの巨漢の元から逃げおおせたのだ、マルセラ殿は?)

ロレンソの頭を勝手な妄想が怒涛のように駆け巡って、眩暈のする思いと同時に、その場で、その巨躯の牢番どもを八つ裂きにしてやりたい衝動に突き上げられる。
しかし、部下たちが、(どうか堪えてください。今、ここで奴らと揉めて、騒ぎになったら、かえって厄介です)と、懸命に視線で訴えてくる。
(今は、マルセラ様や牢を脱した仲間たちを一刻も早く見つけて、援護するのが先です)
石柱の後ろから飛び出していかんばかりの己を抑え込むようにして訴える部下たちの必死の様子に、ロレンソも己の感情を諌めようと努めた。
彼は、じっと堪えて、番兵たちがドスドスと石床をしならせて通り過ぎてしまうのを、柱の陰で待った。
「――行ったようだな」
彼らが去っていくと、ロレンソは低く呻き、気配を消したまま石柱から一歩を踏み出した。
部下たちがハッと目を見張った次の瞬間には、おもむろに腰の投石器に石を番(つが)えたロレンソの腕が、ブンッと鞭のようにしなって、力一杯にそれを投げ放っていた。
放たれた尖石は、完璧な軌道を描いて、去りゆく番兵の背後に迫り、ゴッ、という鈍い音と共に、彼の後頭部に深々とのめり込んだ。
叫び声ひとつ上げる間も無く、番兵の巨体が石床にドッと崩れ落ちる。
その者の傍にいた別の番兵が、異変に気付いて浮足立つも、間髪入れずに投げ放たれたロレンソの次なる棘石が、あっという間に彼をも冷たい床に沈めた。
いつもは沈着冷静を旨とする上官ロレンソの、まるで別人のような直情的な行動に、彼の部下たちが目を丸くして言葉を呑んでいる。
かたやロレンソは、軽く咳払いしながら、投石器を腰袋に戻した。
「わたしにも我慢の限界というものがある。
それに、騒ぎにならぬよう、一発で仕留めたのだから、よかろう」
何やら弁明めいた言葉を部下たちに向かって呟くと、「さあ、先を急ぐぞ」と、薄闇にかすむ地下道の奥に向かって再び駆け出した。
「敵兵どもがマルセラ殿や脱獄した仲間たちを見つけてしまう前に、我らが何としても先に見つけ出し、上階のインカ軍に安全に合流できるよう加勢せねばならん」
冷静さを取り戻して語るロレンソの周囲では、部下たちが頷きながら、顔を見合わせている。
それにしても、一体、どこに身を隠しているのか――皆、心配そうに眉根を寄せた。
マルセラ本人と、彼女が解放した捕虜とを合わせれば、数十名規模の集団になっているはずだった。
それだけの集団が、このような場所を移動していれば、それなりに目立つはず。
しかし、この地下道に降りてくるまでにも神経を研ぎ澄ませて彼らの気配を探してきたが、今までのところ、その気配は微塵も感じられなかった。
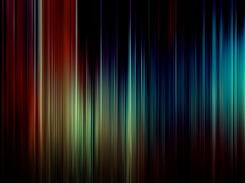
(この地下道も、奥深くへ進むほど、人気(ひとけ)が無くなっていく。
恐らく、マルセラ殿は、敵兵の目を逃れるために、この地下道のもっと奥まった場所まで入り込んでいるに違いない)
何かの見えざる手に引き寄せられるように、ロレンソたちは、足音を忍ばせつつも、疾走速度を上げながら、さらに地下道の深部まで踏み込んでいく。
敵の番兵たちさえも殆ど見当たらぬような地下道の深所は、まるで悪魔の喉笛の中にでも彷徨い込んでしまったかのような、おどろおどろしさである。
ツーッと、暗黒の天井から滴り落ちる水雫が、不意に頬や首筋をかすめ、ゾクッと身の毛がそそけ立つ。
気付けば、数少ない松明の薄明かりが照らす通路の両脇には、林立する錆びついた鉄格子が浮かび上がり、いよいよ地下牢の最奥に到達しているのだと分かる。
目を凝らしても、今は地下牢の中に人の気配は無い。
が、鼻を突くような血生臭く淀んだ空気が辺りに充満しており、少し前まで、そこに捕虜たちが収監されていたことが窺えた。
地下道の通路沿いには、地下牢を挟み込むようにして、幾つもの大小の部屋――尋問室から倉庫のようなものまで様々だが――がある。
敵襲に気を配りながらも、それらの扉のうち鎖錠されていないものを慎重に開けながら、一つ一つ中を覗いて調べていく。
中には拷問部屋などもあり、今は無人のそれらの部屋を横目に走り抜けていくロレンソたちの胸中には、再び強い不安が首をもたげてくる。
(マルセラ殿、どこにいる?!
頼むから、今も、無事でいてくれよ)

予想以上に、地下通路の構造は複雑に入り組んでいた。
ロレンソの部下が、気を利かせて壁にマーキングをしながら進んでいくも、それでも、幾度か同じ場所を行きつ戻りつしてしまうありさまであった。
そんなことを繰り返しながらも、物陰を丹念に覗き込み、石壁に取り付けられた幾つもの鉄扉を一つ一つ開けて中を確認しながら、マルセラたちの姿を探し続けていく。
ロレンソの唇から、声を絞りつつも、堪え切れずに擦れ声が漏れた。
「マルセラ殿、どこにいるのです?!
わたしです、ロレンソです!
どうか出てきてください!」
「マルセラ様――!
どこにいるのですか?!」
低声(こごえ)で懸命に呼びかけながら、辺り中を探し回るロレンソや部下たちが、幾つか目の分厚い鉄扉を開いた時だった。
途端、見覚えのある白球の群れが、開け放ったドア奥から猛然と飛び出してきた。
(あっ、これはっ!!)
と意識が走った瞬間には、既に時遅し。
白球は、ドアノブを握った姿で固まったロレンソたちの顔や全身にブチ当たってきて、見事なほど派手に炸裂した。
「――!!!」
それは、まぎれもなく、自分たちインカ軍が敵の目つぶしのために利用する、あのスパイス弾だった。
破裂した鶏卵の殻の中から、大量の小麦粉や唐辛子、胡椒が飛び出し、ロレンソたちの目や口内に飛び込んで、全身を白や赤に染め上げた。
「くぁ…っ……!」
不意打ちのスパイス弾を大量に喰らって、失神しかけたロレンソや部下たちの耳に、部屋の奥からマルセラの仰天した声が響いてきた。
「ええ?!
やだ、まさか、ロレンソ殿?!」
「マルセラ…殿……!
こ、ここに、身を隠して…いたのですか…ゴホッ!!」
胡椒や唐辛子を深々と吸い込んで激しく咳き込みながらも、安堵と歓喜の声を上げたロレンソの傍に、マルセラが素っ飛んできた。

彼女は、目の前でスパイスにむせているロレンソたちと、自分の手の中にある白球とを交互に見比べて、凛と澄んだ瞳を大きく揺らしている。
「ついに敵に見つかったかと思ったの!
それで、みんなで、このスパイス弾を投げて……。
そしたら、まさか、ロレンソ殿だなんて!
ああ、しっかりして!!」
マルセラは、床の上に崩れかかったロレンソの傍に駆け寄ると、真っ青になって跪(ひざまず)いた。
「お願い、どうかしっかりして!」
粉末だらけになってフラフラと床に縋(すが)っているロレンソの肩を、ハッシと掴んで、マルセラが強く揺さぶる。
「気をしっかり持って!!」
マルセラの手に激しく揺すられて、ますます意識が飛びかけながらも、ロレンソは、この上ない安らかな表情で深々と息をついた。
「良か…った――そなたが無事で、本当に……」
「敵の監視がきつくて、上階に戻るに戻れなかったの。
それにしたって、なんてことしちゃったんだろ。
まさか、こんなところまで、あなたが来てくれるなんて」

大慌てでマルセラが周囲を見回せば、ロレンソのみならず、彼の腕利きの部下たちも、今のスパイス弾を喰らって床にへたり込み、目や口を覆いながら激しく咳き込んでいる。
「うわぁ…!
みんな、ごめんなさい!
大変なことしちゃった☆」
マルセラは、仲間の捕虜兵たちに向かって、部屋の隅に置かれた水瓶(みずがめ)を慌てて指差した。
「そこに入ってる水、腐りかけてるけど、この際、やむを得ないわ。
それで、みんなの目や口をすすいであげましょう!」
マルセラ自身も、ロレンソのために水を汲んでこようと立ち上がろうとしたその時、床に倒れかけていたロレンソが、バネのように身を起こして、マルセラの腕を捉(とら)えた。
ロレンソの手の中にある彼女の褐色の腕は、以前と変わらぬ若枝のようなしなやかさである。
しかし、その肌には、薄闇の中でも息を呑むほど、生々しい傷痕が無数に刻まれていた。
インカ軍を挑発するために、敵将アレッチェが、衆目の面前でマルセラを激しく痛めつけていた、あの屋上階の悪夢のような光景がロレンソの脳裏に甦る。
『来てはだめ!!』
アレッチェに打ち据えられながらも、挑発に乗せられかけた己を止めるために叫んだ、あの時のマルセラの必死の声が今も耳奥にこびりついて離れない。
あれだけのことがあったというのに、もともと気丈で闊達なマルセラは、今も、何事も無かったように快活に振る舞っている。
が――さすがに此度は、その身や心に受けた傷つきや衝撃は、そう軽々しいものではないだろう。
ロレンソは、胸の締め付けられる思いでマルセラの腕を握り締めたまま、懇願するような眼差しを彼女に向けた。
「マルセラ殿、行かないでくれ」
「え?
いえ、そこの水瓶から水を取って来るだけですよ」
明るい笑顔を見せて己の手をほどきかけたマルセラを、ロレンソの腕は、反射的に強く引き寄せ、次の瞬間には、全身ごと胸に抱き締めていた。
「どんなに、そなたの身を案じたことか!
だが、今、確かに、そなたは、間違いなく、ここにいる」

脱走するために牢番と何があったのか、そのことも、つい先ほどまで、あれほど気になっていたというのに、こうしてマルセラの無事な姿を目の前にしてみると、もう、どうでも良かった。
唐辛子や胡椒にまみれた前髪から覗くロレンソの瞳は、よほどスパイスが染みているのか、涙さえも滲ませて見える。
「マルセラ殿、会いたかったぞ」
逞しい腕の中に包んで耳元で熱く囁くロレンソの声音に、マルセラはドギマギしながら、頬を紅く染めた。
「み、みんなが見てるじゃないですか…」
そう言いながらも、いつしか彼女の両手は、相手の顔や髪から優しく粉を払っていた。
そんな彼女を愛しげに見つめるロレンソの瞳を眩しそうに見上げるマルセラの瞳にも、微かに涙が光っている。
「ロレンソ殿…!
ずいぶん心配をかけてしまいました。
でも、もう大丈夫。
あなたが来てくれたのだから、もう、わたしは恐れるものなど何も無い!」
同じ頃、その砦の麓の荒野では、マルセラの叔父でありトゥパク・アマルの重臣でもあるビルカパサの元に、砦のトゥパク・アマルが放った早馬の使者が、激しい戦火をぬって到着しようとしていた。
「ビルカパサ様、トゥパク・アマル様よりご伝言でございます!」
敵軍の熾烈な砲撃による破砕物のために、傷だらけになった全身を火明かりに赤々と照らし出されながら、ビルカパサは鷲のように鋭い眼光を使者に向けた。
「トゥパク・アマル様は、何と?
陛下のお命はご無事であられるか?
砦内での戦いは、いかなる状況になっている?」
矢継ぎ早に問いかけるビルカパサに、使者は馬から飛び降りて礼を払い、砲撃の轟音に負けじと猛々しい声を張った。
「トゥパク・アマル様の騎兵部隊とロレンソ様の歩兵部隊は、先に敵の砦内に潜入していたアンドレス様の援護により、無事に砦内部に進軍を果たされました。
それによって、現在、砦内には、敵に倍するインカ軍がひしめき、砦の要塞砲を占拠するべく、果敢な戦いを展開中であります」
「そうであったか」
使者のもたらした吉報に、ビルカパサの険しい面差しにも、光が射した。

夜の戦場で、ビルカパサは、その内部で行われている激しい戦いを見通すかのように、砦の方へ視線を馳せる。
そうしながら、此度の作戦を、今一度、胸の内で反芻した。
英国艦隊の艦砲射撃も頑として寄せ付けず、原油によるアンドレスたちの脅しにも屈することのなかった、スペイン軍の堅牢な石の砦。
その屈強な砦の制覇を成し遂げるべく次なる作戦の第一段階は、トゥパク・アマル軍及びロレンソ軍の総勢1700が砦内に進軍し、先に潜入していたアンドレス隊500の兵と合流すること。
さらに、作戦の第二段階は、それら砦のインカ軍2200によって、砦のスペイン軍1000を圧倒して砦の要塞砲を奪取し、奪った要塞砲を用いて砦麓に配された重装備の敵軍10000を迎え撃つ、というものであった。
その作戦を成功裏に導くためには、砦麓の敵軍10000を要塞砲の射程内まで誘(おび)き寄せておく必要があった。
それ故に、ビルカパサは、トゥパク・アマルから預かったインカ軍本隊7800を率いて砦麓の荒野に布陣し、自ら囮(おとり)となって、敵軍を砦に引き付けるための偽装退却を演じていたのだった。
偽装退却――つまり、ビルカパサ軍は、砦麓の敵軍10000の猛攻に押されて敵砦の真下に追い詰められているかのように見せかけながら、実際には、敵軍10000の方こそを要塞砲の射程内に引き入れるという、危険な任務に身を投じていたのだった。
迫り来る敵軍10000の砲火は予想以上に凄まじく、その上、敵砦の要塞砲の射程内に敢えて飛び込んでいくというのは非常に危険なことであった。
しかし、主砲台のある砦の屋上階はアンドレス隊の持ち込んだ原油によって火の海と化し、既に無効化されている上、作戦通り、砦に進軍したトゥパク・アマルたちが、迅速に残りの要塞砲を占拠してくれさえすれば、それら要塞砲の傘下はむしろ安全地帯となる。
トゥパク・アマルが、砦の敵軍に倍する数多くのインカ兵を砦内の戦いのために投入したのも、一刻も早く要塞砲を占拠せんがためであった。

そのような作戦下、此度の使者がもたらした報告は、少なくとも現段階では、トゥパク・アマル麾下のインカ軍が砦内部に進軍を果たすという作戦第一段階が、首尾よく成し遂げられたことを意味していた。
戦塵にまみれたビルカパサの厳めしい横顔は、今も予断無く引き締まったままだが、それでも、使者のもたらした朗報に微かな安堵の表情が滲んでいる。
「して、トゥパク・アマル様から、何かご命令を預かっているか?」
ビルカパサの問いに、使者は、ぐっと力強く頷いた。
「はっ。
砦のインカ兵たちは要塞砲を早急に占拠すべく奮戦しているゆえ、ビルカパサ様は、砦外の敵軍10000を砦の射程内まで導き入れるよう、当初の申し合わせ通り、作戦を続行するよう仰せでございます」
今、この瞬間も、砦に追い詰められているかに見せかけて偽装退却を続けているビルカパサ軍に、さらに追い打ちをかけるようにして苛烈な砲火を浴びせてくる敵軍10000の大軍勢。
その方角に鋭利な視線を一閃させ、ビルカパサが、使者に向かって顎を引いた。
「相(あい)分かった。
この命に代えても、あの敵軍を砦の射程内まで誘(おび)き寄せるゆえ、ご案じ召されるなと陛下にご返答申し上げよ」
「仰せの通りに!」

いつしか夜空は厚い雲に覆われ、月も星も見えない。
その暗さを増した夜空を、絶え間ない敵の砲火が生々しい血の色に染め上げている。
ビルカパサは、轟音と共に降り注ぐ敵弾の中、味方の兵をさらに砦方面に退(ひ)かせながら、唇を強く噛み締めた。
「戦えば戦うほど、あの敵軍の持つ装備の並々ならぬ強靭さ、高機能ぶりが、ますます肌身に沁みてくる。
あれほどの重火器を備えた大軍を黙らせるには、トゥパク・アマル様が見通されていたとおり、砦の要塞砲をもって制するしか手立てはあるまい」
「はっ」と、恭順を示して馬上に戻りかけた使者が、今一度、ビルカパサに向き直って声を張った。
「砦に向かう陛下に、英国艦隊から供与された武器類を持参するよう、ビルカパサ様が勧められたと聞きましたが」
荒れ狂う爆風の中で頷くビルカパサに、使者は、周囲で燃え盛る炎を両眼に映しながら猛々しく続ける。
「それらの武器類が、砦内の戦いで大いに役立っていると、トゥパク・アマル様が仰せでございました」
「それは良かった。
英国艦隊が送り届けてくれた銃剣類は、スペイン兵たちに引けを取らぬ最新鋭の見事なものだった。
我が軍の所持しているような寄せ集めの代物(しろもの)とは比べ物にならぬ。
まさか、このような場面で役立とうとはな」
ビルカパサも精悍な笑みをのぞかせたが、一呼吸おいて、低く語を継いだ。
「だが、我が軍としては、これで英国艦隊に借りができてしまったな」
「いえ、今日の昼間、英国艦隊とスペイン砦の激戦の最中、我らインカ軍が砦への攻撃を開始したために、英国艦隊は全艦撃沈を辛うじて免れたのです。
よって、我が軍と英国艦隊は、むしろ、これで御相子(おあいこ)と存じます」
「なるほど、そなたの言うことにも一理ある」
ビルカパサが苦笑交じりに頷いた。
そんな彼に一礼を払うと、使者は素早い身ごなしで馬上に飛び乗った。
「では、わたしは砦に戻ります」
瞬時に馬の踵を返した使者に、ビルカパサの力強いテノールの声が追ってくる。
「アンドレス様やロレンソ殿は、ご無事であられるか?」
「はい。
お二方ともご健在にて、ご安心ください」
「そうか、良かった」
「それに、ビルカパサ様の姪御のマルセラ様もご無事と聞いております」
馬上から振り向きざま、逞しい面持ちを微笑ませた使者の言葉に、ビルカパサは己の内面を見透かされたようで、はっと息を詰めた。
が、ほどなく、真摯な面差しで礼を払う。
「マルセラのことまで、かたじけない。
だが、正直、安堵したよ、ありがとう」
いかに私情を排し、感情統制のいき届いたビルカパサとはいえ、口には出さぬ心の内では、敵中に囚われて酷い目に合わされていたマルセラのことを案じていないはずはなかった。
ビルカパサは、馬上の使者を真っ直ぐ見つめる。
「そなたも気を付けて参られよ」
誠実な思いの宿ったビルカパサの声音に、使者は深く礼を返した。
「ビルカパサ様も。
ご武運をお祈りしております」
そう力強く応じ、使者は砦に向かって一気に馬を駆り出した。
土煙と共に去り行く彼の後ろ姿は、たちまち夜闇の中に吸い込まれていく。
ふと気付けば、先ほどから遠雷の鳴り響いていた高い夜空からは、微かな雨粒が、ポッ、ポッ、と、乾いた荒野に落ちはじめていた。
「雨か…」
ビルカパサ軍と対峙する敵軍10000の陣頭でも、断続的に降り注ぐ雨粒を上質な軍用皮手袋の上に受けながら、低く呟いている人物がいた。
黄金色に輝く肩章を戦場の夜風に吹き流しながら、闇に浮き立つ高級馬の高い背に座したこの人物――植民地ペルー副王領を統治する副王ハウレギの嫡男、アラゴン王子である。
当初、トゥパク・アマルら反乱軍の鎮圧は、アレッチェを総指揮官とした軍部に委ねられていた。
しかしながら、反乱軍の始末に予想以上に手間取っているアレッチェらの様子に痺れを切らした副王は、自らの直属部隊を戦場に派兵するに至っていた。
その父王から預かったスペイン王党軍を指揮しているのが、このアラゴン王子である。

彼は、自軍の砲撃によって砦の方へ退却を強いられているビルカパサ軍を冷徹な横顔で見据えながら、波打つ長髪に降りかかった水滴をサッと振り払った。
「雨とは忌々しいことだ。
だが、まだこの程度の小雨なら、我が軍の砲撃に然程(さほど)の差し障りが出るほどではあるまい。
なれど、このまま大降りになるようでは厄介だ。
早々に決着を付けてしまわねばならぬ」
そう独りごちたアラゴンの傍に、彼の副官エドガルドが、美しい皮紐で結ばれた巻き物を手に、逞しい黒馬を寄せてきた。
いかにも王子の腹心らしく気品溢れる風貌を備えたエドガルドは、その態度も堂々と沈着で、しかも隙が無い。
「アラゴン王子、たった今、砦のアレッチェ殿より書状が届きましてございます。
王子に早急にご高覧頂くようにと」
エドガルドの言葉に、アラゴンは、輝くような銀髪に縁取られた美貌を、書状の方に振り向けた。
「アレッチェからの伝文か。
待ち侘びたぞ。
見せよ」
「はっ」
エドガルドが恭しく掲げ上げた巻き物を素早く受け取ると、鞣(なめ)し皮に包まれたアラゴンの指先が、優美な手つきで書状を開いていく。
無言のまま鋼色の瞳で書状をなぞっていく彼の横顔を、エドガルドや周囲のスペイン兵たちが黙って見守っている。
暫しの後、アラゴンがゆっくり紙面から顔を上げた。
それから、物思わしげに前方のビルカパサ軍に目をやってから、砦の方へ視線を這わせていく。
今もビルカパサ軍に向けて絶え間なく火を噴いている自軍の大砲群の轟きと振動が、アラゴンや彼の周りの兵たちの全身にびりびりと伝播し続けている。
やがて、火明かりに照らされて血塗られたように光るアラゴンの唇から、感情の見えぬ声が漏れた。
「アレッチェの報告によれば、トゥパク・アマルたちが、我が砦のスペイン兵に倍する援軍を引き連れ、砦内へ侵入してきたようだ」
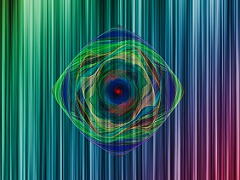
どよめいた周囲の兵たちを背後にしたまま、副官エドガルドが、鮮やかな緑碧玉の瞳を美麗に微笑ませ、艶やかな声音でアラゴンに応じた。
「なれば、我らにとって、それはむしろ吉報。
王子やアレッチェ殿の思惑通りに事は進んでいるということになりましょう。
俗な喩えではございますが、飛んで火に入る夏の虫とは、まこと、このことかと」
「左様(さよう)」と、アラゴンも微かに口端を吊り上げたが、「しかし、まだ予断はならぬ」と、すぐに真顔に戻った。
今も屋上階から炎を噴き上げたままの砦の方へ馬を進めつつ、今一度、アラゴンは、部下の掲げる松明に透かしながら、手元の書状に目を走らせた。
それから、抑揚の無い声で、冷徹に言い放つ。
「さて、では、我らも砦内へ向かうとしようか。
謹厳なる鉄壁のスペイン砦に、汚らわしい土足で踏み込んでいった礼儀知らずの虫けらどもめ。
あの者どもの動きをアレッチェが封じている間に、我らが早々に止(とど)めを刺してしまわねばならぬ」
「はっ」
副官エドガルド以下、アラゴンの側近及びスペイン兵たちが、猛々しく恭順を示した。
「砦のアレッチェ殿は、トゥパク・アマルたちの動きを首尾よく封じることができましょうか?」
側近たちの問いに、アラゴンは皮相な薄い笑みを湛えて頷いた。
「インカ兵どものすることと似たり寄ったりの、原始的な小細工ではあるがな。
その上、砦のスペイン兵まで巻き添えにする荒っぽい手ではあるが、それでも、一時的な効果はあろう。
故に、我らも急ぎ、決着を付けに行かねばならぬ」

「して、王子、あそこで我らの砲火から逃げ惑っているインカ軍の残党どもは、如何いたしましょう?」
冷厳な声音で語を発したエルガルドが、口早に続けていく。
「斥候たちの報告によれば、あれを率いているのは、トゥパク・アマルの腹心ビルカパサとのこと。
この反乱が始まって以来、トゥパク・アマルが捕縛されていた時でさえ、執拗に副王陛下に盾突いてきた、看過ならぬ大謀反人でございます。
この機に、しかと息の根を止めておいた方がよろしいかと存じますが」
エドガルドの言葉に、アラゴンも、その鋼色の双瞼に赤黒い炎を映しながら、険しい表情で顎を引いた。
「まこと、あのビルカパサという男、このまま放置するわけにはいかぬ。
砦に雪崩込んできたインカ軍からアレッチェの掴んだ情報によれば、ビルカパサは、あのように砦に向かって逃げる素振りを見せながら、実のところ、我らを砦の射程内に誘(おび)き寄せようとしているらしい。
多勢を率いて砦に侵入したトゥパク・アマルが要塞砲を奪取し、その砲火によって、射程内に誘き寄せた我らを撃滅しようという愚かしい策謀だ」
「なんと、偽装退却でありましたか――!」
側近や兵たちが、憤然と色めき立った。
「なるほど、それで、先刻からの疑問が解けました。
これまでのあの者どもの戦いぶりを振り返ると、命を顧みることなく、捨て身で立ち向かってきていたというのに、此度は妙に退却が早いと訝しく思っていたのです」
豊かなブロンドを小雨まじりの夜風に吹き纏(まつ)わらせながら、エドガルドは、妖艶な緑の光を湛えた目元を聳やかせた。

「左様」と、アラゴンも呪わし気に応じて、続ける。
「わたしも、エドガルドと同様の印象を抱いていた。
我らを謀(たばか)るとは、生意気千万。
実に、忌々しきことだ。
なれど、それならそれで、逆に我らがあの者どもを謀り返してやればよいこと。
あの者どもの策にかかったと見せかけ、砦に引き寄せられていると装いながら、逆にビルカパサ軍を砦の壁際まで追い詰めて、逃げ場を奪ってから殲滅すればよい。
どうせ、あの者どもに、もはやトゥパク・アマル軍による要塞砲の援護は無いのだから」
熾烈な攻防戦の続くスペイン砦とその麓の荒野を遥かに見晴るかすインカ軍本陣は、スペイン砦が屹立する断崖と暫しの距離を隔てて対峙した別の断崖上に置かれていた。
トゥパク・アマルやアンドレスたちが大軍を引き連れて出陣してはいたが、その本陣もまた、生え抜きの精兵たちによって堅く守られている。
そして、そのインカ軍本陣では、出陣して敵軍に果敢に挑んでいる男性陣に負けぬ勢いで、残された女性たちが、まさに戦争状態さながらの慌ただしさで、続々と運び込まれてくる負傷兵たちの看護に追われていた。
負傷兵たちの多くは、もちろんインカ兵たちではあるが、夜戦場で戦塵や血潮にまみれて正体不明の姿形となって運び込まれてくる者たちの中には、時にスペイン兵も紛れ込んでいた。
それでも、インカ軍の従軍医や看護に勤(いそ)しむインカ女性たちは、敵味方の区別なく、傷ついた者たちの治療に全力を注いでいる。
負傷した者は、敵兵であろうが、たとえ捕虜兵であろうとも、丁寧に治療して看護し、回復したら解放する――反乱当初からトゥパク・アマルが貫いてきた方針は、この時期に至ってもなお、変わることなく貫かれていたのだった。
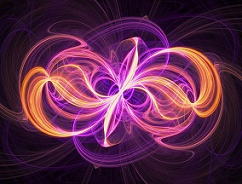
そして、今、その夜の治療場には、さらにスペイン兵以外の負傷兵も大量に運び込まれてきていた。
それは、その日の昼間、スペイン砦と決戦に臨んだ英国艦隊の戦艦に乗艦していた英国兵たちであった。
スペイン砦の猛烈な砲撃によって、多くの英国艦が撃沈されたが、それらの沈没船から投げ出された者や、激しい戦闘の最中に海上に吹き飛ばされた者たち――そうした英国兵たちのうち、幸運にも息のある状態で浜辺に打ち上げられた男たちが、インカ軍本陣に運び込まれ、懸命な治療と看護を受けていた。
それらの負傷兵たちの間を、薬草を手にして忙しく走り回っている看護の女性たちの中には、コイユールの姿もあった。
サーベルによって無残に斬り裂かれた者、銃弾を身に受けて瀕死の重体の者、砲撃によって身体の一部を吹き飛ばされ、あるいは全身に火傷を負った者など、負傷兵たちは、その傷の深さも重症度も様々である。
特に重症の兵たちを受け持っているコイユールのもとに運び込まれてくる兵たちは、皆、思わず目を背けたくなるような惨(むご)たらしい姿となっていた。
それでも、彼女の手は臆することなく、殆ど人の姿を成さぬ血みどろの肉塊と化した兵たちの戦塵や血糊を丁寧に拭い、清潔な水で洗い清め、従軍医の指示のもとに治療を補佐していく。
「くっ…!」
歯を食い縛って苦痛に喘いでいる兵の傍に跪いて、コイユールは心配そうに澄んだ瞳を揺らしながら、兵の顔を覗き込んだ。
「痛むのですね。
どうか気をしっかり持ってください」
兵の額に無数に噴き出した脂汗を手早く拭うと、彼の患部の傍に、細い褐色の指先をそっと触れた。
それから、黙って目を閉じ、指先を触れさせた相手の傷口に意識を集中させていく。

軽い瞑想状態の中で、己の全身に清んだ光が巡りだすのを感じながら、さらにイメージを深め、その光を「気」のエネルギーに換えて、指先から相手の患部へ送り込んでいく。
やがて負傷兵の口元から漏れていた苦痛の呻きが鎮まり、穏やかな寝息へと変わっていった。
コイユールは、安堵の表情で目を開くと、今一度、兵の患部を確かめてから、次の兵の元へと移動していった。
彼女の一族が代々持ち合わせてきた、その不思議な力――手を触れることによって、相手の苦痛を和らげたり癒したりする、ある種の自然療法的な力なのだが――は、こうして戦場で幾多の実践を重ねるうちに、いっそう磨かれ、力を高めていた。
次々と運び込まれてくるインカ兵や、スペイン兵、英国兵たちの間を忙しく行き交うコイユールの頬に、不意に、ポッと、雨粒が落ちてきた。
「雨だわ」
くっきりした目元を見開き、その野外の治療場で夜空を振り仰いだコイユールの背後から、老齢の従軍医が声をかけてきた。
「コイユール、手伝っておくれ。
負傷兵たちを雨に濡らして、身体を冷やしてはいかん。
急いで天幕の中に運び入れねば」
「はい!」
負傷兵たちの移動を手助けしようと彼女が身を翻した瞬間にも、すぐに逞しい体躯をしたインカ兵たちが走り込んで来て、手際よく負傷兵たちを広い治療用天幕の中へ運び入れていく。
「大丈夫、我々に任せなさい」と頼もしい笑顔を見せた兵士たちに、コイユールは長いおさげをはためかせて頷き、かわりに周囲に積み上げられていた薬草類の方へ走って行った。
貴重な薬草を雨で濡らして傷めぬよう、急いで拾い集めて両手いっぱいに抱きかかえると、自分も天幕の方に小走りで駆けていく。
そうしながらも、彼女の視線は、今まさに戦闘の真只中にあるスペイン砦の方へと吸い寄せられずにはいられない。
(アンドレス、今頃、どうしているかしら。
お願いだから無事にしていて…!)

雷鳴が青光りする雨雲の下、屋上階から赤黒い炎をモウモウと吐き出しているスペイン砦、そして、砦麓の荒野で絶え間なく轟き渡る砲声、吹き上がる爆炎。
まるで、その戦場の中心に降り立ったような生々しい戦慄が、コイユールの華奢な全身を貫いて走る。
戦場と本陣を行き来する早馬の使者たちによる報告では、トゥパク・アマル軍はスペイン砦に進軍を果たし、ビルカパサ軍は作戦通りに戦いを進めているとのことだった。
そして、先に砦に潜入していたアンドレス隊も、トゥパク・アマル軍を援護して果敢な戦いに挑んでいると聞いた。
(アンドレス……!)
断続的な雨の雫を全身に受けながら、いつしか、天幕へ向かっていたコイユールの足は完全に止まっていた。
震える瞳を砦に向けたまま、薬草を抱えた両腕に無意識に力がこもる。
(なにかしら…この感じは……。
無性に胸騒ぎがする…!)
己の胸に沸き上がった不穏な感覚の理由を探り当てようとでもするかのように、コイユールは、彼方の断崖上に聳える敵の砦を一心不乱に見つめたまま、雨の中に立ち尽くしている。
そんな彼女の様子を見かねて、共に看護に勤(いそ)しむ義勇兵の少女が、天幕の中から飛び出してきた。
「コイユール、どうしたの?
そんなところに突っ立っていたら、雨に濡れてしまうわ。
さ、中に入りましょ」
我に返ったコイユールの振り向いた表情が、今にも泣き出しそうに見えて、少女も顔を曇らせた。
反乱が始まってから、もうコイユールとの付き合いの長い少女は、コイユールの持つ自然療法の不思議な力と共に、彼女の予見的な直観が異様に当たることも知っていたのだ。
「コイユール、何か良くないことでも感じるの?」
心配そうな友の様子に、コイユールはいらぬ不安を与えてはいけないと、サッと笑顔をつくって、「ううん、なんでもないの。ただ砦を見ていただけ」と慌てて首を振った。
「さあ、あなたまで濡れてしまうわ。
天幕の中に戻りましょう」
そう明るく言って、友に寄り添いながら天幕へ歩み出しかけて、再び、コイユールはハッと足を止めた。
降りしきる雨粒のベールの向こうに透けて見えるスペイン砦の、さらにその向こうに連なる山々の稜線が、にわかに眩い黄金色に輝いて見えたのだ。
それは、今しがた己の中に湧き起こった強い不安など瞬時に忘れさせてしまうほどに、パワフルな、美しい輝きだった。

「ねえ、見て!
あれは何かしら?
何かが金色に光ってるわ!」
先ほどの不安気な表情とは別人のように顔を輝かせ、声を弾ませたコイユールに、隣を歩んでいた少女も驚いて、そちらに顔を振り向けた。
だが、少女の目には、夜闇の中に重々しい威容を晒している砦と、その彼方に聳えるアンデス山脈の連綿たる黒いシルエットしか見えない。
「あたしには何も見えないけれど。
コイユール、あなた、また何かを感じるの?」
首を傾(かし)げながら目を凝らす少女の脇で、コイユールは、己が感じているものが何かを探り当てようとするかのように、山々の方に身を乗り出しながら、大きく見開いた黒曜石の瞳を恍惚と輝かせている。
(何かしら――?!)
再び、スペイン砦内部――。
副王ハウレギの嫡男アラゴンが、アレッチェからの伝令により、トゥパク・アマルの作戦を見抜いて攻勢の手を強めていた頃、且つまた、コイユールが不思議な光を第六感でとらえていた頃、アンドレス当人は、トゥパク・アマルやロレンソから別れて、砦の武器庫を抑えるべく敵と剣を交えながら疾駆していた。
そのアンドレスの行く手を阻もうと、敵兵たちが続々と群れ成して躍りかかりくるも、アンドレスのサーベルが蒼き一閃を放つたび、たちまち敵の姿は石床に沈んだ。
同様に、アンドレスを援護しながら走るジェロニモらアンドレス隊の精兵たちも、アンドレスに劣らぬ勢いで、果敢な戦いぶりを見せている。
アンドレスは汗の雫が滴り落ちる前髪の隙間から、頼もしい部下たちの様子に視線を馳せて、「皆、その調子で頼むぞ。あと一息だ!」と、心で力強く呼びかけた。
が、次の瞬間、何とも言い難い異変を我が身に感じて、ぎくっと身を固めた。
(――!!)
急激に目の奥がズキズキ痛みだし、喉にはヒリヒリ焼け付くような激痛が広がっていく。
それでも右手でサーベルを振いながら敵と対決し続けるも、たちまち、それらの痛みは耐え難いほど激しいものになっていった。
堪えきれずに、左手で己の喉に触れると、まるで首全体が炎に巻かれたような高熱を帯びている。
(な、なんだ……?
俺たちが撒き散らしたスパイス弾の効き目が、今頃、また?)
確かに、今、己が感じている身体の異変や激痛は、唐辛子や胡椒の粉末を大量に吸い込んだ時の症状とよく似てはいた。
(だけど、それにしては、あまりに症状が強烈すぎるのではないか?!)

アンドレスの頭は混乱しつつも、激痛と嘔気に喘ぎながら自問自答し続ける。
(あのスパイス弾では、これほどの身体症状は引き起こせないはずだ。
そもそも、スパイスを撒き散らしてから、もう、かなりの時間が経っている。
あの程度の唐辛子や胡椒の効果なんか、とっくに薄れてしまっているはずだ――なら、これは、一体……!?)
アンドレスは、今も右手でサーベルを辛うじて振いながらも、もう左手では、とうに外してしまっていたゴーグルとマスクを腰袋から引っ張り出していた。
身体の異変や激痛は、何かを吸い込んでしまったことによる症状ではないかと、直観的に感じたからだった。
しかし、それらを装着しても防御効果は感じられず、ますます視界はチカチカして、頭はくらつき、もはや敵と味方の姿を見分けることさえままならない。
ジェロニモや仲間たちの無事を確かめたい思いに駆られるも、閉ざされた視界の中で、ひりつく喉は声すら出せず、どうにもすることができなかった。
熱く焼け爛れたような酷い喉の痛みも、マスクをしても何ら減ずることはなく、むしろ、いっそう呼吸困難に陥りそうだ。
正体不明の何か――それは、このような原始的なマスクやゴーグルでは太刀打ちしようのないものであると、アンドレスは苦渋の思いで察していた。
それでも諦めずにサーベルを振い続けながらも、奪われた視界の中で、彼は、気配で周囲の様子を掴もうと懸命だった。
つい先ほどまで、あれほど激しく続々と己に襲いかかりきていた敵の刃も、今は、水が引いたように不気味なほど大人しくなっている。
アンドレスは、背筋の寒くなる思いで、固唾を呑み込んだ。
(異変を感じているのは俺だけじゃない…。
ジェロニモ…みんな……いや、敵兵たちもだ…!
ここにいる誰もが、目や喉をやられて、その上、ひどい吐き気や息苦しさで、戦う力を奪われている)

己の鼻腔に、マスクの隙間を通って、ツンとした強烈な刺激臭が充満してくるのを、アンドレスは、ぞっとしながら感じていた。
(やはり空気がへんだ…!
ま…さか、大気中に何か毒物を混ぜて流し込んでいるんじゃないのか?
――いや、だけど、それはあり得ない。
だって、そんなことをしたら、インカ兵だけじゃなく、この砦の中にいるスペイン兵まで巻き添えになってしまうじゃないか……)
視界を失った己の周りで、敵味方の別なく、ドサドサと人々の倒れていく不気味な気配と音がする。
アンドレス自身も、とうとう堪え切れずに、石床の上に両膝立ちに身体を崩した。
(いや…!
あいつなら…アレッチェなら、やりかねない…!)
アンドレスは心臓の凍りつく思いで、わななく唇を噛み締めた。
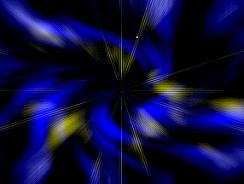
(あいつなら、俺たちインカ兵を一網打尽にするためなら、味方のスペイン兵さえ、犠牲にすることも厭(いと)わない。
砦の外にも、スペイン軍の大軍は温存されているのだ。
ならば、砦内のスペイン兵が使い物にならなくなろうとも、ここにいる俺たちインカ兵をまとめて無力化できるなら、その方を優先するに違いない。
俺たちを身動きできないように弱らせておいて、砦外の友軍を呼び寄せ、抵抗できない俺たちを始末すればいいだけのことなのだから…!)
意識の飛びそうなほど猛烈な頭痛と吐き気に襲われながらも、アンドレスは、強度の憤怒と危機感に突き上げられて、猛然と立ち上がった。
(だけど、アレッチェ…味方の兵さえ、いとも簡単に犠牲にする、おまえの汚いやり方は許せない。
それに、トゥパク・アマル様――トゥパク・アマル様が、危ない)
異物が沁みてズキズキ痛む目からは涙が滲み出し、それこそ大量の唐辛子を喉に押し込まれたような激痛と渇きに意識朦朧となりながらも、アンドレスは、壁伝いに、手探りで元来た道を戻りはじめた。
(トゥパク・アマル様も、俺たちと同じように毒にやられていたら、アレッチェは必ずトゥパク・アマル様に手を下す……!)
しかし、頭が引き千切られそうな激烈な頭痛と、内臓ごと全て吐き出してしまいたくなるような常軌を逸した嘔気に襲われて、アンドレスは、またもガクリと石床に膝をついた。
通路の数ヵ所に設けられている覗き窓に駆け寄って、せめて新鮮な空気を吸うことができたらと切望するも、もはや動く力も、正気を保っていることも難しかった。
(ああ…だけど、このままでは、トゥパク・アマル様の御身が…。
俺は、またもトゥパク・アマル様をお守りできないのか……。
トゥパク・アマルさ…ま……!)
盲目の暗闇の中で、トゥパク・アマルを求めるかのように必死に伸ばしたアンドレスの手が、力無く石床に落ちかけた時、不意に、ふわりと温かな何かがその手を優しく包み込んだ。
と同時に、彼の耳元に、聞き覚えのある柔らかな女性の声が、微かな遠い鈴の音のように響いてきた。
『――アンド…レ…ス』
朦朧としながらも、アンドレスは、反射的に、その感触と声に強く心を集中する。
すると、今度は、もっと近くで、鮮明に、その声が聞こえてきた。
『アンドレス、わたしよ』
「コイユール――?!」
視界の閉ざされた闇の中で、張り裂けぬばかりに琥珀色の瞳を見開いたアンドレスの目の前に、確かに、コイユールはいた。

心配のあまりか涙ぐんだ表情で、それでも力を分け与えるように己の手を華奢な指先で包み込みながら、清んだ眼差しで真っ直ぐこちらを見つめている。
アンドレスの表情が、驚きと共に大きく輝いた。
「俺は…夢を見ているのか…。
それとも、もう、死んでしまったのだろうか……」
恍惚と呟いたアンドレスに、コイユールは長く艶やかなおさげを揺らしながら、『違うわ。あなたは、まだちゃんと生きているわ』と、涙を滲ませた目元を優しく微笑ませた。
『私も、こんなふうにアンドレスに会いに来られるとは思わなかった。
だけど、すごく不吉な予感がして、心配で、心配で……!
そうしたら、ここにいたの』
噛み締めるように語るコイユールの全身は仄かな白光に包まれ、大気中に溶けるように半ば透けていて、その様子からも、彼女が実際にここにいるわけではないと、アンドレスには分かった。
それでも、コイユールの不思議な力をよく知っている彼には、目の前の光景が幻覚などではないということも、彼女自身が説明した通りであろうことも、悟っていた。
「コイユール、俺は、どうしたらいい?
毒のようなものを吸い込んだらしくて、目も喉もやられて、周りも見えないし、吐き気もひどい。
戦うどころか、まともに歩くことさえできないのに、トゥパク・アマル様の身に危険が迫ってる…!」
思いがけぬ愛しい人との再会で、一気に緊張感から解き放たれて、アンドレスは止(とど)めようもなく内面の思いを吐露していた。
そんな彼の手を握り締める細い指先に力を込めて、コイユールは、アンドレスの瞳の奥まで貫き通すように見つめた。
『希望を無くさないでアンドレス。
私、さっき、砦の向こうにある山の稜線が金色に光るのを見たの。

とても力強くて、神々しい綺麗な光だった。
インカの神様が、まだ諦めちゃいけないって、そう告げておられるように思うの』
そう言って、今度はアンドレスの手を握っていた指を緩やかにほどくと、『目を閉じて、アンドレス』と、静かに囁いた。
その包み込むような優しい微笑みに吸い込まれるように、言われるままに目を閉じたアンドレスの瞼に、そして、彼の喉に、コイユールの温かな手がそっと触れる。
彼女の指先から、己の瞼や喉元にスゥッと光の流れ込んでくるのを、アンドレスは夢見心地で感じていた。
そういえば、ここでコイユールと会っている間、不思議と目の痛みも無く視界はスッキリして、喉の激痛や乾きも忘れるほど弱まっていて、胃のねじれそうな嘔気もすっかり消え去っていた。
そのことを、今さらのようにアンドレスは思い返しながら、胸の内に熱く込み上げてくるものを感じていた。
(コイユールが傍にいるだけで、こんなに楽になる。
それに、今もこうして、コイユールは、俺の目や喉を癒そうとしてくれている。
俺のことをすごく心配して、こんなところまで意識を飛ばして、来てくれた)
そう思うと、心の奥まで清涼な光が流れ込んでくるようで、と同時に、コイユールの指先から彼女の鼓動や息遣いまで伝わってくるようで、なんとも言い得ぬ甘美な陶酔感に満たされた。

そんな彼の耳元に、コイユールの澄んだ声が、せつなげに、それでいて、凛と力強く響いてくる。
『アンドレス、ここに留まる力が、そろそろ消えていきそうなの。
だけど、たとえ離れていても、ずっと祈ってる。
力を送り続けているから』
コイユールの声音が急に小さくなった気がして、アンドレスが慌てて目を見開いた時――そこは、先刻まで激しく戦っていた砦の中以外のどこでもなかった。
コイユールの姿は既にどこにも無く、それどころか、毒気にやられて意識不明のインカ兵やスペイン兵たちの体が、累々と通路に横たわっているばかりである。
彼女と会っていた時は、目も、喉も、激痛も、嘔気も、あれほど楽になっていたのに、今また、それらの症状が、己の身体を重く蝕(むしば)んでいるのを感じてもいた。
(でも、コイユールに会う前より、ひどくない)
眼底は相変わらず激しい痛みを伴い、視界も半ば霞んではいたが、それでも全く見えないほどではなくなっている。
喉も焼けつくような痛みと渇きに軋んではいたが、息ができぬほどではなかった。
(やっぱりコイユールの心は確かにここに居て、俺に語りかけ、目や喉の痛みを和らげていってくれた)
己に強く言い聞かせるようにそう呟いて、アンドレスは、床に崩れかかっていた全身に力を込めた。
『希望を無くさないでアンドレス。
インカの神様が、まだ諦めなちゃいけないって、そう告げておられるように思うの』
コイユールの声が、また耳元で聞こえた気がした。
『たとえ離れていても、ずっと祈ってる。
力を送り続けているから』
アンドレスは、両足にグッと力を入れて踏ん張ると、全身のバネを使って、冷たい石床から立ち上がった。
そのまま、通路の壁伝いに両手を這わせながら、重い足を引き摺りつつも、歯を喰い縛って元来た道を戻りはじめる。

(トゥパク・アマル様、どうかご無事でいてください。
すぐに参ります――!)
トゥパク・アマルが戦っている一階部分の大広間でも、アンドレスの想像に違(たが)わず、敵味方の別無く、無数の兵たちが目や喉や内臓をやられて、意識朦朧としながら石壁や床に縋(すが)っていた。
ある者は堪え切れずに激しく嘔吐し、ある者は既に意識を失って死んだように倒れ込んでいる。
悶え苦しむインカ兵やスペイン兵の身体が折り重なりながら累々と連なる中、トゥパク・アマルもまた、目や喉の激痛を免れることは叶わず、崩れそうな長身を壁にもたれかけさせて支えながら、辛うじて起立姿勢を保っていた。
砦内に進軍したインカ兵のみならず、周り中のスペイン兵までもがバタバタ倒れゆく悪夢のような光景に、トゥパク・アマルも、初めは驚愕と混乱を禁じ得なかった。
しかし、この砦内で一体何が起きているのか、それを把握しようと、己の心を落ち着け、理性を保とうと努めてもいた。
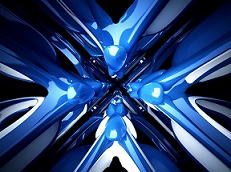
それと同時に、周りの気配にも、鋭く意識を張り巡らす。
毒気にやられてインカ兵たちは戦うことができず、トゥパク・アマル自身も視界が霞んで行動の自由を奪われている今、一番、アレッチェの標的になるのは己自身であると、よく分かっていたからだ。
アレッチェ――その名が脳裏をよぎった瞬間、アンドレスがそうであったように、トゥパク・アマルの胸中でも、この事態を引き起こした張本人が誰であるのか、その答えがはっきり察せられていた。
(砦に侵入した我々インカ軍の行動を封じるためなら、味方のスペイン兵を巻き添えにすることさえ、あの者なら厭(いと)わぬであろう。
砦内のインカ兵の戦意や行動の自由を奪っておいて、砦の外部に配したスペイン軍の大軍を砦内に引き入れさえすれば、抵抗できない我々を如何ようにもできるのだ)
ズキズキする頭を澄ませようと努めながら、「とはいえ――」と、別の思いもトゥパク・アマルの脳裏をかすめていく。
いかにアレッチェが冷酷な手段を使うことに吝(やぶさ)かではないとしても、同じ総指揮官の立場にある者として、これほどの味方の大軍を本当に犠牲にできるのか、という疑問も払拭できなかった。

この反乱が幕を開けて以来、当初の予想以上に戦さは長引き、戦線はペルー副王領南部地域のほぼ全土、隣国ラ・プラタ副王領の北東部、他にもチリのアリカ、ボリビアの高地、さらにはエクアドル、コロンビアにまで大きく広がっている。
その結果、スペイン軍とインカ軍の戦力は分散し、今や両軍の総力は拮抗している。
その混乱に乗じて、英国艦隊まで繰り出してきているのだ。
そのような戦況下なれば、アレッチェとて、本音は、一兵たりとて自軍の兵力を失いたくはないはすだ。
ましてや、砦の兵は、アレッチェ麾下の直属部隊であり、彼が手塩にかけて訓練を施してきた精兵たちでもある。
(そのような大切な兵たちを、いかにアレッチェ殿とはいえ、そう簡単に犠牲にできるのか?)
今も、トゥパク・アマルの右手には重厚な長剣が、そして、左手には英国艦隊から供与された拳銃が握られている。
不十分な視界ながらも、いつどこから来るか分からぬ敵襲に身構えているのだった。
そうはしていても、どこかに潜んだ敵兵に狙撃されれば、その銃弾ひとつで、次の瞬間にも命を奪われていても全くおかしくない状況である。
この反乱が始まって以来、今ほど、己が無防備だと感じたことはなかった。
だが、少なくとも今のところ、まだ命を存(ながら)えている。
その状態からして、恐らく、アレッチェは、己をここで簡単に殺してしまう気は無いのだと推察できた。
殺すつもりなら、もう、とうに殺しているはずだからだ。
(恐らく、あの者は、わたしを捕虜として捕え、見せしめとして、考えられ得る限りの残虐な方法で公開処刑にしたいのだ。
そうすることによって、この植民地で、二度と反乱を起こそうなどという者の現われぬよう、最大限の恐怖をインカの民に植え付けることができると信じているからだ)
トゥパク・アマルは、苦々しい思いで、胸中で呟いた。
(愚かな――そのようなことをしてもインカの民が怯むことなど無いことは、歴史が証明している。
インカ帝国が侵略されてから250年もの間、言語を絶するスペインの圧政下で、これまで幾多のインカ皇帝たちが独立解放を求めて蜂起し、囚われ、酷い処刑に付されてきたことか。
それでも、我らインカの末裔は、立ち上がることをやめることなど決して無かった)

歴代の皇帝たちに遠く思い馳せる眼差しに一瞬変わった後、またトゥパク・アマルは、現実を見据えるように険しい目つきに戻った。
(いずれにしろ、アレッチェ殿は、わたしを捕えるために、わたしが毒気にやられて意識を失うのを、どこかから眺め渡していることであろう)
そう思うと、あのアレッチェの勝ち誇った侮蔑的な視線が己の全身に絡みついてくるようでならず、その粘着的な視線の糸を即座に一刀両断したい衝動に駆り立てられた。
憤りとも悔しさとも虚しさとも、なんとも言い表せぬ感情が己の底辺から燃えるように湧き起こり、それがかえって、朦朧としていた意識を冴えさせた。
この時とばかり、トゥパク・アマルは軋んだ思考を回転させようとする。
「諦めてはならぬ…考えよ…考えよ……」
呪文のように己に言い聞かせながら、彼は、半ば瞑想に近い状態に己の意識を落とし込んでいく。
(我らインカ兵を行動不能にするために、アレッチェ殿が砦のスペイン兵まで巻き添えにした、という可能性には、もう一つの疑問が伴う。
いくら戦争状態とはいえ、このような毒物を無差別に撒くような戦法は、いわゆる騎士道精神に反することは言を俟(ま)たない。
これが敵対するインカ兵に対してのみならば如何なる手段をとろうとも、戦略的に止むを得なかったですむであろうが、味方のスペイン兵まで意図的に殺(あや)めたとなれば、スペイン国民に対する弁明は容易ではなかろう。
アレッチェ殿とて、民意を失うようなことは、避けたいはずではないのか?
にもかかわらず、味方の兵まで巻き添えにするような毒物を実際に用いたということは…。
――毒物…いや、そもそも本当に毒物なのか……?)
時間の経過と共に、意識を保てている兵の数はますます減少し、今やインカ兵もスペイン兵も、殆どの者が折り重なるようにして薄暗い石床に沈み込んでいる。
痛恨の眼差しで、それらの兵たちを見つめるトゥパク・アマルの切れ長の目の端が、考え深気に研ぎ澄まされていく。
(この砦のスペイン兵は、1000名をくだらぬはず。
いかにインカ兵を一網打尽にするためとはいえ、そのような多数の味方の兵を意図的に殺めたとなれば、たとえ戦さには勝ったとしても、スペイン国民の感情は穏やかではないはず。
国民の反感を買えば、アレッチェ殿とて、今握り締めている強大な権力も、地位も、名望も、全てを失いかねない。
あの者にとっては、それでは本末転倒だ)
強い嘔気が胃から這い上がってきて、瞬間、思考が中断される。

それでも、今の己の一連の考えが、トゥパク・アマルに一縷の希望を持たせていた。
(もし、わたしの考えるようにアレッチェ殿も考えているとすれば――いや、あの者なら、己の保身に考えを致していないはずはない。
わたしの考えは、それほど的を外してはいないはずだ。
そうならば、この砦内の大気中に撒かれた毒のようなものは、スペイン兵の命まで奪うような猛毒ではないのではないか?
治療をすれば、あるいは、時間が経過すれば、回復する程度のもの。
視界を奪い、強い頭痛や嘔気を誘い、戦意を奪う――だが、それは一時的なものであって、致命的なものでも、後遺症を残すものでもないと推察できる。
もしスペイン兵にとってそうならば、我らインカ兵にとっても、同様に致命的なものではないはずだ)
それら一連の逡巡たる思考も実際には瞬時のものであったが、トゥパク・アマルにとっては、永い時を煩悶しているような感覚であった。
それに、致命的なほどの猛毒ではない――そう結論づけたことで微かな安堵は覚えるも、とはいえ、今この瞬間に生じている身体症状は、卒倒するほど強烈であることに変わりはなかった。
(たとえ一時的な症状であろうとも、結局のところ、毒が抜ける前に砦外の敵軍が雪崩込んでくれば、砦のインカ兵の運命はそこまでだ。
無抵抗のまま、その場で銃殺か、捕縛の後に処刑か、全てはアレッチェ殿の心ひとつ)
トゥパク・アマルは、床に折り重なって倒れ込んでいる意識不明のインカ兵たちに、視力のおぼつかぬままに視線を馳せた。
全ての者たち一人一人が、独立解放を求めて共に戦い抜いてきた、かけがえのない仲間であり、同志であった。
インカ兵たちは皆、倒れてもなおトゥパク・アマルを気遣い、護ろうとするかのように、彼の方に顔を向けて、開きかけた口はトゥパク・アマルの名を呼んでいるかのように見える。
(すまぬ…!
わたしの方こそ、そなたたちを護ってやることができず)
トゥパク・アマルは、懺悔にも似た思いで、強い無念さに唇を噛み締めた。

しかし、それでも諦めたくはなかった。
この段に至ってもなお、彼の思考は懸命に策を求めて彷徨(さまよ)い続ける。
(何か打つ手は無いか……!)
冷たい石壁にもたれたまま、さらに霞みを増す視界の中で、答えを求めて漂う彼の視線が、ふと、傍らの松明の火に留まった。
紅々と燃え上がる炎から力を得ようとでもするかのように、じっと松明を見つめていた瞳が、ハッと、大きく見開かれた。
トゥパク・アマルの漆黒の瞳の中には、朱色に燃え上がる炎が鏡のように映し出されている。
その彼の強い視線は、松明の周りにたっぷり降り積もってパチパチと爆(は)ぜながら火に炙(あぶ)られている紅や黒の粉末を捉(とら)えていた。
(あれは、我々インカ軍の兵たちがスパイス弾に込めて投げ放った、唐辛子や胡椒の粒では?)
そう思い至ったトゥパク・アマルの眦(まなじり)が、ピクッと、痙攣した。
(もしや…!)
トゥパク・アマルは固唾を呑んで、松明の直近まで、壁伝いににじり寄っていく。
さらに炎に顔を近づけ、何かを嗅ぐような仕草をした後、「うっ」と呻いて、大きく顔をそむけた。
火の熱さ以上に強烈な熱気と刺激臭が顔面と呼気を襲い、堪え切れずに激しく咳き込むと同時に、彼の両目からは、ドッと、滝のように涙が溢れ出た。
トゥパク・アマルは咄嗟に松明から離れて、跳ね上がった心拍を整えようと胸を押さえる。
「なるほど…唐辛子に胡椒…大気に撒かれた刺激物の正体は、これだ…!
それらを大量に集めて燃やし、大気ごと砦全体に流し込んでいるに相違ない。
なぜ、今まで気付かなかったのだ…。
古来からある、原始的な戦法ではないか」
そう低く呻いた後、しばし放心したように虚空を見つめた。

(唐辛子や胡椒の粉末であれば、大量に燃やすことによって、催涙効果の高い毒ガスまがいの強烈な成分を中空に放出できる。
刺激物を吸入した相手の行動を一時的に麻痺させられる上、その刺激成分が抜けさえすれば、後遺症を残すことなく健康体に回復する。
スペイン軍の銃撃を封じるために我らインカ軍が用いた苦肉の武器が、逆に、このような形で敵方に再利用されるとは、なんたる皮肉……!)
トゥパク・アマルは、湧き起こる口惜しさを払い去るかのように、高熱を帯びた顔を、同様に高熱を帯びた手の平で、グッ、と拭った。
その手に冷たい感触を覚え、小さく溜息をつく。
唐辛子や胡椒類の刺激成分によって溢れ出す涙が、今も止まっていないらしい。
(真相が分かってみれば、誠に他愛ない作戦の応酬であるが、我らよりも相手の方が上手であったと言わざるを得まい。
インカ兵が投げ放ったスパイス弾によって撒き散らされた唐辛子や胡椒の粉末は、掻き集めれば、甚(はなは)だしい量になるはずだ。
それらを大量に掻き集め、砦内のどこかで燃やし、焚き上げ、それによって生成された刺激物を大気ごと換気口から砦内の各所に流し込めば、このような惨状を生じさせることも不可能ではない)

この大広間の中で、両軍入り乱れて屍のように失神している無数の兵たちを、苦渋の眼差で見渡すトゥパク・アマルの思考は、一つの結論に向かって回り続ける。
(だが、唐辛子や胡椒の刺激成分による症状であるならば、たとえ一時的に意識を消失しようとも、療養させて解毒してやれば、後遺症が残ることもなく、元の健康体に回復させることができる。
故に、今はここで共に倒れているスペイン兵だが、我らインカ兵を始末した後には、しかるべき治療を施し、元通りの体に回復させてやるつもりなのであろう。
そこまでしてやれば、アレッチェ殿は、手柄が増えこそすれ、軍部や国民からいらぬ反感を買うことも無い。
それら全てを見越した上で、あの者は、この作戦に踏み切ったのだ)
自軍の撒いた唐辛子や胡椒によって反撃を受けるとは――トゥパク・アマルは、どうにもやり切れぬ皮相な思いに胸中が覆われていくのを止められなかった。
それでも、砦内で何が起きているのか、その全体像が次第に見えてきたことによって、彼の心眼は徐々に冷静さを取り戻しつつあった。
しかし、その時、砦内のことに完全に意識を奪われていたトゥパク・アマルの耳に、不意に、砦の外で轟く砲撃音が飛び込んできた。
恐らく、ずっと鳴り続けていたのであろうが、毒気に襲われてから、そこまで意識が回っていなかったのだ。
身体を支えるために、己の背をもたれかけさせている石壁にも、轟音による振動がビリビリと生々しく伝わってくる。
(そうであった…!
砦の外では、ビルカパサたちが本隊を率いて、敵の大軍と戦い続けているのだ。
しかも、ビルカパサたちは、砦に乗り込んだ我々インカ兵が砦の占拠に成功しつつあると、今も信じているに相違ない。
このまま進軍を続けては、ビルカパサたちまで殲滅させられる……!)

トゥパク・アマルの背筋を、ゾクリと、悪寒が走り抜けた。
底無しの悪夢から醒めた途端、また新たな悪夢の中に投げ込まれたような思いで、彼は重い症状の残る身体を引き摺り、一番手近な窓ぎわににじり寄った。
ただでさえ視力が弱まっている上、外は雨と夜闇に閉ざされ、外界の様子を把握するのは非常に困難であった。
が、それでも、外部の戦況を何とかして掴もうと、もてる全神経を懸命に研ぎ澄ます。
視力は効かないながらも、砦外に配されたビルカパサ軍が、敵の大軍によって、この砦の方角へ追い立てられて来るところであろうことは、迫り来る激しい喚声、喧噪、馬の嘶(いなな)き、銃声や砲声などによって察することができた。
やはりビルカパサは、己が命じた作戦通り、砦の射程内に向かって今も偽装退却を続けているのだ。
そう悟ると、トゥパク・アマルの心は再び凍りついた。
ビルカパサたちは、砦に侵入を果たしたトゥパク・アマル軍やアンドレス軍が、首尾よく要塞砲を占拠している真最中だと、現在も思い込んでいるに違いない。
確かに、当初の作戦では、ビルカパサ軍が偽装退却によって砦外の敵軍を要塞砲の射程内に誘(おび)き寄せ、トゥパク・アマルたちが占拠した要塞砲によって、射程内に引き入れた敵軍を迎撃する予定であった。
そうでもせねば太刀打ちできぬほど、砦外に配された敵軍の武装が強壮であったからだ。
しかしながら、今や、状況は全く変わってしまっているのだ。
このままインカ軍本隊がビルカパサに率いられて砦の方へ偽装退却を続けても、トゥパク・アマルたちによる要塞砲の援護など無いばかりか、砦外の敵軍によって砦の真下まで追い込まれ、逆に逃げ場を奪われたまま、全軍壊滅させられることになりかねない。

トゥパク・アマルの横顔を冷たい汗が伝い流れた。
(ビルカパサ、ならぬ…!
そのまま、砦に向かってきてはならぬ。
手遅れにならぬ前に、本隊を退却させてくれ。
我々もろとも一網打尽にされてしまう前に、せめて、そなたたちだけでも逃げてくれ)
そう胸の内で叫んだ己の言葉が、ビルカパサに届きようもないまま己の中で虚しく消えていくのを、トゥパク・アマルは絶望的な思いで感じていた。
ますます迫り来る窓外の轟音や震動を、全身で聴き取り、感じ取りながら、トゥパク・アマルは、懺悔と口惜しさに震える瞼を伏せた。
己の内面を押し包んでいく絶望の暗雲を苦渋の思いで感じながらも、彼の心眼は、さらにその奥深くで、今も煌々と燃えている炎を探し当てていた。
猛々しくも神々しく澄んだ炎――それは己の命の源なのか、魂なのか、いずれにしろ、それは、トゥパク・アマルの心の目が見つめれば見つめるほど、放つ光の強度を増していく。
(インカの神々は、決して我らを見捨てはしない――!)
カッ、と見開かれたトゥパク・アマルの鋭利な双瞼に、夜空の稲光が反射し、彼の瞳を黄金色に光らせた。
その瞳をぐっと押し上げ、彼は、祈るように、それでいて、挑むように、天頂を決然と振り仰ぐ。
その瞬間、分厚い雷雲で覆い尽くされた夜空を、これまでにも増して激しい稲妻が幾筋も駆け抜けた。
地上で轟く豪壮な砲音さえも掻き消すほどに、耳を劈(つんざ)く雷鳴が、無数の青光りと共に夜空を席巻(せっけん)し、時を合わせたように風雨が強まる。

窓から吹き込む大粒の雨がトゥパク・アマルの全身に叩きつけ、漆黒の長髪と黒マントを強風がバサバサと音を立てて弄(なぶ)り上げた。
敵の火器を鈍らせるそれらの雷雨を、さらに煽り、愛おしむように、トゥパク・アマルは天を見据えたまま、雹(ひょう)塊のごとく叩き付ける雨粒に身を晒している。
それでもなお、敵の砲撃音や銃声は、執拗に戦場に鳴り渡り続けている。
険しく吊り上がった切れ長の目をさらに険しくさせたトゥパク・アマルの耳に、不意に、すぐには何者とも分からぬ男の声が、途切れ途切れに聞こえてきた。
(――俺だ、トゥパク・アマル!
聞こえるか?!
聞こえるわけねぇけど、聞こえてくれと願って呼びかけてる!
俺は、今、砦の――・・・)
さらなる風雨の強まりに掻き消されたが、耳に聞こえたというよりも、心に聴こえた、と言った方が正確な、その荒々しく野性的な声音と口調には、確かに聞き覚えがあった。
その声の主に、ハッ、と思い至ったトゥパク・アマルの表情が、恍惚を帯びた驚きの色に染まる。
「まさか――」
思わず声を上ずらせて、窓から大きく身を乗り出したトゥパク・アマルは――しかし、次の瞬間には、己の背に、冷たい銃口が押し当てられるのを感じていた。
かくして、副王ハウレギの嫡男アラゴン率いる大軍によって、聳え立つ砦の壁ぎわへと追い詰められて来るビルカパサ軍を、アンドレスも砦の窓から愕然とした眼で見つめていた。
彼は、アレッチェに狙われているに相違ないトゥパク・アマルを救出したい一心で、トゥパク・アマルがいるはずの大広間に向かって、長大な通路を無我夢中で引き返している真っ最中であった。
できるだけ砦内の空気を吸わぬよう息を止め、通路上に等間隔に据えられた覗き窓ごとに息継ぎをしながら走り続け――這いずり続け、と言った方が正確だが――、大広間まで、あと100メートル弱という距離まで迫っていた。
そんなアンドレスの姿に触発されたインカ兵たちが――辛うじて意識を保てており、不自由ながらも身動きが可能な者たちのみではあったが――一人、また一人と、倒れた上体を起こし、石床を這うようにして、共にトゥパク・アマルの元へ急いでいる。
その数、ざっと十数名にのぼるだろうか。
アンドレスと同様に息を殺して通路を進み、覗き窓ごとに息継ぎを繰り返しつつ這っていく彼らもまた、窓外のビルカパサ軍が、砦とアラゴン軍に挟み込まれながら砲火に呑まれているさまに蒼白になった。

外は、いつしか嵐のような激しい風雨に変わっている。
それでもなお、攻撃の手を緩めぬ敵軍に、アンドレスはどうにも堪え切れず、窓から転げ落ちぬばかりに大きく身を乗り出した。
「ビルカパサ殿――!!
それ以上、こっちに来ては駄目だ!
完全に退路を断たれる前に、なんとかそこから部隊を退却させてくれ!!」
己のどこにそのような力が残っていたのかとアンドレス自身も驚くほどの大音声で、反射的に外に向かって叫んでいた。
が、いくら血を吐くほどの大声を張っても、天を割らんばかりの雷鳴や吠え上げる大砲の轟音に勝てるはずはなかった。
窓から吹き込む大粒の雨に打たれながら、大きな瞳を震わせ、愕然と窓外を見据えるアンドレスの傍に、ジェロニモが這い寄った。
彼も、かなり毒素にやられているらしく、いつもは黒い顔の中で生き生きと白く輝いている白目を、真っ赤に充血させている。
どんな時でも周りを陽気な気分にさせずにはおかない明るい声も、今はガラガラに擦れて、ひび割れ、息も絶え絶えであった。
それでも、ジェロニモは、アンドレスの肩を前方にグッと向き直らせ、諭すように言う。
「アンドレス様、とにかく大広間に急ぎましょう。
あのビルカパサ様のことです。
この状況になっても砦の俺たちが何も援護しないなんて、おかしいって…、何か予測外のことが起こったに違いないって、きっと…勘付いているはずです。
ですから、俺たちはビルカパサ様を信じて、とにかく、今は…トゥパク・アマル様を、一刻も早く…お助けに行きましょう」
喉をゼーゼー言わせながら、赤く腫らした目で懸命に己に訴えかけるジェロニモに、アンドレスも唇を噛んで頷いた。
(ジェロニモの言う通り、ビルカパサ殿は、この砦で起こった異変に勘付いてくれているかもしれない。
あるいは、勘付いていないかもしれない…。
今でも俺たちが予定通りに要塞砲を占拠していると思い込んでいて、敵軍を射程内に充分に引き入れるまで、俺たちが砲撃のタイミングを見計らっているだけだと思っているかもしれないんだ。
だけど、だからって、今の俺たちに何ができる…?
ここで為す術もなく立ち往生していたって、何も始まらないじゃないか!
ならば、ジェロニモの言う通り、ビルカパサ殿を信じるしかない。
何もかもが手遅れになってしまう前に、トゥパク・アマル様をお助けに上がらねば…!)
アンドレスは、吹き付ける雨水の伝い流れる顔を振り向かせて、ジェロニモや周囲の仲間たちに、「このまま前進を続けよう」と、苦渋を押しのけた力強い眼差しで合図を送った。
周囲の兵たちも、「はっ!」と凛々しく頷いて、アンドレスに応じる。
彼らは、もうひとしきり息を止めて這い進むために、叩き付ける雨粒でズブ濡れになりながらも窓から身を乗り出し、新鮮な外気を胸いっぱいに吸い込んだ。

だが、その時、聞き覚えのある声が背後で響いた。
「トゥパク・アマルを助けに行くだと?
そうはさせまいぞ、しぶといドブ鼠どもめ」
アンドレスたちが、反射的にそちらを振り向く。
と同時に、ぐっと息を詰めた。
「サルセード……!」
アンドレスの口端から、軋んだ声が漏れる。
まぎれもなく、彼らの背後にいたのは、サルセード大佐であった。
この砦戦でアレッチェの副指揮官を務めるサルセード――勲章の押し並んだ鋼色の軍服に肥満した体をギュウと押し込め、いかにも高機能そうなガッチリしたゴーグルとマスクを装着し、仁王立ちになって、こちらを睨んでいる。
「アンドレス、お前も部下たちも、ここで命を落としたくなければ、無駄な抵抗はしないことだ。
いずれ処刑されるお前たち大罪人どもを、ここで射殺することに、我らはなんの躊躇(ためら)いもないのでな」
そう冷やかに嘯(うそぶ)いた彼の背後には、同様に重厚なマスクやゴーグルで防御したサルセードの兵たちが20〜30名、銃口をこちらに向けて、アンドレスたちの動きに身構えている。
アンドレスの腕は、反射的に腰の帯剣に走った。
とはいえ、人数的に劣勢な上、銃を手にした相手と、しかも、この弱った身体でどこまで戦えるのか、さすがに心もとなかった。
下手な動きをすれば、サルセードの言葉通り、容赦なく敵の銃口が火を噴くだろう。
アンドレスは、激しく切歯扼腕しながらも、周囲のインカ兵たちに素早く目配せをした。
(皆、動いてはいけない。
今は堪えよ……!)

そんなアンドレスの様子に、サルセードは、贅肉たっぷりの顎を満足そうに撫でながら、「よしよし。聞き分けがよくて、なかなかよろしい」と、小刻みに頷いた。
その都度、彼の顎肉が、タプタプと音を立てて揺れる。
「トゥパク・アマルには、これからアレッチェ様が大事な御用があるのでな。
おまえたちに邪魔をさせるわけにはいかんのだ。
いやはや、それにしたって、まさか、まだ砦の中を動き回っている輩(やから)がいたとは、たまげたものだ」
そう言って、サルセードは、大袈裟に両腕を開いて、さも驚いた、という仕草を見せた。
「さすがに我らのような繊細な民族とは違って、蛮族のおまえたちは、体のつくりからして妙に頑強にできておるのだな。
だが、害虫のようにしぶといおまえたちも、ここまでだ。
その腑抜けた体では、我らの銃からは逃げられまい。
大人しく、ここで捕まってもらおう…かっ……?!」
したり顔で話していたサルセードの声が、突然、悲鳴に似た語尾と共に途切れた。
と見るや、口から泡を吹いて、バッタリ、前に倒れた。
たっぷり肥満した図体が石床に叩き付けられるように倒れ込み、その衝撃波で、砦全体が揺れたのではないかと思えたほどだった。
否、サルセードのみならず、数十名に及ぶ彼の部下たちまでもが、ほぼ同時に、次々と石床に崩れ落ちたのだ。
彼らに一瞬の抵抗の隙も与えぬままの、驚くほど正確で、俊敏な攻撃技である。
まだ何が起きたのか分からぬアンドレスは、体が硬直した状態で、すぐには動くことができない。
そんな彼の目の前で、倒れたスペイン兵たちの体から、ゴトッ、と重い音を立てて、見覚えのある星型の石が床に転がり落ちた。
(この石は!)
生唾を呑み込んで目を見張るアンドレスたちが、卒倒しているサルセードたちのさらに背後の通路にいる一群の人物たちに気付いて、「あっ」と、大きく顔を輝かせた。
「ロレンソ!!」

歓呼の声を上げたアンドレスの方に、ロレンソも視線を向けて、通路の奥から力強く頷いた。
ロレンソの周りには、彼の配下の隊員たちが十数名、凛々しい風貌で控えていたが、恍惚としたアンドレスの視線が自分たちの方にも注がれていることに気付くと、敏捷に礼を払って応じた。
ロレンソや彼の隊員たちの手には、インカの投石器(オンダ)が、しかと握られている。
そのオンダの石を背後から投げ放って、サルセードたちを一撃で仕留めたのだと、我を取り戻したアンドレスにも合点がいった。
「アンドレス、皆も、大事ないか」
張りのある艶やかな声で問いかけてきたロレンソに、アンドレスたちは、興奮と安堵に頬を紅潮させながら、うんうん、と首を大きく縦に頷かせた。
そんな彼らの様子に、ロレンソもホッと息をつきながら笑顔を見せたが、次の瞬間には、そのロレンソもまた、ゴホッ、と咳き込んだ。
ロレンソや隊員たちも、やはり毒気に当てられているようだ。
そう悟ったアンドレスが、再び心配そうな表情に変わる。
しかし、そんなアンドレスの様子をよそに、ロレンソや彼の隊員たちは、冷たい石床に倒れ込んでピクともしないサルセードらの傍に走り寄っていく。

ロレンソは、サルセードや彼の兵たちが完全に意識を失っていることを確かめてから、彼らが装着していたマスクやゴーグルを剥ぎ取った。
「これをはずしておけば、自分たちの撒いた毒を吸入して身動きできまい。
その代わり、このマスクもゴーグルも、我々が有効活用させてもらおうではないか。
それに、せっかくだから、ついでに銃も拝借させて頂こう」
そう目配せしたロレンソに、彼の隊員たちは「はっ」と恭順を示し、投石器によって投打されたスペイン兵たちのマスクやゴーグル、そして、銃を、素早く取り去っていく。
「こいつは、すごい。
たいそう本格的なマスクにゴーグルだ」
品定めするように満足気に呟いたロレンソは、今度はアンドレスたちの方へ、それらを手にして駆け寄ってきた。
「アンドレス、そなたたちも、これを」
「ロレンソ!」
再会を果たしたアンドレスとロレンソの腕は、互いの健在を確かめるように、ガッチリと双方の肩を握り合った。
「アンドレス、そなたを探していたのだ。
それにしても、大変なことになってしまったな。
せっかく大軍を率いて砦への進軍を果たしたというのに、このような毒気にやられて、手も足も出せぬとは」
口惜し気に低く呻いたロレンソに、アンドレスは頷きながらも、相手の鋭利な双瞼を見据えて答える。
「ああ、だけど、まだ諦めちゃいない。
俺たちは、トゥパク・アマル様をお助けに上がるところだ」
ロレンソも、アンドレスの大きな琥珀色の瞳を真っ直ぐに見つめたまま、頷き返した。
「地下牢でマルセラ殿に合流し、地上階に戻りかけたところで、砦内の異変に気付いた」
「マルセラに会えたか、良かった!」

安堵の笑顔を輝かせたアンドレスに、「ああ、スパイス弾を派手に喰らったがな。マルセラ殿は相変わらずだ」と、ロレンソも可笑しそうに白い歯を覗かせて笑顔を見せた。
「え、スパイス弾を喰らった?」
キョトンとした顔のアンドレスに、ロレンソは再び表情を引き締め、続けていく。
「それはさておき、上階に戻りかけて、毒ガスだか何だか分からんが、強烈な何かが砦内に蔓延していると察したのだ。
ここまで進んで来るのも、窓から窓へと息継ぎを繰り返して、難儀したぞ。
が、その度に風雨に当たったせいか、毒気もだんだん抜けてきてくれたがな」
ロレンソの話しに聴き入りながら、そういえば、とアンドレスも口の中で呟いた。
(外の新鮮な空気や豪雨を浴びて多少なりとも浄化されたせいなのか、確かに体が楽になってきている)
一方、ロレンソは口調を早めながら続けていく。
「あまり、ここでのんびり話し込んでいる暇は無い。
とにかく、このような時でも、そなたのことだから、トゥパク・アマル様の居場所へ引き返しているに相違あるまいと思って、戻ってまいったのだ。
そうしたら、予想的中だ」
「それで、マルセラたちは、どこに?
ロレンソ、君と一緒じゃないのか?」
「マルセラ殿や彼女と脱獄を果たした兵たちは、窓から砦を抜け出し、ビルカパサ様の元へ向かっている。
ビルカパサ様に砦で起こった異変を知らせ、もはや我らに要塞砲の占拠は不可能であろうこと、それ故、手遅れになる前に今は兵を退かれるよう、お伝え頂くようマルセラ殿に依頼した」
「そうか、マルセラが行ってくれたか!」
アンドレスは彫像のような端正な目元を見開いて、深々と嘆息をついた。
そして、さらに語を継いでいく。
「ロレンソ、よく決断してくれた。
俺たちの作戦が頓挫したことは悔しいが、全軍壊滅になるよりは、ビルカパサ殿に預けた本隊だけでも生き延びてくれたらありがたい。
俺も、ビルカパサ殿に、この砦の状況を伝える方法を探しあぐねていたんだ。
マルセラが行ってくれたなら、希望が持てる。
何といっても、ビルカパサ殿はマルセラの叔父上だ。
話しの通りも早いだろう」

「ああ。
マルセラ殿が、自ら行くと申し出てくれたのだ。
彼女は騎馬が得意だから、砦の門前に繋いだままの騎兵部隊の馬を使えば早かろう。
ただ、この天候と戦況だ。
無事にビルカパサ様の元に辿り着いてくれるとよいのだが」
そう答えたロレンソの表情が、微かに曇る。
アンドレスも眉根を寄せて、心配そうに呟いた。
「そうだな。
戦火も、雷雨も、あまりに激しすぎる」
「ああ、なれど、わたしはマルセラ殿を信じている。
それより、我らも早くトゥパク・アマル様の援護に参らねばならぬ。
さあ、アンドレスも、皆も、急ごう」
「そうだな、急がねば!
ロレンソ、俺もマルセラを信じる。
敵軍に追い立てられて、ビルカパサ殿は、かなり砦の傍まで来ている。
あのマルセラなら馬を駆れば、すぐだろう」
「それに、これほどまでに風雨が強まっては、いかに強壮な敵の砲火とて、いつまでもつか分からぬぞ。
このような乾燥地帯でこれほどの暴風雨になるなど、尋常ではないと思わぬか?」
「ああ、確かに。
こんな嵐みたいな天候になるなんて普通じゃない」
「アンドレス、そなた、覚えているか?
この砦戦が始まる前にも、トゥパク・アマル様が敵軍の上に雷雲を呼び寄せたことを。
それに、かつてのトゥンガスカの本陣戦の時だって、アレッチェの陣営を凄まじい落雷が直撃したではないか」

「あ…ああ、だけど、どれも偶然だったかもしれないじゃないか。
まさか、ロレンソ、この嵐もトゥパク・アマル様が引き起こしたとでも?」
「トゥパク・アマル様のお力は、わたしにも計り知れぬ。
なれど、少なくとも天は我らに味方している」
冷徹さと情熱の両方を宿した力強い声音でそう応じると、ロレンソは、鋼のように強靭で引き締まった褐色の腕をアンドレスの方へ差し出した。
その腕の先には、投打したスペイン兵たちから剥ぎ取ったゴーグル、マスク、銃のセットが握られている。
「さあ、そなたも、これを付けよ、アンドレス。
借り物だが、無いよりはましであろう」
「このマスク、サルセードが使っていたやつじゃないだろうなあ。
あいつとの間接キスだけは避けたいぞ。
せめて他のスペイン兵の……」
受け取ったマスクを指先でつまみながら難色を示しているアンドレスへ、「アンドレス、そなたの良いところは、分け隔てのないところであろう。どれが誰のものかなど分かるものか」と、ロレンソが有無を言わさぬ口調で一掃する。
「それより、今は一刻の猶予もならん。
すぐにトゥパク・アマル様をお助けに上がらねば」
そう言って、ゴーグルやマスクを己自身も装着したロレンソの周囲では、彼の隊員たちやアンドレス配下のジェロニモたちも、ゴーグルやマスク、銃を早々に身に着け終わっている。
そんな彼らの様子に、アンドレスも、受け取ったマスクとゴーグルを慌ててかぶり、手渡された銃を懐に押し込んだ。
そのままアンドレスやロレンソたちは、大広間に向かって、できうる限り精一杯の速度で突き進んでいく。

ついに広間の重厚な正面扉まで辿り着き、アンドレスが即座に扉の取っ手に指をかけた。
そんな彼の方に、ロレンソの鋭利な瞳が、ゴーグルの向こうから敏捷に注意を促す。
(アンドレス、気を付けて開けろよ。
まだ意識のある敵兵が中に残っていて、いきなり発砲してこないとも限らない)
(ああ、分かってる)
アンドレスも鋭い眼差しで応じ、共に広間の前まで進み来ているインカ兵たちにも、念のため扉の陰に身を隠すよう目線で促した。
それから、注意深く扉の取っ手を回し、引き開けていく。
ギイイイイイイイと軋み音を上げながら、分厚く重い鉄扉が開きだした。
皆、扉の陰に身を隠したまま、緊張した数秒の時が流れる。
幸い、懸念したような、大広間の中からの敵の銃撃は起こらなかった。
それでも予断はならない。
先ほど投打した敵兵から奪った銃を身構えながら、その撃鉄を起こし、アンドレスは、半身だけを覗かせて大広間の中に視線を馳せた。
(こいつは、ひどい……!)
愕然と大きく見開かれたアンドレスの瞳が、激しく揺れる。
大広間の中は、数ヵ所に設けられた窓が開け放たれてはいるものの、アンドレスたちが突き進んできた通路以上に換気が悪く、毒気による惨状は、さらに惨(むご)たらしいものであった。
幾重にも折り重なるようにして倒れ込んでいるインカ兵やスペイン兵の体で石床は埋め尽くされ、もはや意識の保たれている者は見当たらない。
まるで夥(おびただ)しい屍(しかばね)のみが捨て置かれたまま、命あるものは全て立ち去ってしまったかのような、不気味に静まり返った異様な空間がそこにはあった。
アンドレスも、ロレンソも、彼らと行動を共にしている兵たちも皆、蒼白になって、広間の中に飛び込んだ。
「トゥパク・アマル様、どこです?!」
トゥパク・アマルも、それらの兵たちの中に混ざって倒れているのでは?!――アンドレスたちは、ますます顔色を失(な)くしていく。
無数に倒れ伏している兵たちの様子に胸潰れる思いで床を這い回りながら、彼らは必死にトゥパク・アマルの姿を探しはじめた。
ロレンソ隊の兵たち数名が扉付近や室内の各所に立ち、トゥパク・アマルを懸命に探し回っているアンドレスやロレンソが不意の敵襲に合わぬよう、険しい面持ちで銃を身構え、広間や通路の周辺全域に厳しい監視の目を光らせている。
「トゥパク・アマル様、どこですか?!」
「トゥパク・アマル様!!」
我武者羅になって探し続けても見つからぬトゥパク・アマルの姿に、アンドレスたちの胸中には、別の強い不安が頭をもたげてくる。
「俺たちが来るのが遅すぎたんだ。
トゥパク・アマル様は、アレッチェか奴の手下に、どこかに連れ去られてしまったに違いない…!」
「アンドレス……」
口惜しさと心配のあまりに肩をわななかせているアンドレスを前にして、何か声をかけようにも、ロレンソ自身も動揺が激しく、すぐには言葉が出てこない。
(アンドレスの言うように、手遅れであったか…。
トゥパク・アマル様、今、どこにおられるのです?!)
砦の外は、ますます激しく雷鳴が轟き渡り、雹(ひょう)のような雨粒が地に叩き付けている。
それにもかかわらず、スペイン王党軍率いるアラゴン王子は熾烈な砲撃を執拗に続行しており、砦の麓で抵抗を続けるインカ軍本隊を砦の真下へ着実に追い込みつつあった。
かつてトゥパク・アマル軍が壊滅寸前に至るまでの打撃を受け、ついにトゥパク・アマル自身が捕縛された時でさえ、主君を取り戻すべく、スペイン軍に断固たる徹底抗戦を挑み続けたビルカパサ。
今、砦麓でインカ軍本隊を率いている指揮官が、そのビルカパサであると掴んでいるアラゴンやエドガルドにとって、今こそビルカパサを叩き潰しておく絶好の機会という強い思いがあった。
それが、彼らの攻撃をいっそう激しいものへと駆り立てていた。
隕石のように頭上から降り注ぐ砲弾が続々とインカ軍の随所に突き刺さり、褐色の兵たちを粉砕しながら無情な空隙(くうげき)をあけていく。

ビルカパサ軍からも反撃の砲撃を行おうとはしているが、スペイン副王直下のアラゴン軍のごとき最新の装備をもたぬインカ軍にとって、風雨の中で攻撃を続行できるような大砲など皆無であった。
無残に痛めつけられていくばかりの自軍の真只中で、ビルカパサ自身も傷だらけの全身から滲み出す血を雨粒に洗われながら、血潮で真っ赤に染まった唇を噛み締めている。
トゥパク・アマルに命じられた作戦通り、砦の射程内にアラゴン軍を十分に引き入れた今となっても、砦からの砲撃援護は気配すらも無い。
(砦に進軍を果たしたトゥパク・アマル様たちは、砦のスペイン兵に阻まれて、砦の砲台占拠を成し得なかったのかもしれない。
なれど、それならば、自ら射程圏内に飛び込んできた我らインカ軍本隊を、なぜ砦のスペイン兵たちは砲撃してこない?
一体、砦の中では何が起こっているのだ?!)
砦内では、アレッチェの策謀により、唐辛子や胡椒の刺激成分によって両軍の兵が共に意識を失い行動不能に陥っていたが、まだビルカパサはそのことを知らなかった。
そのような彼にとって、まるで砦全体が死に絶えてしまったかのように不気味な沈黙を守り続けていることが、どうにも理解できなかった。
(いずれにせよ、このまま敵軍の猛攻に晒され続けていては、我が軍が壊滅させられてしまうのは時間の問題だ。
どうにかして退却を図りたいが、敵の攻撃が激しすぎる上、これほど砦の真下まで追い込まれては、退路を切り開くことは非常に難しい…!)
その時、ビルカパサの耳に、あまりに聞き覚えのある声が風雨の間を縫って、高らかに凛と響き渡ってきた。
「叔父様――!!」
反射的にそちらを振り返って、吹き荒れる雨と砲火の中で目を凝らしたビルカパサが、大きく息を呑んだ。
「マルセラ…?
マルセラか?!」
ビルカパサが驚いて擦れ声を漏らしている間にも、マルセラは、巧みな手綱捌(さば)きでインカ兵たちの間を走り抜け、ビルカパサの跨(またが)る戦馬の真横に自らの馬を一気に寄せてきた。

風雨と砲弾の降り注ぐ中、全身ずぶ濡れになりながらも、ただならぬ様相で駆け込んで来たマルセラの姿に、ビルカパサは、己の直観していた砦内の異変が現実のものであることを瞬時に悟った。
と同時に、敵軍を見据えて険しく吊り上がっていたビルカパサの目元が、一瞬、柔和に緩む。
いかなる時も私情を排してきたビルカパサではあったが、アレッチェに囚われ残酷な目に合わされていた姪が無事に戻ってきた姿に、さすがに深い安堵の念を禁じえなかったのだ。
「――マルセラ、よくぞ戻った」
短いものではあたっが、己を見つめて噛み締めるように呟いた叔父の言葉に、マルセラの胸にも熱いものが込み上げずにはいられない。
だが、彼女もすぐに気を引き締め直し、雨粒が伝い落ちる前髪の隙間から怜悧な黒曜石の瞳を光らせて、砲撃音に負けじと決然と声を張った。
「叔父様、砦のロレンソ殿からの伝言です。
砦内には、毒素のような正体不明の気体が充満し、敵味方の別無く、皆、意識を失い倒れ込んでいます。
もはや砦の要塞砲を占拠するのは困難であることから、当初の作戦続行は不可能。
このまま叔父様が偽装退却を続けては、砦と敵軍との間に挟み込まれたまま、退路を断たれて、ここにいるインカ軍本隊までもが壊滅させられてしまいます。
せめて叔父様の率いるこの本隊だけでも、一刻も早く、この場から退却してほしいと!」
マルセラの報告に黙って耳を傾けていたビルカパサの眉間には、深い皺が寄っている。
「やはり、そうであったか。
砦内で何か異変が生じているのではと感じてはいたのだ。
それで、トゥパク・アマル様やアンドレス様は、いかがしている?
お二人ともご無事か?」
平素から感情統制のいき届いたビルカパサではあるが、いっそう感情を押し殺した冷厳な声で問いかける様子に、マルセラは、彼がどれほどトゥパク・アマルたちを案じているのか、痛いほど察せられて、言葉に窮した。
それでも、すぐに、きっぱりした口調で「いえ、トゥパク・アマル様やアンドレス様の所在やご無事は不明です」と、ありのままに答えた。
「ですが、ロレンソ殿は、アンドレス様と合流してトゥパク・アマル様の救援に向かうと言っていました。
今頃は、きっと、皆、合流しているのではないかと……」
最後の方は、さすがに自信なさげな声音になってはいたが、暴風雨の中で降り注ぐ砲弾の渦中にいて、ともかくも、自分たちは、この本隊を何とかせねばならない。
「叔父様、私たちがここで踏ん張っていても、あの敵の大軍が砦に雪崩込んでいくのを防ぐことは不可能だわ。
私たちが砦内のインカ軍を援護に向かうためにも、私たちまで、ここで敵軍に壊滅させられるわけにはいきません。
ここにいる兵たちを、まずは安全な場所に退却させて、態勢を整え直さなければ!」
叩き付ける雨粒に濡れた横顔にヌラヌラと火明かりを映しながら、ビルカパサは、非常に厳しい面持ちで低く呻いた。
「おまえの言うことは分かる。
しかし、それがならぬのだ」
ビルカパサの苦渋に満ちた言葉に、飛び交う砲火の中で、マルセラも息を詰めた。
「叔父様、どういう意味ですか?」
「もしや砦に異変が生じているのではと、わたしとて薄々感じてはいた。
なれど、この嵐にもかかわらず、敵軍の猛攻があまりに激しく執拗で、今となっては、退却の道筋を見出すことも、退却の契機を掴むことも至難なのだ」
「それじゃ、退却したくても、退却することができないと……?!」
マルセラの擦れ声に、ビルカパサは重々しく頷いた。
そんな叔父ビルカパサの、これほどに追い詰められた苦しげな横顔を見たのは、傍近くで戦い続けてきたマルセラにとっても、かつてトゥパク・アマルが囚われた時以来のことである。
語を継げずにいる彼女の周りでは、こうしている間にも、トゥパク・アマルからビルカパサに託されたインカ軍本隊の尊い仲間たちが、雨霰と降り注ぐ敵軍の熾烈な砲撃によって次々と粉砕され、人の姿を成さぬ焼け爛れた肉塊と化して、辺り中に飛び散っていく。

波打つ銀髪を叩きつける雷雨に洗われながら、馬上のアラゴン王子は、自軍の砲撃によって傷めつけられていくビルカパサ軍を厳格な表情で見据えている。
撃ち込まれる一弾一弾が、逃げ場を奪われたインカ兵の群れに着実に突き刺さり、悪魔の振るう巨大な鎌の如く彼らの命を抉(えぐ)り取っていく。
それでも、アラゴンの美麗な横顔で光る鋼色の瞳には、今も全く隙が無い。
「このような雷雨が続いては、我らの砲撃も続行が困難になる。
一刻も早く、完膚無きまでに叩き潰すのだ。
砦ぎわギリギリまで追い込み、さらに包囲網を狭めよ。
決して退却の余地を与えぬよう、攻撃の手を最大限に強めよ」
アラゴンの言葉に、脇で戦闘指揮を執っている副官エドガルドが、長いブロンドを強風に激しく吹き上げられながら、恭順を示した。
「仰せのままに、アラゴン様」
「殊(こと)に、あの軍勢を率いるビルカパサを、決して生きて逃すでないぞ」
「よく心得ております、王子」
そう応えたエドガルドの妖艶なエメラルド色の瞳が、雷鳴を映して鋭利な閃光を放った。

しかし、その時である。
周辺地域一体の偵察に放っていた斥候たちの騎馬隊が、血相を変えて、アラゴンたちの元に駆け戻って来た。
「アラゴン様、大変でございます!!」
「何事だ?!」
「ご報告いたします…!
我らの背後から、インカ兵と思しき軍勢が、多数、こちらに向かってきております!!」
その瞬間、稲妻が彼らの真上で炸裂し、辺り一面、目も眩むような白光に包まれ、全ての時が止まったように思われた。
と同時に、包囲網を狭めていたアラゴン軍の一翼から絶叫が上がった。
大気と大地を猛然と引き裂いて、そこに雷が落ちたのだ。

手綱を握るエドガルドの指に力がこもる。
「このような時に落雷が我が軍を襲うとは。
雷による被害状況を調べよ」
冷徹な声で命じると、即座に斥候たちに向き直り、険しい口調で問い質(ただ)す。
「インカ軍の援軍が来たと申すか?
数は如何ほどか?」
「それが…風雨が激しく、正確に見極めることが難しく…。
少なくとも数千はいるものと思われます」
「数千だと?!
そのような大軍、なぜ、このように接近するまで気付かなかった?」
吹き付ける雨水と跳ね上がった泥土にまみれた斥候たちが、口惜し気に顔を歪めながら、しどろもどろに弁明する。
「恐らく、我らの目につかぬよう、この豪雨と夜闇に身を紛らせ、裏手の山を延々と迂回してきたものと思われます。
なれど、あの山は急峻な上に獣道ばかりで、とても軍が進んでこられるような場所では……!」
「ですが、やたらスバシコイ奴らで、まるで野山の獣のような動き方をするのです」
他の斥候も興奮して、口角から唾を飛ばしながら、報告を叫んだ。
「身なりも簡素きわまりなく、持っている武器も斧やら棍棒やらで、山猿か原始人の集団みたいな奴らであります。
歩兵ばかりの軍団で、山からウジャウジャ湧き出してきたかと見るや、不気味な速さでこちらに猛進しております!」
さらに別の斥候が、髪振り乱し、目を白黒させながら、鼻息を荒げて報告を付け加える。
「その蛮族の首領のような男が、信じがたいほど無礼な輩(やから)で、なななんと、『アパサ様が来た以上、おまえらの好きにはさせねぇと大将に伝えておけっ!!』と……!」
「もうよい!
少しは落ち着け。
おまえたちの支離滅裂な報告を聞いていると、かえって混乱してくる」
エドガルドが厳しい語気でピシャリと斥候たちの報告を遮り、黙って彼らの様子を睥睨していたアラゴンに視線を向けた。
「王子、予期せぬ敵援軍の到来。
正確な規模や正体も不明ではありますが、数も多く、俊敏な連中と思われます。
ビルカパサ率いるインカ軍の兵力は約8000。
対する、我が軍は兵力1万。
我が軍のこれまでの砲撃でビルカパサ軍の兵力が減退していたとしても、新手の敵援軍が数千規模となれば、我が軍よりインカ側が優勢になる恐れがございます。
直ちに、迎撃態勢に入ります。
ビルカパサ軍への攻撃勢を、敵援軍の迎撃のために多少割かねばなりませぬが…」
「已むを得まい」
低く言って頷いたアラゴンの面持ちは、今も冷厳さを失ってはいない。
だが、常に誇り高く、動揺や困惑など決して露わにすることのないアラゴンも、今は僅かながらも眉根を寄せて、忌々し気に奥歯を噛み締めている。
「アラゴン様、案ずるには及びませぬ。
そのような無礼きわまりない野性児どもなぞ、即刻、撃退いたしますゆえ」
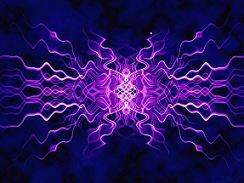
「エドガルド、此度の敵援軍、予断ならぬ相手かもしれぬぞ」
ずぶ濡れになった鬣(たてがみ)で覆われた逞しい愛馬の背を撫でながら、アラゴンが物思わし気に答える。
そのような王子の様子を、エドガルドの緑碧玉の瞳が、ひたと見据えた。
「アラゴン様、向かい来る敵の援軍に、何か思い当たるふしがございますか?」
「援軍の首領が『アパサ』と名乗ったと斥候が申しておったろう。
その名には聞き覚えがある。
隣国ラ・プラタ副王領の豪族で、此度の反乱の首謀者の一人だ。
トゥパク・アマルのような皇族とは異なり、一介の地方豪族ゆえ、まともな火器なぞ持たず、昔ながらの鈍器を武器に戦う蛮族の軍団の首魁。
しかし、それ故に、その首魁も配下の兵どもも、野獣のように身体能力が高く俊敏で、鈍器の腕がやたらに強いと聞く。
その証拠に、隣国ラ・プラタ副王領のスペイン軍を制圧して今に至る」
いかにも西洋人らしい掘り深い横顔に無数の雨水を伝わせながら、厳かな口調で語るアラゴンの目元は険しさを増していく。
そんな主(あるじ)の言葉に聴き入っていたエドガルドも、眦(まなじり)を吊り上げて、低く呻いた。
「ラ・プラタ副王領を席巻(せっけん)したインディオ。
なるほど、その人物なら、わたしも耳にしたことがございます。
周辺国まで燃え広がった反乱の火の手を鎮火するためには、いずれ戦わねばならぬ相手でございます。
このような時に、このような場所で、相見(あいまみ)えることになろうとは、思ってもおりませんでしたが。
しかるに、援軍を率いて迫り来る、その蛮族の首魁というのは――」

闘志を秘めたエドガルドの氷のような美貌に鋭利な一瞥を投げ、アラゴンは重々しく顎を引いた。
「そう。
トゥパク・アマルの最も有力な同盟者――フリアン・アパサだ」
そうしている間にも、アラゴン軍の布陣した背後の荒野からは、アパサ率いると思われる褐色の兵たちが、黒い山だかりのような群れを成して、猛然と馳せて来るのが見えてくる。
その怒涛の勢いに呑まれてしまったかのように、スペイン兵たちの動きが止まっている。
「何をぼやっとしている!
敵援軍に向けて砲撃開始せよ!
狙いつき次第、各個に撃て!!」
猛々しくエドガルドの怒声が号を叫び、我に返ったアラゴン軍の砲兵たちが、迫り来る敵援軍に向けて、一斉に砲頭を回して狙い定めた。
と見るや、その新手のインカ軍からも、多数の球状の何かが、上空に大きな弧を描きながら、アラゴン軍に向けて投げ放たれてくる。
一見、砲弾のようにも見えるが、砲弾よりも明らかに大きく、金属物というよりは、むしろ巨大なゴムボールのような質感と動きである。

「何だ、あれは?!」
「こっちに向かって落ちてくるぞ!!」
投げる――とはいえ、かなりの大きさのある袋状の物体であり、それを、これほどの距離を隔てた相手に届くよう飛ばすには、アパサ軍もそれ相応の機材を用いていると思われた。
スペイン兵たちは、雨粒が矢のように目の中に突き刺さってくるのも忘れて、正体不明のその物体が何かを見定めようと、懸命に瞳を見開いた。
その中央で、アラゴン王子やエドガルドもまた同様に、それらの得体の知れぬ物体の正体を見極めようと、目を凝らしている。
続々と上空を飛来してくる球状物体が、直径50〜60センチ大の革袋のようなものであると視認した時には、それらは、もう、すぐ彼らの頭上まで迫っていた。
「撃ち落とせ!!」
間髪入れず、エドガルドの険しい号が飛ぶ。
火薬を雨に当てぬよう懸命の所作で狙撃兵たちが銃を構え、数十発の銃が飛び込んで来る謎の革袋に向かって火を吹いた。
それらの銃弾にあっさり貫かれた巨大な革袋の群れが、アラゴン軍の真上で、ブワアッ、と派手に炸裂する。
その刹那、それらの炸裂した革袋の中から、大量の水が噴き出した。

ザバァッ、と水音が鳴って、スペイン兵たちはもとより、アラゴン王子やエドガルド自身の上にも、多数の桶をひっくり返したような水が降りかかる。
「なんだ、これは、…ゴホッ…!
ただの水か?!」
既に豪雨に打たれて水濡れの冷えた体に、さらに大量の水を浴びせられて、馬上のアラゴンが、むせながら忌々し気に語を吐いた。
そんな彼の跨る艶やかな高級馬も、頭上で弾けた水に襲われて、ブルブル大きく身を揺すり、遠くまで水の雫を弾き飛ばしている。
「王子、大事ございませぬか?
どうも、ただの水のようではありますが」
アラゴンを案じつつも、自らもドップリと水を被って、全身から滔々と水を滴(したた)らせながら、エドガルドが苦々しい面持ちで周囲の状況を見定めている。
そうこうしている間にも、迫り来る新手のインカ軍からは、満タンに水を詰め込んだ革袋が次々と投げ放たれてくる。
それらは、ブヨンブヨン、と不格好に揺れながら宙を飛んで、見かけ上は、いかにも滑稽で、頼りなげである。
そのくせ、落下して、ひとたび革袋が弾けると、スペイン兵の上のみならず、彼らの大砲や銃、雨避(よ)けをしてやっとのことで守っていた火種や火薬の上にも、容赦なく水が降りかかり、まるで大勢の小悪魔たちが高笑いしながら水鉄砲を乱射し続けているような破茶滅茶な惨状である。
「ああっ……火種に水が…」
「あいつらぁ…!
我らの火器を台無しにさせるつもりだぞ!!」
「これでは、やっと持ち堪えていた火薬も使い物にならなくなってしまう……!」
アラゴン軍の砲手や狙撃兵たちが右往左往しながら、口々に悲鳴混じりの怒声を上げている。
「腐るな!!
稼働可能な大砲だけでも構わぬ!
あのインカの山猿どもは、大砲どころか、銃もまともに持たぬ連中だ。
大砲一発の威力の凄まじさを見せつけてやるがよい」
ブロンドの張り付いた美貌を厳しくさせて、兵に喝を入れるエドガルドに鼓舞されて、辛うじて水害を免れていた数門の大砲が火を吹いた。
しかし、それらが自軍の中に突き刺さってくるのをものともせず、インカの援軍は、断固たる進撃を止めようとはしない。
それどころか、疾風迅雷の進軍を続けながら、これでもかとばかり、続々と無数の水袋を投げ放ち続けてくるのだった。
その援軍の陣頭では、フリアン・アパサ自身が、獣のような身ごなしで、3000の兵を率いて疾駆していた。
馳せながら、自軍の放つ水袋の襲撃によって、着実に火器を封じられていく眼前のスペイン軍を見据えて、ニヤニヤと口端を吊り上げている。
「よしよし、いいぞ!
もっとタップリ見舞ってやれ!!
もっと、もっと、もっと、だ!!」
さも面白そうに、それでいて豪快に号を放ったアパサの周りでは、彼の兵たちが走り続けながら、数人がかりで大きな革袋の口を持って広げ、降り注ぐ雨水を袋の中に溜めていた。
袋いっぱいに雨水が溜まると、その袋の口を頑丈なロープで縛る。
さらに、その雨水入りの袋を、大きな弓を横向きにセットしたような頑強な革布につがえ――実は、投石器を応用したものにすぎない原始的な道具なのだが――、その水袋を、敵軍に向かって、数人がかりで投げ放っていた。
同様の作業を幾つもの部隊ごとに組織的に行っており、準備ができ次第、それぞれの部隊が各個に次々と投げ放っているのであった。
豪雨の中、泥土にまみれて走りながらの作業であったが、アパサの兵たちの動作は統制が取れており、その上、機敏で、疲れを知らない。
本来、彼らがフィールドとするのは、このペルー副王領の隣国ラ・プラタ副王領であり、特にアンデスの山高い地域である。
その上、アパサの本拠地があるティティカカ湖周辺は、アンデスの中でも殊更に標高が高い。

ティティカカ湖は、インカ帝国の創始者である太陽の御子カパックが降り立ったという伝説の地であるが、その湖は標高3800メートルという世界で一番高所にある。
そのような高所の希薄な酸素の中で鍛え上げられ、戦い抜いてきた彼らにとって、このような海辺の低地は、十分すぎる酸素があるというだけで、はかりしれないほど体が楽であった。
とはいえ、決して、気を緩めているわけではなかった。
自らが放った斥候の報告によって、対峙している敵軍の将が、副王の嫡男アラゴンらしいと掴んでいるアパサにとって、相手が油断ならぬ大敵だという自覚は十分にあった。
それでも、いや、それだけに、このアパサにとっては、愉快でならなくもあったのだ。
「あのトゥパク・アマルにしろ、アラゴンにしろ、皇族だの、王族だのってのは、いつだって軟弱だったらありゃしねえなぁ!!」
疾駆しながら傲然と言い放ったアパサの周囲では、「へぇ、全く、お頭(かしら)の言う通りでさぁ!」「情けねえっすよねぇ!」と、彼の部下たちも、アパサ同様、口の減らない者たちばかりである。
アラゴン率いる大軍1万は、もう、すぐ目の前である。
アパサの目つきが鷲のように鋭くなった。
腰に括(くく)り付けた、いかにも獰猛そうな斧に、自動的に右手が走る。
そんな彼の風貌はといえば、身長は中位で筋骨逞しく、その相貌も、その目は小さいながらも深く窪み、活動性と意志の強さが漲っている。
地方豪族にすぎない彼は、外見に頓着しない性格もあいまって、戦闘姿も貫頭衣に胸甲を当てただけという簡素さだが、それだけに、機動性が高く、身も軽い。
決して美男とはいえないが、不遜なほど不敵な覇気を全身に纏ったその姿は、多分に人目を惹く雰囲気をもっている。

アパサは、眼前のスペイン軍の火器が自軍の水袋攻撃と豪雨によって、すっかり萎え切っているのを見極めながら、チラリと、その奥に聳える敵の高い砦に視線を馳せた。
(あの砦は、なぜ、ずっと黙りこくっているんだ?
トゥパク・アマル、おまえ、どういう戦いをしているんだ?
アンドレス、ビルカパサ、おまえたち、一体、何をやってやがる?!)
幾ら斥候を放っても、掴める情報には限りがあった。
アパサは、トゥパク・アマルやアンドレスの今の戦いぶりに猛烈な苛立ちを覚えつつも、ひどく案ずる思いに駆られてもいた。
(そもそも、おまえたちは無事に生き延びているのか?
何が起きているのか全く分からんが、とにかく俺が行くまで、なんとしても凌げよ!)

「お頭、アラゴンの部隊にこのまま突っ込みますか?!」
勢いある部下の声に、アパサは、砦に向けていた視線を素早くアラゴン軍に戻した。
「ああ、このまま突っ込み、間髪与えず、一気に白兵戦に持ち込む。
あいつらに火器さえ使わせなければ、分(ぶ)があるのは、肉迫戦を得意とする俺たちだ。
副王の王子だかなんだか知らねぇが、大砲やら銃やらばかりに頼ってきた軟弱者どもに、本当の男の戦いってもんを教えてやろうじゃねえかっ!
敵軍の向こう、砦下には、インカ軍の部隊が数千はいると見た。
今はアラゴンに動きを封じられているようだが、俺たちが攻め込めば、必ず、そのインカ軍も動く。
敵を腹背から肉弾戦で挟撃する!」
眼光を炯々とギラつかせながら豪語したアパサに鼓舞されて、彼の兵たちから、猛々しい鬨の声が、ドッと、天高く湧き上がった。
山裾に広がる荒野から、突如、雪崩れ込む黒い大河のように現われ、そのままアラゴン軍の背面に突撃敢行してきた援軍の到来に、砦下で身動きを封じられていたビルカパサ軍の兵たちが驚嘆していたのは言うまでもない。
「お、叔父様…、援軍が来るなんて聞いていました?」
自弁の武器を振りかざして、みるみる敵軍の中に斬り込んでくる新参のインカ兵たちを、恍惚と驚きの入り混じった表情で見つめながら、騎乗のマルセラが擦れ声を漏らした。
ビルカパサもまた、その鷲鼻の際立つ鋭利な横顔に驚きを隠せぬまま、「いや。援軍が来るなぞ、聞いてはいない」と、固唾を呑んでいる。
そう答えながらも、ビルカパサの脳裏には、この予期せぬ援軍の正体が何者たちなのか、早くも薄々予測がつき始めていた。
(この唐突な現れ方、それに、あの機動性の高さや、鈍器による戦闘の並外れた強さ。
あのお方に相違あるまい)

豪雨に加えて、先刻の水袋攻撃に止(とど)めを刺され、今や殆ど火器を使用できなくなったアラゴン軍の兵たちは、たちまち自軍の奥深くまで斬り込んできた敵援軍の肉弾戦に、彼らもまた、サーベルや銃剣による肉弾戦で応じるしかなかった。
しかしながら、新手のインカ兵たちは、獰猛な斧や、鋭い突起付きの棍棒、分厚く鋭利な刃が光る鎌などを得意の武器としており、筋骨隆々たる腕で振るうそれらの鈍器は、スペイン兵たちのサーベルを易々とへし折り、鋼の鎧さえも貫いて破壊していく。
夜闇と雷雨の中で、それらの様子をしかと感じ取りながら、ビルカパサは、自分の周囲で、みるみる生気を取り戻していく自軍の兵たちを凛然たる面差しで見渡した。
「皆、願ってもない援軍の到来だ!
我らも、今ひとたび、敵軍との決戦に挑もうぞ!!」
傷だらけの顔を決然と上げて、光の甦った双瞼で己を注視する自軍の兵たちに、ビルカパサは、さらに力強く語を継いでいく。
「もはや敵軍は、火器を殆ど使えぬ状態だ。
この豪雨の中、我が援軍から水攻めに合い、火器が萎え果てている上に、体温も下がり、体力的な消耗も激しかろう。
援軍は敵の背面から猛撃している。
よって、我らは、即座に反転し、敵正面から突撃を敢行する。
腹背からの挟撃による肉迫戦にて、一気に勝負を決しようぞ!!」
血塗れの顔面を炯々とさせて、そう猛々しく声を張ったビルカパサに応えて、彼の兵たちが「オー!!!」と、勇壮な雄叫びを上げた。
そのような仲間たちを隅々まで見渡して決然と頷くと、ビルカパサは、すかさず馬ごと踵を返し、自ら陣頭を切って、一直線に敵軍に向かって突撃を開始した。

己の後を追って進撃してくる自軍の兵たちが上げる雄々しい咆哮を背後に聞きながら、ビルカパサは、胸の内で、援軍の将に向かって呼びかけずにはいられない。
(あなたは、ラ・プラタ副王領を護っていてくださるよう、トゥパク・アマル様から重々依頼されていたはず。
にもかかわらず、あなたは、いつもご自身の判断で、陛下の許可を得ることも無く、勝手気儘に動かれる。
それでは、インカ軍全体としての統制がとれず、とても困るのです。
ですが――)
そう胸の中で呟きながらも、アラゴン軍の真只中で破竹の勢いで剛腕を振るっているに違いないその援軍の将を見通すかのようなビルカパサの目元には、逞しい笑みが滲んでいる。
(ですが、此度ばかりは、そのようなあなたの到来が、誠に有難い。
心より礼を申し上げますぞ、アパサ殿!!)
他方、アラゴン軍の大軍の只中では、獣のように吠え上げながら斧や鎌を振りかざして飛び込んでくるアパサ軍や、強壮な生気を取り戻したビルカパサ軍の両軍のインカ兵たちの襲撃に、スペイン兵たちがサーベルや銃剣を振るって懸命に対抗している。
その中央では、副官エドガルドを筆頭としたアラゴン王子の親衛隊たちが、堅固に王子を囲んで護りながら、続々と襲いかかりくるインカ兵たちと激しく斬り結んでいた。
「何があろうとも王子をお護りするのだ!」
険しい声で命じたエドガルドの言葉に、「はっ!!」と応じた親衛隊員たちは、このスペイン王党軍きっての精鋭たちである。
高速、且つ、正確な彼らの剣捌きは見事であるが、それにしても、豪雨は視界を霞めさせ、ドロドロにぬかるんだ大地は、足を絡めとり、滑らせる。
ひときわ剣の腕の立つエドガルドも、この時ばかりは、引き結んだ唇を歪めている。

エドガルドは、己に向かって飛び込んできた褐色のインカ兵を、目にも留まらぬ剣の一撃で薙ぎ払うも、ほぼ時を同じくして、すかさず別の方向から襲いかかってきた新手のインカ兵が、獰猛な斧を振り下ろし、エドガルドの愛剣を中央からぶった切った。
「我が一族に代々伝わる高貴な宝剣を、そのような野蛮な斧で汚(けが)すとは…!
貴様、許せぬ……!」
エドガルドの緑碧色の瞳が怒気をはらみ、美麗な目元が修羅の如く吊り上がる。
「ふふん、そんな細っこいサーベルが宝剣とは、笑いが止まらねぇ!
俺たちなら、そんな剣じゃあ、ガキどものチャンバラごっこにも使えねえなあ。
それに、そんなもんより、あんた自身の身を心配した方がよかねえかっ?!」
そう咆哮したかと見るや、次の瞬間には、そのインカ兵は、大きく斧を振りかざして宙空に高く跳躍し、エドガルドの頭頂目掛けて、斧を一直線に振り下ろしてきた。
瞬時に相手の動きを捉えたエドガルドの鋭い心眼が、反射的に身をのけ反らせ、相手の斧をギリギリよける。
予想以上に反応の鋭敏なエドガルドによけられて、逆に、インカ兵の方が、瞬間、バランスを崩した。
その一瞬の隙に、すかさず胸元から引き抜かれたエドガルドの懐剣が、インカ兵の急所に突き立てられる。
「――…!!」
言葉にならぬ呻きを上げて泥の中に崩れたそのインカ兵を見下ろし、フッと息をついたのも束の間、エドガルドの背後からは、さらに別の褐色兵が鎌を振り回しながら、野太い雄叫びを上げて襲いかかってきた。
その鎌を、またも、すんでのところでかわすが、エドガルドの息は上がりはじめている。
「きりがない……!
しかも、この者どもは、疲れを知らぬ…!」
切歯扼腕しながら呻いた彼の周囲では、同様に、スペイン兵たちが皆、雲霞(うんか)の如く群がり来るインカ兵たちの執拗な攻撃に苦戦を強いられていた。
今や、砦の麓は、先刻までのアラゴン軍の圧倒的優位な状態が一変し、腹背から猛烈な勢いで挟撃をかけてくるインカ軍が、明らかに押している。
一方、砦の中では、そうした外部の気配の変化を感じて、窓から外を見やったアンドレスが大きく息を呑んでいた。
(え?!
一体、あの戦場では何が起こっているんだ?!)
つい先刻まで、よもやビルカパサ軍の退却さえ叶えば、それ以上は何も望めぬと思っていたほどの悲惨な戦況が、はたと気付けば、いつの間にか、すっかりインカ軍が優勢に変わっている。
そのような麓の光景を、窓から目の当たりにしているアンドレスやロレンソたちの驚きようは言うまでもない。

彼らは、敵味方の別無く今も毒気で意識消失したままの兵たちに為す術も無く、心痛めながらも、自らも毒気の抜けきらぬ体を引きずって、敵に連れ去られたトゥパク・アマルを必死に探している真っ最中であった。
そうしながらも、ビルカパサや、彼に託されたインカ軍本隊のことをどれほど案じ、救出することのできぬ自らをどれほど責め苛んでいたか知れなかった。
そのような只中、窓外の戦況の思いもかけぬ大転換に、アンドレスは激しい驚嘆と興奮に、息することさえ忘れている。
頬を紅潮させながら、大きな琥珀色の瞳を震わせ、喰い入るように見入る窓外では、予想もしなかったインカ側の援軍の参戦によって、ビルカパサ軍が息を吹き返し、あれほど強壮だったスペイン軍の火器を封じ込め、接近戦による戦闘によって、敵軍を圧倒している。
(あの援軍を率いているのは誰なんだ?
そもそも援軍が来るなんて、まるきり聞いてなかったぞ!)
歓喜と興奮に昂ぶる胸を打ち震わせながら、心の中で叫んだアンドレスの脳裏に、サァッと、あの時のコイユールとのやり取りが流れ込んできた。
それは、砦内に流された毒気にやられて、身も心も完全に打ちひしがれていたあの時、己を力付けるために現われてくれたコイユールの幻(まぼろし)との一瞬の会話だった。
『コイユール、俺は、どうしたらいい?
毒のようなものを吸い込んだらしくて、目も喉もやられて、周りも見えないし、吐き気もひどい。
戦うどころか、まともに歩くことさえできないのに、トゥパク・アマル様の身に危険が迫ってる…!』
たとえ、それが己の夢か幻だとしても、思いがけぬ愛しい人が眼前に現われてきたことで、一気に緊張から解き放たれて、アンドレスは止めようもなく内面の思いを吐露していた。
そんな彼の手を握り締める細い指先に力を込めて、コイユールは、アンドレスの瞳を見つめて微笑みながら、言っていた。
『希望を無くさないでアンドレス。
私、さっき、砦の向こうにある山の稜線が金色に光るのを見たの。

とても力強くて、神々しい綺麗な光だった。
インカの神様が、まだ諦めちゃいけないって、そう告げておられるように思うの』
あの時の、コイユールの優しく涼やかな声は、今も、はっきり己の耳に、心に、残っている。
(コイユール、あの時、君が言っていた金色の光っていうのは、この援軍のことだったんだね。
君の言葉通り、インカの神々は、俺たちを見捨ててなんかいなかった!)
アンドレスは、はからずも己の目頭が熱く込み上げるのを感じながらも、すっかり窓外に乗り出していた姿勢を正し直した。
(だけど、まだ予断はならない。
トゥパク・アマル様の行方も未だ知れず、あのアレッチェの所在も分かっていない。
一刻も早く、なんとしても二人を探し出さねば!)
同じ頃、その同じ砦の奥まった場所の一角に、スペイン軍総指揮官ホセ・アントニオ・アレッチェのガッシリした長身のシルエットがあった。
トゥパク・アマルによる反乱が幕を開けて以来、スペイン軍全体を取り仕切ってきたのは、このアレッチェある。
しかしながら、アレッチェら軍部が反乱鎮圧に手こずっている様子に痺れを切らした副王ハウレギが、自身の嫡男アラゴン王子を戦線に繰り出してきたことによって、スペイン軍全体の最高位に君臨するのは、今や、アレッチェではなく、アラゴン王子の方である。
それでも、やはり、軍部におけるアレッチェの権力は今も絶大であり、まだ若いアラゴンよりもはるかに経験豊富な軍人であるアレッチェの采配を、副王は今でも重く見ており、また、結局のところ彼を頼りにしてもいたのだった。
そのアレッチェが居丈高に仁王立ちになっているその場所は、人目を避けるかのように辺りに据えられた松明も数少なく、アレッチェの姿も薄闇に溶け込むように霞んでいる。
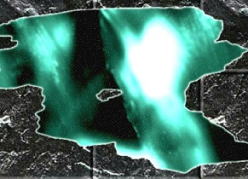
彼は通路の壁際に立ち、己の前で身を低めている部下の報告に耳を傾けながら、冷やかに相手を睨(ね)めつけている。
「インカ側の援軍が現われただと?
3000ものインカ兵が迫っていたというのに、方々に放っていた我らの斥候どもは何をしておったのだ」
「はっ…、まさか人が通るなどとは思いもよらぬ急峻な荒山を、獣道を通って越えてきたようで……」
「斥候どもの言い訳など無用。
索敵を誤った者どもは厳罰に処する。
この砦戦に敗れることあらば、死罪も覚悟しておけと言い渡しておけ」
「はっ……」
「せっかく、あと一息でインカ軍の息の根を止められるところであったというに」
険しく吊り上がった眉根を寄せて、吐き捨てるように呻いたアレッチェが、忌々し気に舌打ちした。
そのようなアレッチェを前にして、報告のスペイン兵は、アレッチェの怒りの矛先が己にも向けられるのではないかと冷や冷やしながら、表情も、身も、強張らせている。
そんな兵に氷のような一瞥を投げると、アレッチェは、苛立たしげに顎をしゃくった。
「行け。
戦況を正確に調べ、逐次、状況を報告しろ。
急ぐのだ」
「はっ…!」
兵は緊張を滲ませた声で恭順を示し、すかさず踵を返して、逃げるようにその場を後にした。
通路を駆け去って行く兵の姿が遠くなると、アレッチェは、おもむろに石壁の方へ体の向きを変える。
素早く周囲に視線を馳せ、辺りに残っているのが数名の己の護衛兵のみであることを確かめると、その強靭そうな手を通路の壁に押し当てた。
そして、その手で、グッ、と壁を押すような動作をする。
と見るや、アレッチェが手を添えていた部分の石壁が、不意に、ゴゴゴ…と震動しはじめ、やがて、その部分から壁が左右に開きだした。
そして、なんと、開いた壁の向こうに、広々とした個室が現われたのだった。

その壁部分は、いわゆる隠し扉となっているのだ。
かくして、その部屋は、アレッチェの秘密の執務室であり、スペイン兵たちの中でも、彼の護衛兵以外は、ごく上層部のものしか知らぬ、特別な場所でもあった。
警護のために護衛兵を隠し扉の外に残し、アレッチェは、己一人、室内に踏み入ると、今度は内部から壁をひとつ叩く。
すると、また壁はゴゴゴ…と鳴りながら左右から閉まりだし、僅かの間に両側から固く閉じて、室内を外部から完全に遮断した。
通路側からその部分を見たら、実際、全く普通の壁にしか見えない。
まさかそこが隠し扉になっていようとは、決して誰も思い付きはしないであろう。
それほど精巧な造りであった。
室内に窓は無く、四方は石壁によって堅固に遮蔽されている。
設置されている調度品――書斎机、椅子、ソファ、本棚、キャビネットなどは、いずれも本国スペインから調達したと思われる格調高く豪華な高級品ばかりである。
随所には、黄金の燭台が幾つも置かれ、煌びやかに室内を照らし出している。
陰鬱な雰囲気の砦の通路とは、まるで別世界のような場所であった。
そして、その室内の書斎机の前に、トゥパク・アマルが両手首を縛られた状態で座っていた。
トゥパク・アマルは、隠し扉を通って室内に戻ってきたアレッチェに、静かに視線を注いでいる。
「何かあったのか?
顔色があまりよくないが」
低く沈着な声で言葉を放ったトゥパク・アマルを、憎悪を秘めたアレッチェの双瞼が射るように見返す。

彼の視線の先で、己の豪奢な机の前に座すトゥパク・アマルは、漆黒の長髪が燭台の光を反射して濡れたように輝き、褐色の美貌を際立たせている。
吸い込んだ毒素もまだ抜け切れていないはずであり、その上、囚われの身であるにもかかわらず、まるで玉座にでもあるかのような気高い覇光を纏った姿が、アレッチェをいっそう苛つかせた。
アレッチェは、カッ、カッ、と、石床に軍靴を居丈高に高鳴らせてトゥパク・アマルの目前まで来ると、荒々しく椅子を引いて相手の正面に座った。
それから、宝石をちりばめた黄金細工の葉巻入れから、いかにも高級そうな葉巻を、一本、摘まみ出した。
それを口に運びながら、トゥパク・アマルに冷ややかな一瞥を投げる。
「今、伝令の兵が、我が軍への朗報をもたらした。
ビルカパサの軍が、全軍、壊滅したという報告だ」
口端を吊り上げて、そう言いながら、アレッチェは探るような視線を相手に馳せた。
しかし、トゥパク・アマルは、未だ動揺を見せず、ひたと己を見据えながら、じっと、耳を欹(そばだ)てている。
「いや、外の気配が、先ほどまでと明らかに違っている。
砲撃音がやみ、むしろ、インカ兵たちの吹き鳴らすホラ貝の音や彼らの歓声が聞こえる」
トゥパク・アマルの言葉に、アレッチェは、葉巻をくわえた唇を反射的に歪めた。
が、それを悟られぬよう、すぐに皮相な笑みを口元に浮かべて、「追い詰められて、ついに幻聴まで聞こえるようになったか」と、嘯(うそぶ)いた。
実際、この秘密部屋は、構造的に外部との遮蔽度が高く、外の音が聞こえてくることはありえない。
逆に言えば、この室内の音が、外部に漏れることもない。
たとえ銃を発砲したとしても、その銃声さえも、外に聞こえはしないであろう。
そう分かりつつも、アレッチェは、無意識に耳を欹てずにはいられなかった。
己の眼前で、半眼となった面差しで、強く意識を集中しているトゥパク・アマルが、まるで、本当に、外部の様子を聞き取っているかのように見えるからだった。
水を打ったように静まり返った室内に、布石を打つかのように、トゥパク・アマルの低く艶やかな声が、厳かに響く。
「援軍――我が軍の援軍が現われたのであろう」
「……!」
アレッチェの険しい目元が、ピクリ、と大きく引き攣(つ)る。
――いや、何も聞こえるはずなどない。
不覚にも、一瞬、跳ね上がった鼓動を鎮めながら、アレッチェが、そう己に言い聞かせ、平静を装った。
そんな相手の様子の変化の一つ一つを、内面の奥底まで冷徹に見通すかのように、トゥパク・アマルの鋭利な切れ長の目が、揺るぎない光を強めてアレッチェに注がれる。
アレッチェもまた、そのようなトゥパク・アマルを険しい双瞼で睨み返しながら、葉巻の煙を深々と吐き出した。
そうしながら、彼は酷薄な笑みを口端に滲ませて、眼前の捕虜の心を弄ぶように喋りだす。
「援軍が来たなどと、おまえの希望的観測なぞ聞きたくはない。
だが、仮におまえたちの援軍が来ようとも、我らには、おまえという人質がいる。
おまえの命と引き換えに、援軍を黙らせれば良いことだ。
無駄な抵抗を続けるならば、捕えたトゥパク・アマルの命は無いとな。
さすれば――」
「無駄だ」
眉一筋、動かすことなく、トゥパク・アマルがピシャリとアレッチェの言葉を遮った。
「無駄だと?
おまえの命と引き換えでも、インカ軍は戦いをやめぬと、降伏せぬと言うか?」
吊り上がったアレッチェの目元が、微かにわななく。
「そう、そのような脅しは無駄だ」
トゥパク・アマルは不動の面持ちのまま、机上に乗せた己の両の腕を見下ろした。
その両手首は太縄で固く縛られ、さりげなく様々な方向から、グッ、グッ、と押し引きしてみるが、ビクともしない。
さすがに自力では、この縄を解くのは不可能と、内心で判断せざるをえなかった。
それでも、外面的には、あくまで飄々とした風体のまま、トゥパク・アマルは、アレッチェの問いに答える。
「わたしを人質にしたなどと脅しても、もはやインカ軍は、そのようなことでは怯むことはない」
生粋のスペイン人さえも凌ぐほどの流麗なスペイン語を淀みなく操りながら、トゥパク・アマルは、さらに語を継いでいく。
「わたし一人の命などより、そなたたちスペイン役人の圧政によって苦しみに喘いでいる無数の民(たみ)の命を救うことの方が、はるかに重要であると、今や我が軍の兵たちは良く心得ている。
ましてや、此度の援軍の将が、あのアパサであるならば、なおのこと、人質としたわたしを盾に脅しても、決して屈することはないであろう。
あの者は、かつて、わたしが、そなたに捕えられてクスコの獄中に繋がれ、処刑を目前にしていたあの時でさえも、わたしを救出に来ることはなかった。
その上、アンドレスがわたしを救けに来ることさえも、断固として阻止したのだ。
獄中のわたしを救出に来ることによって、逆に、そなたの仕掛けた罠にかかり、インカ軍が一網打尽にされる危険を見抜いていたからだ。
フリアン・アパサ――あの男は、常に冷静な目で全体を見通している。
アパサがいる以上、そなたの如何なる脅しも、二枚舌も、インカ軍には通用せぬであろう」
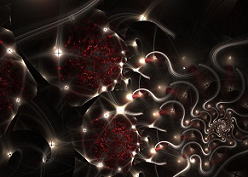
「くくく…おまえは、どこまでお人よしなのだ、トゥパク・アマル」
新しい葉巻に手を伸ばしながら、真摯に語っていたトゥパク・アマルの言葉を、アレッチェが鼻で笑い飛ばした。
「フリアン・アパサ、あの野蛮人に、おまえがそこまで入れ込んでいたとは知らなかった。
いい加減、目を覚ましたらどうなのだ?」
葉巻を上手そうに口に運び、高級椅子のゆったりとした背もたれに身を沈めながら、アレッチェの黒眼が、目尻の端からトゥパク・アマルを覗き見る。
一方、トゥパク・アマルは、今度はそなたの発言する番だ、とでも言わぬばかりに、ただ黙って聞き耳を立てている。
ひとしきり深く葉巻の煙を吸い込んだ後、アレッチェが、言葉にするのも汚らわしいという風情で喋りだした。
「あの時、おまえが、妻子共々、クスコの地下牢に幽閉されて、拷問の責苦に喘いでいたというのに、アパサは、おまえの一番の同盟者でありながら、隣国で喃喃(のうのう)と過ごしていたのだぞ。
拷問漬けの日々で、おまえは受けた傷も放置され、衰弱を極めていた。
ミカエラは、美貌が災いして、拷問と称し、牢番たちに如何なる目に合わされていたかは言を俟(ま)たない。
幼いフェルナンドは熱病に罹患し、処刑を待たずに死にかけていた。
あの小賢しいアパサが、獄中でそのような惨劇に至っていることを、想像できなかったと思うか?
そのような事態を知りながら、それでも、あの男は自分の部隊を一兵たりとも動かそうとはしなかった。
アパサがおまえにどのような言い訳をしたかは知らぬが、結局のところは、我々スペイン軍の力を恐れ、己自身の命が惜しかったからに他ならぬ。
もしあの時、おまえが自力で脱獄していなければ、おまえも、ミカエラも、息子たちも、獄中で発狂していたか、予定通り処刑されていた。
それを重々分かっていながら、結局、アパサは最後まで救出に来なかった。
トゥパク・アマル、おまえは、あの時、アパサに見捨てられたのだ。
あの卑劣な野蛮人は、ただの保身の塊だ。
あのような匹夫(ひっぷ)をおまえが今でも頼みにしていたとは、驚き、呆れて、空いた口が塞がらぬ」
皮相な笑みを口端に浮かべながら、クックッと含み笑いを漏らしているアレッチェの面前で、しかしながら、トゥパク・アマルは、相変わらず沈着な、どこか同情さえ滲ませた面差しで、相手を静かに見つめている。
「アレッチェ殿、そなたが、わたしを落胆させようとして、そのようにアパサを悪しざまに言っていることは分かる。
なれど、もし、あの時、わたしがアパサの立場であれば、わたしもアパサと同じ行動を取ったであろう。
あのように見えても、あの者は、人一倍、情が深い。
獄中にある我らのことを思って、あの者が苦しまなかったはずはない。
だが、あの時期、クスコ周辺のスペイン軍の軍備は非常に堅固で、蟻の子一匹通さぬ厳戒態勢であった。
むざむざ兵を率いてやってくれば、虎視眈々と待ち侘びているそなたたちの餌食になることは自明。
そのようなことに陥ることを、わたしも、ミカエラも、息子たちも望んではいなかった。
アパサは、そのことを誰よりも良く認識していた。
インカ軍の、ひいては、この国の民を、一人でも多く護るのが我らの使命。
無駄死にをすることも、無駄死にをさせることも許されぬ。
アパサは信じるに足る人物だ。
その証拠に、此度、こうして援軍を率いて、当地に現われたではないか。
アレッチェ殿――そのように人を疑っては、そなたは孤独で、生きにくかろう……」

「黙れ!
誰に物を言っているつもりだ」
そう言って、トゥパク・アマルの言葉を断ち切ったアレッチェの表情には、ありありと残忍さが浮き出ている。
「それ以上、くだらぬご託を並べることは許さぬ。
第一、アパサなど、ここにはいない」
「いや、当地にアパサはいる。
わたしには、あの者の声が、はっきりと聞こえた」
――ダンッ!!!
アレッチェの手が、ついに荒々しく机上を叩き付けた。
憎悪に燃える眼で睨みつけながら、凄みを帯びた声音で、冷やかに命ずる。
「これ以上、わたしを苛つかせるな。
人質としてさえ役立たぬなら、おまえをこの場で処刑するのみだ。
だが、その前に、この降伏受諾書に署名をしてから、逝ってもらおうか」
そう嘯(うそぶ)いて、アレッチェの手が、豪奢な銀細工の飾りを付した引出しから、一丁の銃と、一通の書面を取り出した。
トゥパク・アマルの漆黒の瞳が、それらの銃と紙面に鋭い一瞥を投げ、それから、彼の視線は、アレッチェが先ほど出入りしていた隠し扉の方へ動いていく。
そのような一挙一動とて見逃すまいと棘ばった眼光を強めているアレッチェの目の中で、トゥパク・アマルの表情は、今や能面のように感情が見えない。
そのトゥパク・アマルの唇が、ゆっくりと動いた。
「先ほどから、そなたを外から呼んでいるようだが」
そう言って、トゥパク・アマルが、この場にあってもなお、ブロンズ像のごとき滑らかな妖艶美を宿した横顔を軽く振って、隠し扉の方を示した。

ギリッと、さらに強く睨みを利かせてから、アレッチェも扉の方へ顔を振り向ける。
と、確かに、扉の横に据え付けられたハンドル状の金具が、非常に慌ただしく回転を続けている。
それは、扉の外側から、己の部下が、大至急、砦下の戦況を知らせようと懸命に送っている合図であった。
そのハンドルの尋常ならざる切迫した回転ぶりに、アレッチェは息を詰めた。
いつから、あれは回り続けていたのか――?
ハンドルの回転による発電によって、ハンドル中央に真っ赤な光が点灯する仕組みとなっており、普段なら見落とすはずのないものであった。
にもかかわらず、トゥパク・アマルとのやり取りに意識を奪われ、合図に気付かなかったのだ。
そのような己に舌打ちしながら、アレッチェは、トゥパク・アマルの手首に縛りつけた太縄の健在を確かめるように険しい視線を走らせた後、居丈高な調子で席を立ち上がった。
隠し扉を抜けて通路に出ると、血相を変えた部下たちが、切羽詰まった戦況報告を携えてアレッチェを待ち侘びていた。
「閣下、砦下の戦況は、我らにとって、かなり不利になっております。
インカ側の援軍の加勢を得て、ビルカパサ軍が反撃に転じ、その上、雷雨も強まるばかりで、火器を使いあぐねているアラゴン様の軍勢を圧倒しつつあります」
「その敵援軍を率いている者は誰だ」
「ラ・プラタ副王領の豪族、フリアン・アパサでございます」
「アパサ、だと……?」
アレッチェが喉の奥で低く呻き、その長い脚で、即座に通路の窓際に歩み寄った。
夜闇と嵐に霞む窓外を見晴らすアレッチェの掘り深い横顔で、強く噛み締められた奥歯が軋み音を上げている。
『此度の援軍の将が、あのアパサであるならば、なおのこと、人質としたわたしを盾に脅しても、決して屈することはないであろう。
アパサがいる以上、そなたの如何なる脅しも、二枚舌も、インカ軍には通用せぬ』
先ほどのトゥパク・アマルの言葉が、アレッチェの脳裏に甦る。
ペッ、と石床に唾を吐き付け、雷雨に濡れた窓枠にギリギリと拳を押し付けた。
爆音のように叩き付ける豪雨の彼方に聞こえくる戦さ場の喧噪に耳を欹てるも、砲撃音も銃声も鳴りを潜めているのは、インカ軍が優勢な証しでもあった。

(なんという情けない状態だ。
副王がアラゴン王子を戦場に繰り出してくるというから、我ら軍部は王子に戦功を上げさせるべく、どれほど神経を使ってきたことか。
この砦戦が始まって早々に、我らはトゥパク・アマルとビルカパサの軍を分断し、砦に誘き寄せたトゥパク・アマル軍を行動不能にさせた上、砦に潜入していたアンドレス隊の動きも封じた。
あとは弱体化したビルカパサ軍を攻め滅ぼせばよいだけの状態だった。
王子のために、これほどお膳立てをしておいたというのに、この醜態はなんたるざまだ。
アラゴン――!
副王嫡男という極上の称号と後ろ盾を持ち、戦場でもそこそこ使えそうな骨のある男かと思いきや、ひとたび逆境に陥れば、手も足も出ぬこの有様とは。
結局は、温室育ちの軟弱者にすぎぬ)
厳めしい肩をわななかせ、妖魔のごとき形相で戦場を睨(ね)め付けているアレッチェの傍では、部下たちが、彼の采配を乞い願うように平伏している。
彼らは皆、予測外の決定的劣勢に転じた自軍を前に、顔面蒼白となっていた。
そのような兵たちを、アレッチェの険しい相貌が振り向き、睥睨する。
そして、冷厳な声で命じた。
「即刻、アラゴン王子のお命をお助けせねばならぬ。
この砦の一角に、毒素の及ばぬ健康状態で、わたしの親衛部隊を待機させている。
せいぜい2〜300名にも満たぬ少数だが、予備兵力を温存しておいたことは幸いだった。
数は少ないが、親衛部隊は精鋭揃い。
その全兵をもって、王子の救出に向かわせよ。
その方策を伝える。
もっと近くに寄れ――」
部下たちを己の直近まで呼び寄せ、声を落とし、口早に策を伝ずる。
「大至急、行け。
王子の身に何かあっては、副王陛下に責を問われるのは、結局、我ら軍部の方だ。
王子のお命だけは、何があっても、お護りせよ」
「はっ!!」

(アラゴン、なんと世話の焼ける……!)
薄暗い通路を全速力で駆け去っていく部下たちの後ろ姿を見据えながら、胸の内で吐き捨てるように呟いたアレッチェの両の拳は、手の平に爪が喰い込むほどに、きつく握り締められていた。
「なぜ、これほど事態が悪化するまで、わたしに状況を伝えに来なかったのだ。
今となっては、手の施しようがない。
逐一、戦況を報告せよと、あれほど言っておいたであろう…!」
呪わし気に言い放ったアレッチェに、彼の護衛兵の一人が、言いにくそうに告げる。
「アパサの攻撃は電光石火で、見る間に我が軍の状況が悪化したことは事実であります。
なれど、報告の兵たちは、ずいぶん前から、その隠し扉の前でアレッチェ様を呼び続けておりました。
ですが、閣下は、一向に中から現われてはくれず、報告しようにも報告できぬ状態だったのであります」
「……」
護衛兵の言葉に、アレッチェは返す言葉を見つけられなかった。
捕虜としたトゥパク・アマルの方に意識を完全に奪われ、不覚にも、扉の外から送られ続けていた合図に気付かなかったのだ。

(いや、むしろトゥパク・アマルは、何もかも見通していて、敢えて、わたしの気を長々と己自身に引き付けていたのに相違ない。
アパサ率いる援軍によって、インカ側の有利な戦況が決定的になるまで、わたしに采配を振るわせまいと謀ったのだ)
そう気付けば、アレッチェの腸(はらわた)は、またも激しく煮え繰り返った。
トゥパク・アマルに対してはもちろんだが、トゥパク・アマルの思惑に填(は)まった己自身にも憤りを禁じ得なかった。
沸々と内奥に憤怒を燃え立たせながら、アレッチェが隠し扉を抜けて執務室内に戻ると、眼前に突き出された机上の降伏受諾書に目を落としているトゥパク・アマルの姿があった。
そちらに再び足を運びながら、トゥパク・アマルの胸中を探るかのように、彼の目から見ても忌々しいほどに整った相手の端正な横顔に、粘着的な視線を這い回らせる。
そうしているアレッチェの口元には、相変わらず苛立ちと怒りが色濃く滲んでいたが、しかし、次第に、それは薄い笑みへと変わっていった。
先ほどは言葉の応酬に気を取られて気付かなかったが、今、少し離れた位置から改めてトゥパク・アマルの様子を客観的に観察してみれば、その顔色は青褪めて、表情もどこか苦し気で、呼吸も浅い。
己を前にした先刻のトゥパク・アマルの態度が、余裕を漂わせるほど沈着で毅然としていたため見落としていたが、大広間で吸い込んだ毒素の症状が、実は、まだ抜けきれてはいないのだ。
いかに健康体を装って見せようとも、実際には、嘔気、めまい、頭痛、発熱などを今も重く引き摺っているに違いない。

アレッチェは、乾いた己の唇を舐めた。
衰弱しているなら、好都合――砦下の戦況が戦況だけに、トゥパク・アマルとの決着をここで一刻も早くつけてしまわねばならぬ。
何か決意にも似た思いで、そう胸の内で独り言(ご)ちて、彼は冷たい靴音を響かせながらトゥパク・アマルの面前へ戻っていった。
アレッチェは威圧的な態度で椅子に身を沈めると、手首に血が滲むほど縄できつく縛られた相手の両手の前に、打ち付けるようにしてペンを置いた。
その荒っぽい動作の刹那、尖ったペン先がトゥパク・アマルの左手の甲を掠め、その箇所に一筋の切り傷ができた。
かと見るや、傷口から鮮血が膨れ上がり、ツーッと、滑らかな褐色の皮膚を伝って机上に流れ落ちた。
「ちょうどよい。
おまえ自身のその血で、その書類に署名をしろ。
自らの大罪を自らの血で贖(あがな)った、この上ない降伏の受諾になる。
後々、この降伏受諾書を目にしたインカ兵や民衆どもの顔は、さぞ見ものであろう」
その表情にも、その態度にも、ありありとサディスティックな残忍さを曝け出しているアレッチェに目を向けたトゥパク・アマルの面差しにも、さすがに険しい憤怒が滲みだしている。
「砦下のインカ軍の戦況が有利になっている今、なぜ降伏せねばならぬ?」
「有利?
ビルカパサ軍は全軍壊滅したと言ったはずだ」
トゥパク・アマルの言葉を鼻で笑い飛ばし、アレッチェは厳つい双肩に圧倒的な自信を漲らせ、昂然と言い放った。
他方、トゥパク・アマルもまた、断固とした口調で食い下がる。
「このようなものに署名をしても無意味だ。
この反乱は、もはや、そなたやわたしの手の内から、とうに離れたものとなっているのだ」
降伏受諾書の表面に細々と並べられたスペイン語の文字列に鋭利な一瞥を走らせ、再びその視線を眼前のアレッチェに戻して、トゥパク・アマルが淀みない口調で続けていく。
「インカ帝国が侵略されて200年以上もの間、インカの民は、そなたたちの言語を絶する圧政に忍従を強いられてきた。
インカ帝国時代には1000万人を越えていた民の人口は、今や100万人もやっとという激減ぶり。

我らインカの末裔は、そなたたちの植民地政策という名の元、何重にも渡る税を搾り取られ、過酷な強制労働で命を削られ、辛うじて生き延びている者も屍同然であった。
このままインカの末裔たちが絶滅していくことを看過できず、やむなく我らは立ち上がったが、この戦いが、このように長期に渡り、広範囲に及ぶとは、わたしとて予測の範囲ではなかった」
「この大謀反人めが…!
いかなる言い訳をしようとも、反乱行為なぞが正当化される謂(いわ)れはない」
氷のように冷たく言い捨てたアレッチェに、トゥパク・アマルは口惜し気に唇を噛んだ。
「我らとて、流血を避けられぬ武力行使など、望んではいなかった。
憎しみは、憎しみしか生まぬ――故に、何年もの歳月をかけて、そなたたちとの話し合いを試みた。
なれど、そなたたちは、その話し合いの席に着こうとさえしなかった」
「トゥパク・アマル、おまえは、今さら、一体、何を言いたい?」
ありありと額に青筋を立てて苛立ちを露わにしているアレッチェの面前で、重厚な蒼いオーラを纏ったトゥパク・アマルが、流れるように美しいスペイン語で語り続ける。
「この反乱期を通じて、自らの意志で行動することを知ったインカの民たちは、精神的な強さや生命力の逞しさを取り戻している。
彼らは、今や、これまでとは違った、もっと真に人間らしい生き方があることを知っている。
そのために、己自身の自由意思と力で、その道を切り拓くことができることも知っている。
そのことは、インカの民だけのことではない。
遠くアフリカの祖国から引き離されて奴隷とされてきた黒人の者たちはもちろん、スペイン渡来の白人たちに甚だしい差別を受けてきた当地生まれの白人たちもまた、自らの意志で立ち上がり、この国に新たな時代をもたらそうとしている」
「シモン・ボリバル――!
スペイン人でありながら、革命などとほざいて我らに反旗を翻している、あの売国奴の青二才のことか?
あの男を焚き付けたのもおまえであろう、トゥパク・アマル」
机上で握り締めたアレッチェの拳が、またも激昂のためにわなないている。
そのような相手を鋭くも怜悧な瞳で見つめながら、トゥパク・アマルが、決然と応じた。
「確かに、あの者の革命運動も、きっかけは我らの起こした反乱行為であったかもしれぬ。
なれど、あくまで、一つのきっかけにすぎぬ。
そなたたちのような暴政が長く続けば、このような解放運動が起こることは、むしろ必然であった。
今この瞬間でさえも、自由と解放を求める怒涛のエネルギーが、激しく渦巻き脈動しながら、南米大陸の隅々まで広がりゆこうとしている。

もはや、この戦いは、我らの手の内にあるものではない。
このような紙切れ一枚、わたしの署名があったとて、何の役に立とうか」
「その書類の使い方や効果のことなど、おまえが心配せずともよい…!
おまえの血によって、おまえ自身に署名された降伏受諾書なれば、反乱軍を黙らせる充分な大義となり、法的根拠ともなる。
それに背く者は、インカ皇帝を標榜するおまえに背く反逆者となるのだ。
それでもまだ楯突くならば、インカ兵の残党どもや、すっかり生意気になった民衆どもが、最も衝撃を受け、最も落胆するような使い方を、いくらでも考え出してやる」
強度の憎悪と残忍さに炯々と両眼を光らせながら、アレッチェは転がっていたペンを掴み上げ、トゥパク・アマルの指の間にギリギリと押し込んだ。
と同時に、己の右手に銃を構え、撃鉄を起こす。
「トゥパク・アマル、おまえは、まだ自分が置かれている状況が分かっていないようだな?
おまえは、署名をするか、しないか、それを選べる立場ではない。
ただ、黙って、即座に、わたしの命令に従うのだ。
早くしろ!!」
「嫌だと言ったら?」
トゥパク・アマルの研ぎ澄まされた双瞼が、不動の深い光を宿したまま、血走ったアレッチェの目を射抜くように見返した。
「今、この場で、おまえを殺すのみだ」
凍てつく声で凄んだアレッチェの手が、銃口をトゥパク・アマルのこめかみに強くねじ込んでいく。
だが、トゥパク・アマルは、確固たる覚悟を宿した揺るぎない口調で明言する。
「ならば殺すがよい。
この命は、とうに天に預けている」
その言葉が終わるか否かという次の瞬間、アレッチェの握る銃身が、トゥパク・アマルの頭に猛然と叩き付けられた。
ガッ!!――と、銃底が頭肉を裂く生々しい音と共に、傷口から吹き出した血飛沫によって、トゥパク・アマルの漆黒の長髪が朱に染まる。
容赦の欠片も無くトゥパク・アマルの頭を銃で殴りつけたアレッチェの力は凄まじく、さすがにガッシリとしたトゥパク・アマルの身体も、半ば脳震盪(のうしんとう)を起こしかけてグラついた。
そんな彼の側頭を、またもアレッチェの銃身が、猛烈な勢いで横殴りに叩き付けられる。

そのあまりの勢いと力の激しさに、バランスを失ったトゥパク・アマルの身体は、椅子から石床に転がり落ちた。
倒れた彼の上に、呪わし気なアレッチェの言葉が降りかかってくる。
「いつまでも手を緩めていれば、いい気になりおって。
未開地の蛮族の首領ごときが、このわたしと対等に渡り合おうなどと…!」
憤激と憎悪に染まった赤黒いオーラを全身から燃え立たせながら、アレッチェは、床に打ち倒されたトゥパク・アマルの前にすかさず回り込むと、その至近距離から、硬い軍靴を思い切り振り上げた。
床上のトゥパク・アマルは、反射的に体勢を整えようとするが、それよりも早く、満身の力でアレッチェに蹴り込まれた軍靴が、彼の胴体に深々とのめり込んでいた。
「―――ゴホッ…!」
トゥパク・アマルの口から、真紅の血が、ドバッ、と噴き出す。
「死にたいなら、望み通りに殺してやる」
地底から湧き出すように低く嘯(うそぶ)くと、アレッチェの獰猛な蹴りが、再びトゥパク・アマルの腹部に、次は胸に、さらに背に、鉄槌の如く幾発も蹴り込まれていく。
対するトゥパク・アマルは、箍(たが)が外れたようなアレッチェの蹴襲(しゅうしゅう)を避ける術も無く、相手の為すがままになっている。
それでも、声ひとつ上げることなく、自らの血溜まりの中で、縛られた両手を梃(てこ)にして堪えながら、崩れそうな体を懸命に支えようとしている。
乱れた長髪が俯(うつむ)いた顔に降りかかり、表情こそ分からないが、苦しげな一呼吸ごとに小刻みに震える輪郭からは汗や血の雫が雨垂れのように伝い落ち、相当厳しい状態にあると見て取れた。
そんな相手の頭を足でガシガシと踏み躙(にじ)りながら、冷酷な眼で睥睨するアレッチェの鬼のような形相は、取り憑かれたような激しい憎悪や怒りと共に、どこか不気味な悦楽の色を帯びはじめる。
――このまま、本当に、殺(や)ってしまおうか。
幾度も煮え湯を呑まされてきた昔年の仇敵が、己の足元に平(ひれ)伏すような格好で、無残な苦悶の姿を晒しているのを目の当たりにするのは、自身の征服欲と優越性を少なからず満たしてくれるものであった。
その、ある種の快感が、アレッチェの加虐性を加速させていく。

凶器にも等しいその軍靴で、無我夢中で、果たしてどれほど蹴り続けていたのか、気付けば、足元のトゥパク・アマルは、ビクとも動かなくなっている。
ハッと、半ば我に返って、アレッチェは振り上げていた足を止めた。
実際のところ、トゥパク・アマルをここで抹殺することには、何の躊躇もありはしなかった。
全ては密室での出来事であり理由付けは幾らでも可能な上、対外的にも、大罪人の即時処刑という名目で道理が通り、己が咎(とが)めを受けることはない。
しかしながら、本当に息の根を止めてしまう前に、降伏受諾書へのトゥパク・アマルの直筆の署名は何としても欲しかったのだ。
そもそもトゥパク・アマルにこうして折檻(せっかん)を加えたのは、トゥパク・アマルが理屈で説得できぬことを知っていたが故に、毒素で衰弱している身体にさらに体刑を与えて脆弱化させ、力づくでも署名をさせたいがためであった。
にもかかわらず理性を失いかけた己をやや悔いながら、生きているのか息絶えているのか、血みどろになって、ぐったりと床に崩れているトゥパク・アマルの状態を探ろうとアレッチェは身を屈めた。
と、その時、彼は、不意に息を詰めた。
彼の視界に、外部からの合図を知らせるための、隠し扉横に据えられた例の回転金具に付属されたライトの光が、突如として飛び込んで来たのだ。
(――!)
その金具の回転速度と赤々と光るライトの点滅の激しさは、これまで類を見ぬほど切迫したものであった。
あの合図は、いつから送られていたのか…?
いずれにせよ、よほど砦下の戦況が、自軍にとって、悪化しているに相違ない。
それにもかかわらず、トゥパク・アマルへの折檻に夢中で、そちらに意識を奪われ、またも重大な合図を見落としていたのだ。
アレッチェは、奥歯をギリギリと擦り合わせた。
大至急、扉の外に出て戦況報告を受けて指示を飛ばさねばならぬが、かといって、死んだような状態のトゥパク・アマルの容体も早急に確かめねばならない。
一瞬の迷いの間、アレッチェの動きが止まった。

その刹那、時を待ち構えていたかのように、ぐったりと床に身を沈めていたはずのトゥパク・アマルが、目にも留まらぬ速さで上体を起こした。
「我を忘れ、わたしを早計に殺(あや)めてしまったかと案じたか?
大丈夫。
これしきのことではやられぬゆえ、安堵せよ」
アレッチェの眼前十数センチに迫る直近で、鮮血に染まったトゥパク・アマルの真紅の唇が、微かな笑みを浮かべて、そう動いた。
と見るや、トゥパク・アマルは、縛られた両手首をアレッチェの顔面に向けて振り上げ、と同時に、その手の中に握り締めていた何かを思い切り投げ放った。
「なっ?!」
死にかけているとばかり思っていたトゥパク・アマルの、至近距離からの思いがけぬ反撃に、アレッチェが目を見張る。
が、その時には、トゥパク・アマルの手の平から放たれた赤黒い粉末が、アレッチェの両目や口中に勢いよく飛び込んでいた。
――グアッ……!!
言葉にならぬ獣のような叫びを上げて、アレッチェが、咄嗟に両目と口を手で覆う。
言わずもがな、その粉末は、インカ軍のスパイス弾の中身でもあり、且つまた、燃やして有毒ガスを生成する原料としてスペイン軍が利用した、あの大量の唐辛子や胡椒の一部であった。
トゥパク・アマルは、囚われる前に広間で拾い上げていたそれらの粉末の一握りを、密かに隠し持っていたのだ。
「あああ…おのれっ…」
唐辛子や胡椒の粉末をまともに喰らって、目も喉も、燃えるような激痛や口渇に襲われ、床を這い回って悶絶しながら、アレッチェが懐から手探りで銃を抜き取った。
だが、今や盲目状態のアレッチェが銃を構えるよりも早く、猛然と立ち上がったトゥパク・アマルの鋼のように強靭な足が、その銃をアレッチェの手から瞬時に蹴り飛ばしていた。
カン、カン、カンッと、けたたましい金属音を響かせ、銃が部屋の隅まで遠く吹っ飛んでいく。
トゥパク・アマルの頭部や顔面に張り付いた長い黒髪は傷口から溢れ出す血で赤黒く染まり、痛々しく腫れ上がった額や唇からは今も紅い雫が滴り落ちている。
傷だらけの全身は半ばよろめくような動きながらも、トゥパク・アマルの鋭い眼光は、今も生気を失ってはいない。
「手荒なことをしてすまぬ。
なれど、今は、こうするより手立てが無かった」
トゥパク・アマルは低く囁き、半狂乱で目や喉を掻き毟って身悶えているアレッチェの姿に、痛まし気な視線を向けた。
しかし、すぐまた感情を排した厳しい顔に戻って、相手の傍に、にじり寄った。
「来るのだ」
アレッチェの耳元で有無を言わさぬ声でそう言って、縛られた不自由な手を用いて相手の肩を掴むと、トゥパク・アマルは、アレッチェの体を隠し扉の前まで引き摺っていく。
「この扉を開けよ。
わたしをここから出すのだ」
「馬鹿な…!
囚人の…おまえが、こ…のわたしに命ずる…というのか?」
「命じているのではない。
頼んでいる。
ここを開けてくれ」
「何を血迷ったことを言ってい…る。
なぜ…、わたしがおまえの言葉…に…従わねばならぬ!」
魔人ような相貌で息巻いたアレッチェの舌や喉は、唐辛子や胡椒が沁み込み、ますます強く痛み、痺れているのであろう。
息も絶え絶えな上、言葉の呂律も回っていない。
目の中にも相当量のスパイス類が混入していると見え、視界を失った目の端からは、大量の涙が滝のように流れ出している。
そのようなアレッチェを前にして、トゥパク・アマルは、険しいながらも、真摯でさえある声音で、諭すように応じた。
「アレッチェ殿、そなたとて、そのままでは、失明をしかねぬぞ。
一刻も早く、目や口を注がねば、重大な後遺症を残すことになろう」
「わたしを脅そうというのか……そのような手には…のらぬ。
そんなに出たければ、まず、おまえ…が、降伏受諾書に署名をしろ。
さすれば……ゴホッ…!!」
いきり立つあまりに、ますます深くスパイス類を吸い込んだらしく、アレッチェが激しく咳き込んだ。
そのようなアレッチェを見据えるトゥパク・アマルもまた、荒い息を吐き出しながら、実際には、ギリギリのところで起立姿勢を保っている状態である。
割れるような喉音を発して咳き込んでいる相手の様子に気を配りながらも、トゥパク・アマルは、縛られた両手で、隠し扉の周りを叩いたり、あれこれ触れたりしてみるが、やはり扉はビクともしなかった。
そんなトゥパク・アマルの様子を気配で感じてか、やっと咳の止まったアレッチェが、くっ、くっ、と卑屈な笑い声を漏らしている。
「無駄だ、おま…えには開けられぬ。
第一、扉の外に…は、わたしの衛兵たちがいる。
室外…に出ようとも、おまえに、逃げる術は無…い」

「それはどうかな?
砦内には、わたしの可愛い部下たちも、多数、潜入しているのだ。
きっと、わたしを懸命に探しておろう。
そのような彼らの目に留まれば、そなたの衛兵が今もこの扉向こうで安全にしている、という保証はあるまい」
「インカ兵ども…は、全員…、毒素にやられている」
しかし、トゥパク・アマルはそれには答えず、眦(まなじり)を吊り上げた峻厳たる面差しで、最後通牒を突きつけるが如く、今一度、アレッチェに詰め寄った。
「もう一度だけ言う。
即刻、この扉を開けるのだ。
さもなくば――」
「断る。
それより、おまえの署名が…先だ!」
そう言い切ったアレッチェの耳に、次の瞬間、ガタンッ、と、何かが倒れる音が響いた。
それに続いて、ボッと、何かが燃え上がる音。
と同時に、何かが焦げるような異臭と熱風が漂ってくる。
「トゥパク・アマル、おまえ…何を…している?」
ガンガン痛んで、まるきり霞んで見えぬ視界にもかかわらず、アレッチェが、執務室内の異変を直観して、周囲を見渡そうと懸命に首を振っている。
そのような彼の耳に、執務机の置かれている方角から、トゥパク・アマルの声が聞こえてきた。
「燃えるこの部屋ごと、わたしと共に心中したくなくば、その扉を開けるのだ」
「――!?
ま…さか……!
馬鹿なことはやめろ!!」
アレッチェが事態を察して叫んだ時には、既に、トゥパク・アマルは、降伏受諾書の上に、机上に据えられていた黄金の燭台を倒していた。
トゥパク・アマルの漆黒の瞳の中で、降伏受諾書が、金色の炎に巻かれて、たちまち灰と化していく。
それを見届けると、彼は、机上で燃え上がる炎の中に、さらに、辺りに積まれていた書類や手帳の類(たぐ)いを手当たり次第に焼(くべ)はじめた。
その都度、小さかった炎は、徐々にその大きさを増していく。

「やめろ!!
この部屋には重要書類が山ほどあるのだ!」
アレッチェの逼迫(ひっぱく)した怒声をよそに、トゥパク・アマルは、「さて、では次は、何を燃やそうか?」と嘯(うそぶ)きながら、新たな燃材を物色するかのように、スパニッシュ・マホガニー製の豪奢な書棚の方へ歩みだした。
そうしながらアレッチェの方に一閃を投げた時、対するアレッチェは、「よせ!それ以上、ふざけた真似は断じて許さん!!」といったようなことを喚(わめ)きながら、手探りで、こちらに突き進んでくるところであった。
殆ど視界が効いていないはずにもかかわらず、執念としか言いようのない猪突猛進ぶりに、思わずトゥパク・アマルも目を見張る。
と、その時、闇雲にこちらに驀進(ばくしん)していたアレッチェの体が、高さ1メートル半ほどあろうかと見える硝子張りのキャビネットに、側面から凄まじい勢いで激突した。
その強い衝撃波で、キャビネット上に載せられていた別の燭台が石床の上へ投げ出され、その燭台の炎が消えるよりも早く、衝撃によって開いたキャビネットの硝子扉から雪崩れ落ちた山のような書類が床に倒れた燭台の上へ降り注いだ。
さらに、不味いことに、キャビネット内にはカンテラ用の灯油瓶が納められており、その大瓶が、書類と一緒に燭台の炎の上に転がり落ちてきたのだ。
トゥパク・アマルが、アッと、息を呑む間も無く、灯油の大瓶は硬い石床に叩き付けられて砕け散り、中の油が周り一面に派手にぶち撒かれた。
ゴウッ、と不気味な音を上げて、灯油が床上の燭台の炎に着火し、と同時に、辺り中に舞い散った書類やら本やらに燃え広がった。
瞬く間に勢いづいた周囲の炎が、長身の二人の腰丈ほどに成長するまでには、ものの数秒もかからなかった。

「……!!」
キャビネット間近にいたアレッチェが、声にならぬ叫びを上げている。
盲目状態のまま立ち往生しているアレッチェの靴先に着火した炎が、彼の足首辺りまで上がってきていたのだ。
殆ど反射的に、トゥパク・アマルの体は、書棚の前から離れて、キャビネット傍のアレッチェの元へ走り込んでいた。
「しっかりしろ!」
みるみる足首からアレッチェの膝上の方まで駆け上ってこようとしている炎の舌を、未だ拘束状態のままの手を叩(はた)き付け、無我夢中で炎を払い除けながら、トゥパク・アマルが叫ぶ。
「気をしっかり持つのだ!
頭を下げよ。
煙を吸ってはならぬ。
このままでは、我らは本当に、ここで運命を共にすることになるぞ。
頼むから、隠し扉を…、扉を開けてくれ!」
そう声を張りながら、トゥパク・アマルは、縛られた手を己のビロードのマントに走らせた。
先刻受けた暴行による傷口から吹き出した血で濡れた部分を探り当て、そこを大きく引き千切ると、その布でアレッチェの脚に這い上がりくる炎を覆って叩き消そうと、力の限り奮闘している。
だが、そうしているトゥパク・アマル自身の方にも、火の勢いは迫っていた。
今や、炎は、部屋中にある燭台や可燃物に連鎖的に着火して、執務室全体を紅蓮(ぐれん)の火の海と化しつつあった。
正直、トゥパク・アマルも、己が初めに燭台の炎を倒した際、ここまで本格的な火災を招くつもりはなかったのだ。
もっと早い段階で、アレッチェが、扉を開く気になるものと予測していた。
室内のどこかに灯油燃料の類いが納められている危険性も想定してはいたが、まさか、それが即座に床に撒かれる羽目になるとは考えていなかった。
トゥパク・アマルは、血の混じった大量の汗をハラハラと横顔から流しながら、腫れ上がった唇を噛み締めた。
既に部屋中が灼熱の炎に包まれ、降り注ぐ火の粉の中で、今にも、全身ごと高熱で溶けそうである。

(アレッチェ殿……!)
薄まりゆく酸素や一酸化炭素の吸入で遠のきそうな意識の中、トゥパク・アマルは、未だ火を消し止めてやれぬアレッチェの大火傷の甚大な苦痛を思って、汗の滴る瞼を震わせた。
他方、アレッチェもまた、己の脚に巻きついている火を我武者羅(がむしゃら)になって消そうとしているトゥパク・アマルの気配を、朦朧とした意識の中で感じていた。
「トゥパク・アマル…なぜ、おまえは……敵のわたし…を」
足の重大な火傷に加え、周囲で踊り狂う炎の異常な熱さや吸い込んだ有毒煙のために、殆ど意識を失いかけているアレッチェの唇が、微かにそう動いた。
ちょうどその時、遮二無二(しゃにむに)火を消そうと躍起になっていたトゥパク・アマルが、やっとのことで、アレッチェの足に取り憑いていた炎を消し止めていた。
その気配を茫漠(ぼうばく)とした意識の中で感じていたアレッチェの耳に、遠く、トゥパク・アマルの声が聞こえてくる。
「そなたの火はなんとか消し止めた。
なれど、そなたの負った大火傷は、すぐにも治療を要する重症だ。
いや、それどころか、我らが火達磨になるか、その前に窒息死するか、一刻の猶予も無い。
そなたも、わたしも、このようなところで死ぬわけにはいかぬ!
共に、ここを生きて出よう。
後生だから、扉を開けてくれ……!」
アレッチェの耳に切れ切れに聞こえくる殆ど哀願するかのようなトゥパク・アマルの声は、恐らく彼が知る限りでは、これまでで最も悲愴で切迫したものだった。
そのトゥパク・アマルの形振(なりふ)り構わぬ必死さが、途切れそうなアレッチェの意識の底にある何かに、再び着火した。
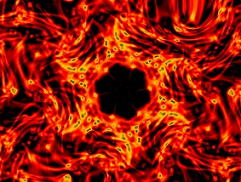
どこにまだそのような力が残っていたのか、アレッチェの腕が、周囲の火から庇うようにして盲目の己の体を支えていたトゥパク・アマルの全身を、ドッ、と、突き飛ばした。
「謀反人が、汚らわしい手で、このわたしに触るでない!
この偽善者めが!!」
ゴウゴウと燃え上がる煉獄の業火の中で、歯を剥き出して呪わし気に叫んだアレッチェの凄まじい形相は、もはやこの世のものとは思えなかった。
高熱の鉄板と化した床に打ち倒された身をよろめくように起こしながら、トゥパク・アマルは、暫し愕然と目を見開き、それから悲しげに瞼を伏せた。
「なぜ、これほどまでに我らの間は遠いのだ」
己の足元からも炎が上がってこようとしているのさえも気付かぬ様子で、その場に身を固めたまま、トゥパク・アマルは力無く項垂(うなだ)れかけた。
が、次の瞬間には、その唇が、ハッ、と大きく息を呑んだ。
「アレッチェ殿、危ない!!」
そう叫んで、トゥパク・アマルの全身は、アレッチェの躰を庇うために、瞬時に、そちらに飛び込んでいた。
視界を奪われているアレッチェには恐らく見えなかったのだが、彼の右横に高く聳えていた重厚なアンティークのシェルフ(収納棚)が燃え崩れて、その残骸が、アレッチェの頭上に降り注ごうとしていたのだ。

燃え崩れた木材がアレッチェに降りかかる寸でのところで、トゥパク・アマルの全身がアレッチェに体当たりするような格好で、まだ火の侵入の少ない、シェルフと反対方向にアレッチェを突き飛ばしていた。
「――なっ…?!」
均衡を崩して石床に横転しかけたアレッチェを護るために、身を挺して相手の上に覆い被さったトゥパク・アマルの背に、シェルフの残骸が燃えながら幾つも降り注いだ。
己の背に落ちかかりくる、それら残骸と化した角材を、トゥパク・アマルは即座に体から振り払いつつも、アレッチェがそれらの下敷きになることをギリギリ免れたことに微かな安堵の息をつく。
しかし、その安堵の念も、即座に打ち砕かれた。
己の体に庇われていたはずのアレッチェは完全に意識を失い、しかも滝のように汗を流して、ただならぬ苦悶の表情で息を荒げていたのだ。
トゥパク・アマルは瞳を微動させながら、アレッチェに覆い被さっていた己の身を離して、相手の頭部から足先まで視線を走らせていく。
「なんということだ…」
トゥパク・アマルの口元から、擦れた呻き声が漏れた。
アレッチェの全身を護って身を挺していたはずの己の体から、相手の左足が大きくはみ出しており、その左足の膝下に、全焼したシェルフから燃え落ちた50センチ四方大の重く鋭利な角材がザックリ突き刺さっていたのだ。
「しっかりせよ…しっかりするのだ……」
アレッチェに言っているのか、己自身に言っているのか、食い縛った歯の間から呪文のようにそう唱え、心を鎮めようと努めながら、汗と血が流れ込んで霞む視界の中で、アレッチェの足に刺さった角材や傷口の様子を懸命に見定めようとする。
幸い角材の火は消えてはいるものの、足への刺さり度合は深く、角材を不用意に抜き取ることはかえって危険を増すと思われた。
すぐにも医師の治療を要する致命的な重症であり、ともかくも、その傷口からドクドクと溢れ出る鮮血を止めるために、引き裂いたマントの布をアレッチェの左大腿部に縛りつける。
拘束されたままの不自由な両手で、それらを行うことは至難極まりなく、そうしている間にも、ますます手は焼けついて、感覚も定かではなく、熱ささえも殆ど感じられない。
手首に縛り付けられたままの太縄も、もう、すっかり焦げついて、今にも縄そのものが焼き切れるのではないかと思われるほどだった。

己の大きなマントの中に意識を失くしたアレッチェを包んで庇護しながら、トゥパク・アマル自身も意識朦朧とした状態で、炎の嵐が吹き荒れる密室の中をズルズルと扉の方へ這いずっていく。
そして、血を吐く思いで叫びながら、最後の力を振り絞って扉をガンガン叩いた。
「誰か!!
誰か、ここを開けてくれ!!!」
だが、外に助けを求めて叫ぶトゥパク・アマルの声も、長くは続かなかった。
大声を上げたために大量に煙を吸い込み、激しく咳き込みながら、ぐったりと頭(こうべ)を垂れた。
(――息ができぬ…)
火の粉を噴き上げながら燃え狂う炎が酸素を呑み込み、執務室内は、明らかに酸欠状態になりつつあったのだ。
紅蓮の炎の中、もはや火から逃れる力も、助けを呼ぶ力も無く、ハッ、ハッ…、と浅い呼吸を苦しそうに続けながら、遠のいていく意識の中で、トゥパク・アマルは、己の膝の上に庇っているアレッチェを見つめた。
大火傷と足の怪我と酸欠とで、気を失ったまま苦悶の呻きを上げているアレッチェの姿は、悲痛そのものである。
(アレッチェ殿、我らは共に、あの世から戦いの行方を見守ることになりそうだ)
そうアレッチェに語りかけたのを最後に、トゥパク・アマルの意識も、ついに事切れた。
――それから、どれくらい時間が流れたのか。
あるいは、すぐ次の瞬間だったのか。
トゥパク・アマルの意識は、朦朧としながらも、再び現実世界へ引き戻されていた。
いや、現実かどうかは実際のところ定かではなかったのだが、彼の意識は、今また、燃える執務室の中にいた。

『あなた、しっかりなさって』
あまりにも聞き覚えのある艶やかな女性の声がいたわるように耳元で響き、と同時に、しなやかな両手が己の頬を包む感触が伝わってくる。
燃えるような高熱を帯びた傷だらけの肌に、相手のひんやりとした柔らかな手の感触が心地よい。
スラリと細く長い相手の指の感触や、肌理(きめ)細かく滑らかな手の平の感触、そして、微かに薫る甘美な百合の香り。
トゥパク・アマルは、焦点の定まらぬ視線で、それでも、懸命に、相手の姿を見定めようと目を凝らした。
ほどなく、霞んだ視界の中に、ぼんやりとながらも、豊かな黒髪に縁取られた褐色の美しい輪郭が見えてくる。
エレガントな雰囲気と戦士のような凛々しさとを兼ね備えた風貌を持つ、その女性の黒曜石の瞳が、激しく揺れながら、こちらを見つめている。
『あなた……』
「ミカエ…ラ?!」
驚きを含んだ擦れ声を喉から発して、トゥパク・アマルが、鉛のように重い瞼を大きく押し開けた。
辺りでは、今も炎が猛々しく渦巻き、いよいよ空間の全てを呑み込もうとしている。
そのような炎をものともせず、意識を取り戻したトゥパク・アマルを深い安堵の眼差しで愛しそうに見つめながら、その女性――ミカエラは、涼やかな目元を細め、己の顔を夫の顔の方へ、さらに近づけた。
『まあ、なんと酷い、傷だらけではありませぬか。
唇もこんなに腫れ上がって』
ブロンズ像のような美貌に深く案ずる眼差しを宿しながら、ミカエラは、形良い指先で、スッと、夫の唇に触れる。
そのトゥパク・アマルの唇が、微かに動いて、思いを込めて囁いた。
「たとえ幻(まぼろし)であろうとも、最後に、そなたに会えて良かった。
今一度、本物のそなたに会いたかったが、今度ばかりは叶わぬようだ。
ミカエラ――皆のことを頼……」
言いかけたトゥパク・アマルの唇を、次の瞬間、ミカエラの唇が塞いでいた。

命を吹き込むように長く情熱的な口づけを交わした後、ミカエラは、ゆっくり己の唇を離し、美麗な目元に戦女神の如く強い光を宿して、決然と言う。
『何を情けないことを言っているのです。
あなたらしくもない。
あなたは、まだ生きねばなりません。
気をしっかり持つのです』
そう言い放ったかと見るや、彼女は、トゥパク・アマルの頬を包んでいた手を離して、その美しいプロポーションの長身で、夫の前に凛と立った。
いつしか彼女の両手の中には、黄金の大きな水瓶が、現われている。
ハッと、トゥパク・アマルが目を見張った時には、ミカエラは、その手に抱きかかえていた水瓶の水を、トゥパク・アマルに、そして、燃え盛る室内全体に、勢いよく投げ放っていた。
――ザバアッ!!
大きく水音が鳴って、大量の水飛沫が勢いよく降りかかる。
己に降りかかった水の冷たさや、あまりにリアルな水の感触が、それまでの夢か現(うつつ)か分からなぬ茫漠とした感覚を一気に吹き飛ばし、完全な現実感覚の中にトゥパク・アマルを引き戻していた。
そうしている間にも、次なる水の一撃が、威勢よく己の全身に投げ放たれる。

頭から爪先まで、ザンブリと水を被(かぶ)って、目を瞬かせているトゥパク・アマルの耳に、今度は、先刻のミカエラとは別の人物の声が大きく響き渡った。
「トゥパク・アマル様!!
しっかりしてください、トゥパク・アマル様!」
血相を変えて半狂乱で叫びながら、己の肩を抱き起している眼前の若者は、まぎれもなく己の若き副官、アンドレスであった。
「トゥパク・アマル様、気付かれましたか!!」
「アンドレ…ス…どうやって、ここに……?
ミカエラは…?」
「トゥパク・アマル様、しっかりなさってください!
何を仰っているんです?!
ミカエラ様が、このようなところに、いらっしゃるわけがないじゃないですか。
ここは砦の中の、アレッチェの執務室の中です。
しかも、すごい火災で、俺たちが来るのがもうちょっと遅かったら、トゥパク・アマル様は、ここでアレッチェと一緒に丸焼けになってしまうところだったんですよ!」
尋常ならざる大怪我や火傷を負いながらも、無事に意識を取り戻したトゥパク・アマルの姿を前にして、言葉に尽くせぬ深い安堵感のために、アンドレスの声音はどうしても大きくなる。
「ああ、そうであった…、そうであったな。
どうやら、わたしは、まだ生きているようだ」
さすがにトゥパク・アマル自身も安堵の念を禁じ得ず、まだどこか意識朦朧としながらも、傷だらけの口元に微笑を浮かべた。
その間にも、アンドレスは、開け放たれた隠し扉の中に、水桶を持って次々に走り込んでくる部下たちに、「もっと、もっと、水を!!二人に、それに、部屋全体に!一刻も早く火を消し止めねば」と、指示を飛ばしている。
それから、アンドレスは、半ば涙を滲ませた大きな瞳を揺らしながら、滔々と水の滴るトゥパク・アマルの無事な姿を、再び感動を込めて見つめた。
彼は、即座に懐剣を取り出すと、トゥパク・アマルの手首を縛っていた太縄を、掻っ切った。
「トゥパク・アマル様、もう、これで大丈夫です。
だけど、大至急、お怪我や火傷の手当てをせねばなりません」
「いや、わたしは大事ない。
案ずるな」
アンドレスと話すうちに徐々に意識が清明になってきたようで、トゥパク・アマルの表情には、次第に生気が戻りつつあった。
「それより、アンドレス、そなたたち、どうやって、この部屋の扉を開けたのだ?」
「あいつが、隠し扉を外から開けるための鍵を持っていたんです」
そう言って、アンドレスは、肩をすくめて笑顔をみせながら、執務室の中央へ目をやった。
彼の視線の先には、インカ兵たちに囲まれながら、苦虫を何十匹も噛み潰したような顔で立ち尽くしている、でっぷり体型のスペイン人将官がいた。
それは、ロレンソが投石技で捕えていた、あのサルセード大佐――この砦戦におけるアレッチェの副官、であった。
「捕虜となっていたサルセード大佐が、彼自身の命と引き換えに、この隠し扉を開けてくれた、というわけです」

「なるほど」と、トゥパク・アマルも合点がいって、太縄から解放された己の手首をさすりながら頷いた。
「では、大佐殿はわたしの命の恩人というわけだ。
彼には深く感謝せねばならぬな。
大佐殿との約束は必ず守り、彼の命は確実に保証せよ。
とはいえ、大佐殿に扉を開けるよう依頼をしたのは、ここに隠し扉があると、先にそなたたちが見抜いたからであろう?
隠し扉は、外からは扉と分からぬ構造になっていたはず。
なのに、なぜ扉の位置が分かったのだ?
いや、それより、重傷を負ったアレッチェ殿はどうなっている?!」
アンドレスは、心配そうにトゥパク・アマルの双眸(そうぼう)を覗き込みながら、「トゥパク・アマル様、今は、あまりお話されてはいけません。お身体に障ります」と、難しい顔をした。
そうしながらも、真剣に問いかけてくるトゥパク・アマルの目線に押されるようにして、噛み締めるように答える。
「トゥパク・アマル様のお姿が見えなくなってから、俺たちは、砦中、隅々まで、どんなに必死に探し回ったと思いますか?
そうしている最中、俺の部下の一人が、この通路の方向から走ってきた何人かのスペイン兵たちが、大慌てで砦外へ飛び出していくのを目撃したのです。
恐らく、アレッチェの伝令兵たちか誰かだったのでしょう。
それで、俺たちも急いでこちらに来てみれば、壁しかないように見えるこの通路に、アレッチェの衛兵たちが、何人も配備されているじゃないですか。
その様子から、ここに何か重要なものがあるって、すぐに検討がつきました。
あとは衛兵たちを締め上げれば…、この隠し扉を見つけるのは、そう難しくありませんでした。
ただ、この扉を開ける鍵を持ったサルセードが強情でなかなか言うことをきいてくれなくて、扉を開けるまでに時間がかかってしまったんです。

「そうであったか。
さすがに、此度は、心底、そなたたちを待ち侘びた。
来てくれて、誠に有難い。
心から礼を申すぞ」
トゥパク・アマルは、眼前のアンドレスに、そして、いつしか己の傍に跪いていたロレンソの方に、それから、周囲で同様に深く案ずる面差しのインカ兵たちに、視線で篤く礼を払った。
そんなトゥパク・アマルやインカ兵たちの耳に、不意に、サルセード大佐の悲痛な叫び声が響き渡った。
「あああ、アレッチェ様、なんたるお姿に!!
とんでもない火傷をなさっている上に、足が血だらけじゃありませんかっ」
その動転したサルセードの叫びに呼応するように、アンドレスがトゥパク・アマルに向かって語を継いだ。
「アレッチェが左足の大怪我と全身火傷で、意識を失っています。
でも、まだ何とか息はありますが…。
トゥパク・アマル様だって、ひどいお怪我ですし、アレッチェと、一体、何があったんです?
アレッチェに酷い暴行を受けたんじゃないですか?!」
息せき切ったように問うアンドレスに、トゥパク・アマルが表情を引き締めて答えた。
「詳しい説明は後だ。
それより、すぐに腕の立つ従軍医を呼び寄せ、アレッチェ殿の治療に当たらせてくれ。
彼は、見ての通り、非常な重症を負っている。
かつて、わたしが砲弾に倒れた時に見事な治療を成し遂げた名医がいたでだろう。
あの者がよかろう。
すぐに本営に使いをやって、彼を呼び寄せよ」
対するアンドレスは、「分かりました」と答えながらも、微妙な面持ちになる。
「俺たちインカ軍や民衆たちを散々な目に合わせてきたアレッチェに、そこまで好待遇を与えなくてもと、正直、思いますが…。
ですが、トゥパク・アマル様がそれでご納得されるのならば、お言葉のままにいたしましょう。
ですから、さあ、もう、お話にならないでください。
トゥパク・アマル様ご自身も、大変なお怪我や火傷をなさっているのです。
陛下こそ、早急な治療が必要です」
アンドレスがそう言って会話を切ろうとするも、トゥパク・アマルの問いかけは止まらない。
「いや、まだだ。
教えてくれ。
砦外の戦況はどうなっている?
ビルカパサに預けた本隊は持ち堪えているか?
砦内で毒素に倒れた兵たちの様子はどうなのだ?」
「アパサ殿の援軍が到来し、ビルカパサ軍も健闘しており、おまけに豪雨のおかげもあって、砦外の戦況は我が軍に有利です。
さあ、細かいことは、順次お伝えしますから、どうか今は、もうこれ以上、お身体のご負担になる会話はおやめください」
厳しく制したアンドレスの言葉とは裏腹に、トゥパク・アマルは、「やはりアパサ殿が来てくれていたか」と納得気に独り言(ご)ち、両足に力を込めて真っ直ぐ立ち上がった。
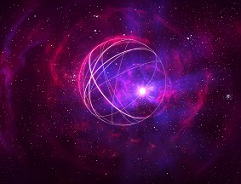
彼は、インカ兵たちの果敢な消火活動によって執務室内の炎が次第に鎮火されていくのを目に収めると、まだ覚束(おぼつか)ぬ足取りながらも、隠し扉の外に向かって歩き出した。
「トゥパク・アマル様、おやめください!」
「そのような火傷やお怪我の体で、どこに行こうっていうんです?!」
血相を変えてトゥパク・アマルの前に立ちはだかったアンドレスとロレンソの肩を、トゥパク・アマルの両手が、真摯な思いを込めて、ぐっと握り締めた。
「ありがとう。
なれど、案ずるには及ばぬ。
そなたたちのおかげで、充分に水を浴び、すっかり楽になった。
戦場で命のやり取りをしている兵たちに比べれば、このようなわたしの怪我など、かすり傷にすぎぬ」
そう言って、トゥパク・アマルは、隠し扉の外に広がる薄暗い通路の空気を胸に吸い込み、「たいぶ砦内の大気中の毒素も薄まってきているようだな」と、安堵を込めて呟いた。
トゥパク・アマルは、そのまま通路の方に進み出て、その長大な通路の石壁に等間隔に築かれた窓の一つに歩み寄った。
そこから、砦下に広がる戦場に、険しい視線を走らせる。
いつしか時は深夜にさしかかり、まもなく日付も変わろうとしている。
分厚い雲に覆われた天空からは、今も大粒の無数の雨が槍のように落ちて地表に突き刺さり、その水浸しの大地の上では、雨や泥土に塗(まみ)れた兵や馬たちが入り乱れ、熾烈な白兵戦を続けていた。
先刻のアパサによる水袋投下作戦や降りやまぬ豪雨のために、もはやスペイン軍の大砲や銃は使い物にならぬと見え、完全に鳴りを潜めている。
両軍の兵は、共に、剣、槍、斧などの武器を手に、肉弾戦を繰り広げているが、ドロドロの泥土に塗れ、全身に血飛沫を浴びて、それらが降りしきる雨水で混ざり合い、その上、夜の闇の暗さもあいまって、誰がどちらの軍の兵なのか、見分けることさえ困難な状態である。

それでも、様々な戦場を目に収めてきたトゥパク・アマルの心眼は、先刻のアンドレスの報告通り、今、確かにインカ軍が優勢である――どころか、殆ど勝利しているといってもよいほど優勢であることが、夜闇や雷雨を貫いて見通せた。
(アパサ殿、ビルカパサ、見事な戦いぶりであった)
そう胸の内で、トゥパク・アマルは、アパサに、ビルカパサに、そして、全ての戦場の兵たちに深く礼を払った。
しかしながら、暗黒の夜空を蒼白く染め上げて不規則に走る雷光に照らし出される地上を、砦窓から見下ろすトゥパク・アマルの横顔には、険しさが増していく。
「このような時間に、このような混戦状態で、これ以上の戦いは無用。
視界も足場もあまりに悪く、長時間に渡る戦いで両軍の兵共に消耗が激しすぎる上、これでは味方討ちを誘発しかねぬ。
アンドレス、ロレンソ、そなたたちは兵を連れてすぐに眼下の戦場へ下り、アパサ殿とビルカパサに、戦さを休止するよう伝えよ」
「ですが、トゥパク・アマル様、砦下のスペイン軍を率いる敵将が、まだ捕縛されておりません」
窓から吹き込む風雨に全身を弄(なぶ)られながら食い下がるように言うアンドレスに、トゥパク・アマルも、激しい雨に煙る戦場を見つめたまま、「うむ」と頷いた。
「あの砦下で、アパサ殿やビルカパサと剣を交えている敵軍は、これまでアレッチェ殿が率いてきたスペイン軍本隊を凌ぐほどに、重装備の非常に強壮な別働隊であった。
アンドレス、あの敵軍を総(す)べる敵将の正体について何か分かったか?」
「はい。
副王ハウレギの嫡男、アラゴン王子であるとの情報を得ています」
若々しい面持ちを凛々しく引き締めて答えたアンドレスの方に、トゥパク・アマルは敏捷に視線を馳せて、「副王の嫡男?なるほど、されば、あれほどの重火器を備えていることにも頷ける」と、噛み締めるように呟いた。
再び眼下の戦場に目をやったトゥパク・アマルの鋭利な横顔を、耳を劈(つんざ)く轟音と共に天駆ける稲妻が、白銀の光で皓々と照らし出す。
そのような主君に真っ直ぐ向き直り、アンドレスは、腰に佩(は)いた帯剣の柄を強く握り締め、決然と語を放った。
「陛下、そのようなアラゴンを放置すれば、今後、我が軍にとっては、アレッチェ以上に厄介な相手となりかねません!
せっかく我が軍が優勢な今こそ、手を緩めることなく、アラゴンとの決着を付けてしまうのが得策ではないでしょうか?」

しかし、トゥパク・アマルは、戦場を睨んだまま、きっぱりと首を振る。
「そなたの言いたいことは分かる、アンドレス。
だが、此度は、もう手遅れであろう」
「手遅れとは?」
「副王の嫡男ともなれば、とうに手を打っているであろう、あの者が」
そう答えて、トゥパク・アマルは、まだ燃え燻(くすぶ)る執務室内でインカ兵たちに看護されている意識不明のアレッチェへ一瞥を投げ、それから今一度、アンドレスへ、さらに戦場へと視線を戻していく。
そうしながら、トゥパク・アマルは、物思わしげに語り続ける。
「この豪雨や夜闇は、我らインカ軍にとって、重火器に頼った戦いを得意とする敵軍を封じるのには誠に好都合であった。
なれど、同時に、敵兵が身を隠して逃げ去るにも好都合なものなのだ。
ましてや副王の嫡男ほどの重要人物なれば、恐らく、アレッチェ殿が、自軍に不利な戦況を察した時、即、アラゴン王子を救出するための方策を打っているに相違あるまい。
この期に至っても、未だアラゴン王子が、囚われても、討ち取られてもいないとなれば、口惜しいことなれど、此度は取り逃がしたと思うしかあるまい」
同じ頃、砦下の戦場の一角では、今、まさにトゥパク・アマルとアンドレスが語り合っていたアラゴン王子その人が、差し迫った状況の真っ只中にいた。
本来ならば眩いばかりに白銀に輝く鎧も、飛び散る泥土や打ち付ける雨水でドロドロに汚れ切り、彼の跨る純白の戦馬も泥水を浴びて変色し、さらに不味いことに、馬の足がぬかるみに取られて立ち往生している。
その彼の周りを、鋭すぎる眼光を炯々とさせた一団が、グルリと取り囲んでいたのだった。
激しい雨や夜闇に視界を阻まれている上、誰もが頭頂から爪先まで泥水や血糊や戦塵に塗れ、もはや髪色も肌色も顔立ちも判別できぬ状態で、己を囲んでいる軍団が、味方のスペイン兵なのか、はたまた敵のインカ兵なのか、それさえもアラゴンには見分けることができなかった。
とはいえ、その軍団の兵たちが携えている武器が斧や棍棒などの鈍器であることや、彼らの身に着けているものが、鎧などではなく、簡素な貫頭衣であることなどから、己が敵兵に囲まれているのだと察することは難しくなかった。
しかも、そのインカ兵と思しき軍団は、いかにも隙が無く、野獣が集団で獲物を狩るがごとき統制のとれた動きで、軽々と重々しい鈍器を身構え、じわりじわりと己を取り囲んでいる包囲網を狭めてくる。

(――くっ…!)
アラゴンは強く噛み締めた唇の隙間から、苦々しい呻きを漏らした。
平素は、ひときわ誇り高く、感情的に取り乱した姿など見せぬアラゴンではあったが、この時ばかりは、いやに重く感じる剣を右手に携え、左手で懸命に馬の手綱を繰りながら、雨や汗が滴り落ちる美貌を引き攣らせている。
そんな王子の前では、彼の重側近たる副官エドガルドが、緑碧色の瞳をこれ以上無いほど険しくさせて、敵前に馬ごと全身を晒して立ちはだかっていた。
エドガルドは、今にも飛びかかり来ようと身を低めている野獣のごとき集団から、己の命に代えても主を護ろうと、雷雨さえも弾き返さぬばかりの気迫と覇光を漲らせ、あらゆる方向からの攻撃にも応ずるべく長剣を隙無く身構えている。
ついに、何匹も――と形容したくなるほどの獰猛さと、敏捷さで、インカ兵と思しき者たちが群れ成して、まずエドガルドの方へ向かって、泥土を派手に弾き飛ばしながら一斉に跳躍した。
アラゴン王子の前に身を挺したまま、エドガルドが決死の剣を振うが、目にも留まらぬ速さで続々と飛びかかり来る野生児のごとき男たちの、その数の多さと、鋭敏さと、剛腕さに、エドガルドの卓抜した剣技も歯が立たない。
己の上に黒山の人だかりとなって群がり来る男たちに押し潰されるような格好で、エドガルドは馬上から地面へドゥッと転げ落ちた。
そんな彼に体勢を立て直す一瞬の隙も与えず、「敵兵」と思しき野生児たちが、横転したままのエドガルドの上に何人も飛び乗って、完全に身動きを封じる。

その時、群の中の大柄な一人が、グワッと歯を剥いて、雨土で黒々と汚れた顔を、噛み付かぬばかりの勢いでエドガルドの耳元に近づけてきた。
かと見るや、さすがにエドガルドも自身の耳を疑ったのだが、意外にも、その相手は、篤(あつ)い礼のこもったスペイン語で囁きかけてきたのだ。
「エドガルド様、このような乱暴を働き、ご容赦ください。
我らは、アレッチェ様の親衛部隊でございます。
わたしは、その親衛部隊長ドロテオと申す者。
アレッチェ様のご命令にて、インカ兵どもに身を扮し、アラゴン王子を救出に上がりました。
どうか今は何も仰(おお)せにならず、我らの為すに任せてください。
全てはアラゴン様を無事に安全な場所に退避させるためでございます」
泥水溜りの中に押し倒され、羽交い絞めにされて、矢のように真上から降りつけてくる雷雨に全身を打たれながら、混乱する意識の中で、エドガルドは目を剥いたまま絶句している。
確かに、ドロテオと名乗った相手の今の言葉通り、全身に褐色の泥土をこすりつけて、鈍器を携え、貫頭衣を身に纏ってはいるが、すぐ直近で良く見れば、その人物は、まぎれもなくスペイン兵の一人であった。
アレッチェの親衛部隊長であるというドロテオが率いる周囲の「敵兵」たちにも素早く目を転じれば、先ほどは野蛮なインカ兵にしか見えなかった一団の者たちも、そう分かってみれば、なるほど、皆、スペイン人に相違なかった。
彼らの人数がいかほどかは数えようもなかったが、少なくとも数十人か、いや、百人を超えているかもしれないとも思われた。
インカ兵に扮した彼らは、いかにもエドガルドを捕えて攻撃しているかのような素振りを見せながらも、『エドガルド様、今は全てを呑んで、ご容赦ください』と、自分に懸命に視線で詫びている。
屈辱を通り越して驚愕しているエドガルドが、泥の中に打ち倒された状態のまま、今度はアラゴン王子の方に目をやれば、案の定、アラゴンも、己と同じく、インカ兵に扮したアレッチェの親衛部隊員たちに、その身を「拘束」されていた。
エドガルド同様、アラゴンも、荒っぽく馬から蹴落とされて、泥の中に鎧ごと身を沈めさせられている。
力任せに身動きを封じられたアラゴンの鎧に鈍器を打ちつけるような振りをしながら、アレッチェの親衛隊員たちが、アラゴンの耳元に何かを懸命に訴えかけている。
だが、アラゴンは、エドガルドとは異なり、このような方法にはどうしても納得しかねるようだ。
「こんなやり方で、尻尾を巻いて戦場から逃げ出せと、わたしに言うのか?!
ええい、放せい!!
身を隠して遁走(とんそう)するなど――…末代までの恥となろうぞ!
それぐらいなら、敵兵の手にかかり、堂々と討死する方がまだマシだ!!」
激怒したアラゴンのヒステリックな喚き声が、今やこの戦場全体を席巻(せっけん)している本物のインカ兵たちの耳に届くのではないかと、エドガルドの心臓は凍りつく。

しかし、叫んでいたアラゴンの声は、即刻、有無を言わさぬ沈黙の中に押し込められた。
蒼白になりながら、泥水の中で死んだように息を潜めて見守るエドガルドの朦朧とした視界の中で、アラゴンは、インカ兵に扮したアレッチェの親衛隊員たちに、大きな麻袋を鎧ごとスッポリ被せられて、さらに、その麻袋の表面には、辺りの水溜りから跳ね上げた泥をかけられ、すっかり闇色の物体に仕立て上げられていた。
睡眠薬でも嗅がせられたのか、麻袋の中のアラゴン本人も、もはや何をされても小声ひとつ漏らさない。
そのアラゴンを包んだ大袋を、特に図体の大きい親衛隊員たち数名が、インカ兵を装った姿のまま、筋骨隆々たる腕で横向きに――つまり、アラゴンの体が水平になるような向きで――ガッチリ抱え込んだ。
かと見るや、彼らは、その格好で雑踏の中に身を沈め、夜闇と雷雨に全身を紛らせながら、敏速な足取りで戦場の外に向かって走り去っていく。
全ては瞬時の出来事であったが、一連の成り行きを息を殺して見守っていたエドガルドにとっては、永遠にも思える長い時だった。
一目散にアラゴンを運び去っていく一団の後ろ姿が見えなくなると、彼は、やっと泥の中から身を起こして、深く息をついた。
先ほどアラゴン王子が声を荒げた時には肝を冷やしたが、王子がインカ兵たちに見咎(みとが)められて仕留められてしまう前に、アレッチェの親衛隊員たちの強引ながらも迅速な立ち回りによって、辛うじて脱出をはかれたことには、さすがに安堵の思いがあったのだ。
エドガルドは、まだ己の傍に控えていたアレッチェの親衛隊長に、低く囁きかける。
「そなた、アレッチェ殿の親衛部隊を率いるドロテオ、と申したな?
さすがに我が国きっての精鋭揃いと誉れ高い親衛部隊だけある。
見事な変装ぶりに、わたしもすっかり騙されたぞ」
「はっ、畏れ入りまする」
「それで、砦のアレッチェ殿は、いかがされている?」
「はっ…、それが、我らにアラゴン様の救出を命じた後のアレッチェ様の動向は、我らも掴めておりません」
「そうか。
アレッチェ殿自身のための親衛部隊員まで我らのために繰り出させてしまうことになろうとは、アレッチェ殿には、誠に申し訳の立たぬことをした。
戦況がここまで我らに不利になった今、アレッチェ殿の安否が案じられる」
さんざん泥溜まりの中に体を沈められ、普段の優美な風貌は見る影もない姿ながらも、エドガルドは大地の上に毅然と立ち上がると、再び長剣を身構えた。

今もインカ兵に成りすましたままのドロテオと互いの武器を交えて戦っている様子を演じながらも、エドガルドは素早く相手の耳元に顔を寄せ、鋭い口調で語を放つ。
「今の状況では、我らは火器を使えぬ上、あまりの悪条件の中、被害も消耗も激しすぎる。
対するインカ兵たちは、身体能力も持久力も我らに勝り、このような混戦状態の肉弾戦こそ彼らの得意とするところ。
もはや我らにとって勝機の見えぬ戦いは無用。
これ以上の犠牲を出すよりも撤退をするが、今は賢明。
アラゴン王子さえ無事でいてくれれば、今一度、態勢を立て直し、再起の時を窺うのが得策であろう」
天駆ける稲妻の雷光を浴びて、緑碧色の瞳を炯々と青光りさせて言うエドガルドに、ドロテオもグッと顎を引いて応じた。
「御意――!」
にわかに兵を退(ひ)きだしたアラゴン軍を逃がしてなるかと、アパサ軍の兵たちが追撃態勢に入っている。
敵味方が激しく入り乱れた接近戦と化していたため、いざや退くとなっても、それはアラゴン軍の兵たちにとって容易いことではなかった。
だが、今や戦場は、水煙が立ち上るほどの酷い土砂降り状態である。
天から叩きつける雨脚は、鉄壁の水のカーテンとなって、数センチ先の視界さえも遮断する。
それでも、アパサは、戦場を駆け回って執拗に敵兵を追い求め、さして大柄でもない肉体のどこから湧き出るのかと思えるほどの猛烈なパワーで、特大の戦斧を振るっていた。
しかし、さすがのアパサも、狂ったように降りしきるゲリラ豪雨の中で敵兵を次々に見失い、奥歯をギリギリと噛み締めて厳つい双肩をわななかせている。
彼は、強度の憤激のために、野生児のような散切り頭の髪を逆立たせ、天を仰いで吠え上げた。
「おい、雨っ!!!
おまえは俺たちの味方なのか、それとも、敵どもの味方なのか?!
もうちょいで副王直下の大敵を完全に打ちのめすことができたってのによぉ!!」

とはいえ、どんなに天に向かって管巻(くだま)いてみても、この悪天候の中で、これ以上の戦いの続行は、味方の兵のためにも無理があると、さしものアパサ自身も察していた。
そう理屈では分かっていても、腹の底では、自軍が優位であったという思いがあるだけに、アラゴンを取り逃がした上、このような中途半端なかたちで戦さの続行が困難になってしまったことが口惜しくてならなかったのだ。
そのようなアパサの耳に、ゴウゴウと滝のように唸る雨音の向こうから、聞き覚えのある若者の声が懸命に呼びかけているのが聞こえてきた。
「アパサ殿!!
そこにいるのはアパサ殿ですよね?!
ああ、やっと見つけました。
この豪雨だし、誰も彼もが泥だらけだし、探すのに難儀しました。
とにかく、やっとお会いできて良かったです。
俺です、アンドレスです!
トゥパク・アマル様の伝令でまいりました」
雨音に負けじと己に向かって声を張りながら、雷雨の壁の向こうから近づいてきた若武者のシルエットの方を、ハッとアパサも振り向いた。
と見るや、アパサの鋼のように強靭な腕が、近づいてきた若者の胸倉に、いきなり掴みかかった。
「ア、アパサ殿…?!」
その若者アンドレス――彼は、トゥパク・アマルの指示で、アパサに休戦を促す伝言を携え、懸命にアパサを探し出し、やっとのことで彼の元に辿り着いたところであったのだが――は、アパサに本気で首を締め上げられて目を白黒させている。
一方、アパサは泥鼠のようになった顔をアンドレスの鼻先に齧(かじ)りつきそうなほど近づけ、グワッと鋭い歯を剥き出して、がなり出した。
「アンドレス!!
おまえ、今までどこにいた?!
おまえも、トゥパク・アマルも、大事な戦いの最中には、まるで影も形も見えやしねぇ!
それが、今頃になって呑気に現われやがって。
どこかで高いびきでもかいて、眠りこけていたんじゃねえだろうなっ?!」
「も、申し訳ありません…!
トゥパク・アマル様も、俺も…敵の砦の中にいました。
砦の中でも…いろいろあったんです。
詳しいことは後で話しますから…今は休戦を…と、トゥパク・アマル様からの伝言で……」
もの凄い剣幕で捲(まく)し立てられ、強く首を締め上げられたまま、アンドレスは息絶え絶えに声を絞り出した。
だが、アンドレスの胸倉を掴んでギリギリ締め付けるアパサの指は緩まない。

「あの重要な局面で、俺とビルカパサだけに戦わせやがって。
アラゴンを取り逃がしたのも、おまえたちの責任だぞ!」
雨水さえも弾き返さぬばかりの激昂のオーラを燃え立たせ、吐き捨てるように言い放ったアパサに喉元を抑え込まれたまま、アンドレスは、弁明することはおろか、呼吸さえもできずに顔色を失っていく。
そんなアパサとアンドレスの方へ、ついにアパサの部下たちが見かねて飛び込んできた。
「アンドレス様、しっかりなさってください!」
「お頭(かしら)、放してやってください!
ほんとに死んじまいますよ!!」
アパサの部下たちが、アパサとアンドレスの間に寄って集(たか)って割って入って、やっとのことで二人を引き離した。
アパサの手から解放されて、アンドレスは、しばらく激しく咳き込んでいたが、そうしているうちにも彼の表情は満面の笑顔に変わっていく。
「なんだか懐かしいです、この感じ。
ああ、本当に、本当に、アパサ殿なんだ!!
どんなにお会いしたかったことか!」
雨の中で嬉しそうに叫んだかと思いきや、今度は、アンドレスの方から、まるで無邪気な子どものように、大きく腕を広げてアパサに抱きついた。
今では、長身のアンドレスが中肉中背のアパサの背丈を軽く越えていて、体型的にも逞しく成長したアンドレスの胸の中にアパサが埋まってしまうような格好ではあったが。
「砦下の戦場で、アラゴンたちがあまりに強くて、もうダメかと思った時に、予想もしなかった援軍が現われてくれた時の、あの時の気持ちはとても言葉にできません。
どんなに、どんなに、有難かったか!」
そう歓喜の声を上げながら、いっそう力強くアパサを抱き締めるアンドレスの腕の中で、今度はアパサの方が赤くなったり黒くなったりしながら悲鳴を上げている。
「気持ち悪いぞ!
放せ、ええい、放さんかっ!!」

そんな彼らの周囲に集まったアパサの部下やインカ軍本隊の兵たちは、やんやと二人を囃(はや)し立てながら、ピューピュー口笛を吹き鳴らしたり、拍手喝采したりして面白がっている。
豪雨は相変わらず彼ら全員の上に勢いよく降り注いでいるのだが、その雨音さえも、今は、まるで地表の鍵盤をリズミカルに奏でる音楽のような響きに変わっている。
やがてアンドレスは、その胸からアパサを離し、未だ感動の醒めやらぬ瞳で、眼前の師をしみじみと見つめた。
このアパサは、トゥパク・アマルにとって最も有力な同盟者であると同時に、アンドレスにとって、武術から戦術指南まで、何年にも渡って厳しくも丁寧に指導を施してくれた恩師でもある。
やがてアンドレスは我に返ったように、辺りに集ってきている大勢の兵たちにも視線を馳せて、真摯な眼差しで礼を払い、それからまたアパサの方へ顔を戻した。
「さあ、アパサ殿、砦の中に参りましょう。
アパサ殿の部隊の皆々も、インカ軍本隊の者たちも、限界まで戦い尽くしてくれました。
砦で何があったかは後で詳しく話しますから、今は、アパサ殿とご一緒に、皆をすぐにも砦内に引き揚げさせてください。
敵を追撃しようにも、この豪雨では限界がありましょう。
それに、さすがに誰もが、全力を出し切り、疲れ切っている。
戦場に山のように溢れ返っている負傷兵たちを一刻も早く助け出し、早急に治療もせねばなりません。
このような冷たい雨の中に、大怪我を負っている彼らを長時間放置することはできません。
幸いにも負傷を免れた者たちだって、充分な食事や休息が必要です。
さあ、アパサ殿も、俺と一緒に砦に戻りましょう」
他方、アパサは、アンドレスの言葉に耳を傾けながらも、変わらぬ難しい表情で、ギュッと腕を組み、傲然(ごうぜん)と胸を反らしている。
「アンドレス、おまえ何を呑気なことを抜かしてやがる。
アラゴンの行方を掴めぬまま、のうのうと休んでなどいられる道理があるか。
すぐに追撃せねば、完全に取り逃がすことになる上、あやつの残党どもに反撃の機会を与えることにもなるのだ」
そう言いながらも、アパサは、その険しく鋭利な双眸(そうぼう)で、周り中に集まったインカ兵たちに、ぐるりと視線を馳せる。
いずれの男たちも生気は失ってはいないものの、誰が誰なのか判別不能なほど血糊や泥にまみれ、過酷な天候の中で長時間に渡って強敵と戦い続けたことによる苛烈な消耗が、ありありと滲み出している。
さらに、彼らのすぐ足元や背後や、否、広大な戦場のありとあらゆる場所では、敵味方双方の死傷した無数の兵たちが倒れ込み、滔々と傷口から流れ出る血を大雨に洗われ、戦場の大地を朱に染め上げていた。
眉根を強く寄せて瞑目しているアパサの葛藤的な心境を察しながらも、アンドレスは、憔悴した戦場の兵たちの思いを代弁するかのように、言葉を選びながら、語を継いでいく。
「まだ此度の戦闘の双方の被害状況は正確には把握できてはいませんが、それでも、我が軍同様、アラゴン軍の被害も決して軽いものではないと思われます。
彼らが即座に態勢を整えられるとは考えにくい上、たとえ、それが可能であったとしても、少なくともすぐには当地での戦闘は望まないのではないでしょうか」
「なぜ、そう思う?」と、凄んだ声で言い放ち、アパサが目を開けて、片眉を吊り上げた。
「我らインカ軍が、あの敵砦を我らの手中に収めたからです」
「――!」

「あの砦には、どれほど多くの要塞砲があると思いますか?
いくら副王直下のアラゴン軍が比類なき強壮な火器を備えているとしても、我が軍の手に渡ったあの砦の大砲群をまともに相手にしたいと思うでしょうか?」
そのアンドレスの言葉に、アパサの炯々たる黒眼が、光を強めて大きく見開かれた。
「あの敵砦を占拠したのか?」
「まあ、実質的にそのようなかたちになりました。
それというのも、アパサ殿が援軍として来てくれたおかげで、アラゴン軍を撃退してくれたために他なりません。
それに、砦を守備していた敵軍の親玉アレッチェも、意識不明になって我らの手の内におりますし、アラゴン軍も撤退してしまった今、あの砦を護る敵兵は、とりあえず当地にはいなくなりました。
とはいえ、アレッチェ隊の兵たちが、砦内にたくさん残ってはいますけれど。
ですが、その砦内の敵兵たちも、自軍の撒いた毒にやられて、皆、今も意識を失っています。
我が軍の砦内の兵たちも、未だ毒にやられて意識不明なのは同じですが…」
「なに、敵の撒いた毒?
砦の兵が、敵味方共々、意識不明だと?」
「毒と言っても、俺たちインカ軍が武器として使った大量の唐辛子弾や胡椒弾の粉末を、敵軍が掻き集めて燃やして発生させた天然の軽い有毒ガスにすぎなかったんですが。
それでも、大気中に撒かれたそれらを吸い込んだ砦内の誰もが、意識不明になって、倒れてしまうには充分でした」
ますます意味が分からんという不審顔で己をジロジロと眺め回しているアパサに、アンドレスは「まあ、砦に行ってみれば分かります」と軽く肩を竦めて答えた。
「それよりも我らも一旦、砦に退いて、態勢を整え直さねばなりません。
皆に休息を与え、それに、動ける者たちは皆で力を合わせて、戦場の負傷兵たちを一刻も早く救出し、風雨を避けられる砦内に移送して、治療を施さねばなりません」
アンドレスの言葉を聞いているのかいないのか、ますます眉間に強く皺を寄せながら難しい顔をしているアパサに、アンドレスが、真摯な声音で畳み掛ける。
「いずにしても、アラゴンが戻る先は、最終的には、首都リマの王宮でしょう。
アパサ殿の懸念は俺も分かりますし、それに、アラゴン、ひいては、その父たる副王ハウレギとの決着は、遠からず、何らかのかたちでつけねばなりません。
でも、そのためにも、今はインカ兵たちの力を充分に温存し、高めておくことが必要です。
皆、今宵、どれほど死力を尽くして戦ってくれたか、アパサ殿が一番よく分かっているはずではありませんか。
さあ、アパサ殿、兵たちと共に砦に引き上げましょう。
トゥパク・アマル様も、どんなに会いたがっているか知れません」
「トゥパク・アマルは、無事にしているのか?」
あれほど先刻はトゥパク・アマルのことも毒づいていたアパサであったが、アンドレスに向ける彼の眼差しには、深い安堵の念が宿っている。
それがアパサの本音なのだと感じながら、アンドレスは笑顔で力強く頷いた。
一見、ひどく荒っぽく傍若無人で、傲慢な印象さえ与えるアパサの言動や態度の裏側に、比類ない篤い情を秘めていることをアンドレスはよく知っている。
「トゥパク・アマル様は、ご無事です。
あ、でも、ひどいお怪我や大火傷を負っていますけど」
「ひどい怪我や大火傷だと?
何があったのだ?」
平静を装おうとしながらも鼻腔をひくつかせて声を上擦らせているアパサの背を軽く押して、アンドレスは砦に向かって歩みだした。
「全て砦に行けば分かります。
さあ、アパサ殿も、部隊の方々も、はやく参りましょう。
トゥパク・アマル様も、どんなに首を長くして待っていることか!」
渋々ながらも歩み出した師匠の横を進みながら、アンドレスは、周囲に漂う血の臭いに混ざって、風に乗って微かに潮の香りが流れてくることに気が付いた。
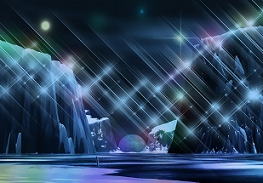
そういえば、そこが、すぐ海の傍であったことを、そして、日中には海上で英国艦隊と砦のスペイン軍との間で熾烈な戦いがあったことを不意に思い出す。
(ずいぶん前のことのように感じるが、昼間のあの海戦も酷いものだった…。
陸地にも、海辺にも、たくさんの負傷兵たちが溢れている。
彼らを急いで救出しなければならない。
今夜は、まだまだ忙しくなりそうだ――)
そう内面で呟きながらも、漂いくる清々しい潮の香りが、アンドレスの心に、今やっと、ささやかな平安をもたらしていた。
★☆★☆★<註:「副王」について>★☆★☆★
この物語の舞台である「ペルー副王領(かつてのインカ帝国の中心地)」は、物語の時代にはスペインの植民地であり、この時代、当地にはスペイン副王ハウレギが最高権力者として君臨し、過酷な植民地政策を敷いていました。
なお、スペイン国王自身は、スペイン本国におり、スペイン本国を治めていました。
※但し、当作の内容は、ほぼフィクションであり、史実とは異なりますので、どうぞご容赦ください。